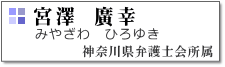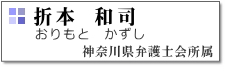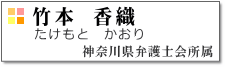今から2年余り前に提訴した、横浜市内にある総合病院における生後11か月の乳児に対する肝生検後の死亡事故に関する損害賠償請求訴訟の弁論期日が本年1月29日に横浜地方裁判所において開かれました。
この裁判では、この間、ずっと弁論準備手続という、法廷ではない場所で手続が行われていましたが、今回の期日は公開法廷における弁論手続に戻してもらいました。
その理由はいろいろあるのですが、一番大きな理由は、当時、本件事故に関わった複数の医師から、被告病院の医師らの過失による死亡事故であることについて真実を伝えたいという申し出をいただけたということによるものです。
私たちは、この内部告発を受け、この病院の体質といえるかもしれませんが、事故の背景にある実態といったことも含め、公開法廷でそのことを正面から訴えるべき時期に来ていると判断をしました。
まだ事件が終わったわけではありませんが、そのことについてご報させていただきます。
なお、確認したところでは、翌1月30日付の神奈川新聞の社会面でこの期日のことが取り上げられていました。
今回は、公開法廷で意見陳述を行いましたので、その原稿を転記する形でご報告ということにしたいと思います。
長くなりますが、以下、ほぼ原文のままで引用して掲載いたします。
↓
本日の弁論期日におきまして、時間を取っていただき、まずは裁判所に御礼申し上げます。
通常の民事事件で審理中途で意見陳述を行うことは比較的稀なことかと思いますが、本件については、弁論準備手続を重ねていた間に、様々なことが起きており、それによって判明した事実もございます。
その結果、本件事故自体、そしてその後の対応も含めて本件に関する被告の悪質さがより明らかとなってもおりますので、これらの事実について、本日提出の準備書面、証拠を踏まえて、意見陳述させていただきたいと思います。
まず、本件は、被告の運営する病院において、生後11か月の乳児に対する肝生検が実施され、それから数時間後に急変して死亡したという症例であり、司法解剖においても「肝生検に起因する出血死」と明確に結論付けられております。
にもかかわらず、被告側はずっと肝生検後に出血が生じていたこと自体を争い、ミトコンドリア肝症による急激な代謝異常で生じたことだとして、肝生検後の経過観察における過失をも否定して争っているわけです。
本日提出した2通の準備書面では、この点に関する被告主張が虚構であること、本件は極めてシンプルな「肝生検に起因する出血死」の症例であり、肝生検後の経過観察で多々あった出血兆候を見逃し、出血に対し適切な対処を怠ったことによって、体内の血液の2分の1を優に超える出血を来し、生後11か月の乳児を死なせたもので、被告が法的責任を負うべきことが明白な事案であることを、医学的な知見と事故関係者の陳述書などを基に詳細に指摘いたしました。
準備書面の要旨は以下のとおりです。
まず、本件では、肝生検後、脈拍数が分あたり200を超え、呼吸数が分あたり60を超え、さらに口唇チアノーゼ、四肢冷感、亡尿などの、明らかに出血によって生じたと見られる症状、所見について、たとえば、発熱は出血によるショックとは矛盾するであるとか、多呼吸だとクラスⅡのショックにあたるはずとしながら、拡張期血圧が上昇していない等として、あくまでショックではなかったとし、出血が起きてないといった主張を行っていますが、そもそも発熱はサイトカインの影響で起きるもので、出血性ショックと矛盾しないし、クラスⅡのショックではない根拠とされた拡張期血圧については被告病院では異常が現れて以降そもそも測定すらしていないにもかかわらず、「上昇していない」として、ショックを否定する根拠としているわけです。
わかりやすくいえば、ショックに陥っていたことを否定するために、嘘の情報、誤った医学的知見を紛れ込ませているといっても過言ではありません。
結局のところ、本件における被告の主張は、6回もの穿刺を行った肝生検後の出血で普通に説明のつく事象を、出血とは無関係であるとこじつけようとしているにすぎず、およそ医学的にも合理性のない主張なのです。
本件事故では、肝生検当日の午後3時50分ころに急変していますが、その直後のレントゲン写真でも明らかな出血所見が確認できます。
被告は、乳児は脂肪組織が少ないため、はっきりと写らないことがあるなどの医師の意見書を証拠として提出し、出血はなかったとしていますが、前日の写真では臓器がくっきりと写っているのでその差は一目瞭然ですし、今回、内部告発をした当時救命に関わった医師も、このレントゲン写真で、肝臓の周囲がくっきりと写っていないことから出血が確認できると陳述書で明言されています。
被告が誤った情報で責任を言い逃れようとしていることは、ミトコンドリア肝症に関する主張においてより顕著となります。
そもそも、ミトコンドリア肝症は、極めて稀な疾患です。
この点、被告が主張の拠り所としているミトコンドリアの形態異常は、本件の場合、およそ典型的なものではありませんし、形態異常は、ミトコンドリア肝症の鑑別において特異性がなく、続発性、つまり他の疾患から二次的に発現することがあるとされているもので、およそ鑑別の決め手にはなりません。
被告もそのことは承知しているためか、患者に現れた所見、身体的特徴を根拠にミトコンドリア肝症が疑われるなどとの主張を行っています。
しかし、被告が取り上げた「強度の貧血」「凝固異常」「中等度以上の肝障害」といった所見は、すべて急変後のものであり、これまたすべて出血性のショックが非代償期に陥っていることと矛盾しないものです。
現に、死後の解剖においても、ショック肝、ショック腎であったことが指摘されており、肝臓にも腎臓にも、心臓にも血液がなかったことが確認されています。
逆に、肝生検前には、貧血も、凝固異常も、中等度以上の肝障害もなかったわけで、それが肝生検後わずか数時間の間に進行し、大出血を来すことなどあるはずもありません。
ちなみに、急変後、強度の貧血を来した点についても、被告は出血では説明がつかないと言い切っていますが、急激な出血が起きると、血管外から水分が血管内に戻って来るため、血液は希釈されることになりますし、本件では肝生検開始前から輸液が行われており、肝生検後には輸液量が倍に増量されたという事実もあり、この輸液によっても血液は希釈されることになります。
要するに、被告は、出血に関する基本的な医学的知見も無視し、さらには、本件で輸液が実施されていたことも無視して、誤った医学的評価でもって責任を逃れようとしているもので、これは一例にすぎず、被告のこのような手法は枚挙に暇がないといっても決して過言ではありません。
今回、私たちは計40ページに及ぶ準備書面を提出しましたが、かなりの部分を、被告の虚偽主張を医学的に論破するために割いており、怒りを通り越して、あきれるくらいなのです。
本件では準備書面を2通提出しましたが、2通目の準備書面は、今まで述べたことを踏まえつつ、本件における真実をより明らかにするためのものです。
弁論準備手続が行われている間に、私たちは、本件事故等、被告病院に勤務していた複数の医師から内部告発を受けており、今回の手続で、2名の医師の陳述書を証拠として提出いたしました。
いずれの医師も、本件事故に直接関わっていた方ですが、両医師とも、本件事故が「肝生検に起因する出血死」であり、被告病院の医師らの過失さえなければ救命できていたはずだと断言しています。
また、内部告発の中には、被告病院において直近で同種事故が起きていたことの指摘もありますので、その点を含め、被告の有責性についてもはや争う余地のないものであることを準備書面において指摘しております。
告発をしてくれた医師の内のお一人は、本件事故に直接関わり、肝生検施行後の患者の容態観察を行っていて、刑事手続で書類送検された当時の研修医の方です。
同医師は、「本件事故は肝生検に起因する出血死であると認識していることを前提に、自身が肝生検後の経過観察に直接関わり、出血を疑うべき状況を確認していながら、上級医の指示に従い、出血に対する対処をせず、そのまま経過観察を続けた過失を認め、それがなければ救命できたはずである」と述べておられます。
また同医師は、遺族である原告らに謝罪の手紙を渡されていますので、その手紙も証拠として提出しております。
同医師は、陳述書や手紙で、何か重大なことが起きていると思い、上級医に何度も相談に行ったが、対応してもらえなかったことを具体的に述べ、その後経験を積んだ医師として事故を振り返り、本件事故については「当然に出血を疑うべき状況であった」として、「出血を疑って対処をしなかった過失」を認め、その過失さえなければ救命できていたと明確に述べてくれています。
もう一人の内部告発者である医師は、現在も、済生会系列に勤務されている医師であり、勇気をもって告発していただきました。
同医師は、急変後の蘇生に関わった方ですが、やはり本件事故について極めて重大な事実を述べておられます。
同医師は急変から1時間半あまり経過した時点でエコー検査を実施した医師ですが、このエコーで肝臓の周囲、つまり外側ですが、出血の所見を確認したそうです。
同医師は、急変直後のレントゲン写真を確認し、同写真でも出血所見があることを明言しており、やはり、本件が肝生検に起因する出血死であることを明言しております。
このエコーについては不可解な事実もあります。
同医師は、エコー画像をプリントアウトしたそうですが、その後、このエコー写真は病院内で紛失したそうです。
また、裁判で被告は、当初診療経過一覧表で、同医師のエコーで、カルテの記載通り、腹腔内出血を疑う所見と診断したことを認めていたのですが、後になって、腹腔内出血は認めず、肝被膜下血腫と言い換えています。
しかし、この点について、同医師は自身の認識とは異なるし、そのように述べたことはないと断言しておられます。
端的に申し上げれば、被告側は、裁判の手続が進行するなかでも、自身に不都合な事実を捻じ曲げるような対応を重ねていることになり、非常に悪質というほかありません。
同医師は、本件事故に関連して、もう一つ重大な事実を指摘しておられます。
それは、本件事故に先立って、被告病院内で肝生検に起因する出血事故が起きていたという事実です。
同種事故の有無については、すでに求釈明を行っておりましたが、被告は、同種事故の存在を明らかにしておらず、もし同医師の指摘どおりであれば、この点でも被告は虚偽の回答をしていたことになります。
告発した医師によれば、この同種事故は、本件事故の1~2年前に、同じ小児肝生検チームが行った肝生検の後に起きた事故で、被告病院には小児外科がないため対処できず、世田谷にある国立成育医療研究センターに救急ヘリで搬送され、一命を取り留めたとのことです。
研修医の方は本件事故の年に被告病院に来ている医師で、その事故のことは知らないそうですが、上級医は当然知っていたことになります。
仮に肝生検後の出血事故であったとすれば、その教訓がまったく生かされず、本件事故の発生につながったもので、その意味でも同種事故の内容は非常に重要な意味を持つことになります。
私たちは、この内部告発を踏まえ、再度の求釈明を申し立てました。
今度こそ、被告側が誠実に対応してくれることを強く求めます。
本件ではほかにも重大な問題があります。
その一つが電子カルテの改ざんの事実です。
この改ざんの経緯ですが、事故後の遺族との話し合いの中で、病院側が「死因は不明だが、病院に責任はない」等の極めて不誠実な対応を行ったため、不審を感じた遺族が司法解剖を希望し、未明に警察介入となったのですが、その明け方に電子カルテの改ざんが繰り返されます。
実際、穿刺回数を少なくするであるとか、肝生検の1回目はリアルタイムエコー下ではなかったといった記載を削除するといった改ざんが行われています。
この電子カルテの改ざんの手法は、確定履歴の改ざんではなく、仮登録状態にした中での改ざんであるため、通常の証拠保全手続ではまず入手できないというものです。
一般の方には理解しづらいことかもしれませんが、このやり方がまかり通るのであれば、事故の事後的な検証はおよそ不可能になりかねないというもので厚労省が定めた電子カルテの原則に反するとも考えられますので、あわせて問題提起したいと思います。
以上、本件について述べさせていただきましたが、詳細な医学的反論に加え、2名の医師の内部告発もありましたので、本件事故の法的責任の有無ということでいえば、すでに決着は着いたといっていい事案です。
事故に関わった医師が自身の過失を認め、医師が適切に対応していれば救命できていたと述べて、謝罪している事件で、被告がさらに争い続けることは、単に不毛ということにとどまりません。
かけがえのない生後11か月のお子様を失った遺族に対し、医学的にでたらめな主張を重ねることで、さらなる苦しみを与え続けているのだということを、被告、そして被告病院の関係者の方々は、強く自覚し、反省していただきたいと心から願っています。
医療事件を扱っていると、あるべき医療とは何かということをいつも考えさせられます。
私たちは、本来、医療者、医療機関を断罪したいと考えているわけではありません。
医療事故が完全になくなることはないのかもしれませんが、医療者、医療機関が、常に事故を真摯に反省し、教訓とする姿勢で臨んでいただければ、不幸な事故を減らすことができます。
「患者のための医療」は、突き詰めて行けば、「医療者の幸福」にもつながるのだと確信しています。
最後に、本件については年末ぎりぎりに刑事事件に関し、不起訴処分が出されていますが、ご遺族の意向を踏まえ、近日中に検察審査会に審査請求の手続を取る予定です。
刑事事件についてのお話はまたいろいろありますが、そのことについては申立時点でご報告したいと思います。