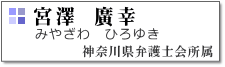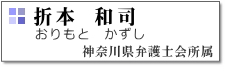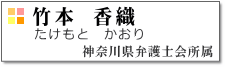横浜市内のある総合病院で起きた、生後11か月の乳児に対する肝生検後の死亡事故に関する、当時担当医であった被疑者に対する業務上過失致死被疑事件について、本年6月下旬に出された検察審査会における不起訴不当の議決を受けての再捜査の結果、本年8月6日に、嫌疑不十分不起訴の判断が維持される結果となりました。
私たちは、この間、多くの医療関係者、警察関係者ともお話をし、また今回の嫌疑不十分不起訴の判断を維持した担当検事ともお話をしておりますが、まもなく10年という月日が経過しようとする時点まで待たされ続けた挙句、あまりに不可解な不起訴処分が出されたことによって非常なショックを受けられたご遺族の心情を踏まえ、あらためて、本件の経緯を含めてご報告させていただくことといたしました。
まず、事件の実体、性質からすれば、私たちは、検察審査会における不起訴不当の議決には非常に重い意味があると考えておりました。
そこで、議決後、私たちは、新しい担当検事と面談し、この間に入手した証拠やこれまでの調査、検討に基づく、事件の真相や法的評価について資料を携えて説明をしました。
担当検事にとっては、限られた時間の中で検討しなくてはならないので、この説明は、事案のポイントについて理解してもらうための協力をしたいという考えによるものでした。
私たちは、公訴時効期間満了までわずか2ヶ月しかないという状況ではあるものの、本件事故における医師の過失は明らかで、適切に対処していれば救命できたはずであること、そして、事故後の隠ぺいなどの対応の悪質さなどからすれば、当然起訴されるべき事案であることを強く訴えました。
そして、7月末までに意見書を提出することを検事と約束し、その約束どおり意見書も提出しました。
ところが、担当検事は、私たちの意見書が7月中に提出されることを承知していながら、その前に、ご遺族に対し、“報告”があるので検察庁に来てほしいと連絡を入れて来たのです。
弁護士同席の上でということになり、8月6日に私たちは検事のもとに赴きました。
すると、検事は、いきなり、嫌疑不十分不起訴にしたという結論を伝えたのです(上記の“報告”があるとの連絡を受けたのが意見書提出前ですから、その時点で不起訴の結論は決めていたことになるわけで、まあ、それも失礼な話ですが・・・)。
それに対して、理由を尋ねたところ、検事は、「本件が肝生検に起因する出血死」の事件であるとの前提に立ちながら、以後の経過について「肝生検後の出血を疑う状況と評価することは難しい」などとして、容態が悪化してから数時間もの間、何の精査もせず、「経過観察」としたことにつき、起訴はできないと判断したと述べました。
しかし、元々、肝生検には出血などの合併症のリスクがある上、特に本件の肝生検は、呼吸が止められず、肝臓が上下するリスクの高い乳児が、手技中にベッド上で体動が激しく、ブリッジをして肝臓が上下している状況で鎮静もせず、小さな肝臓を複数回刺し(担当医のカルテに明確に記載されています)、都合6回の穿刺が繰り返されたという、出血の合併症を来すリスクが高い症例であり、当然ながら、術後管理はより厳重に行われなくてはならないことは明らかでした。
ところが、肝生検後、1時間半後には脈拍数が分あたり200を優に超え、呼吸数も60台に上昇し、さらには発熱、チアノーゼ、四肢冷感など、出血兆候、出血性ショックを強く疑うべき所見が現れ、その状況が延々と続いてアラームが鳴りっぱなしだったにもかかわらず、医師らは、2時間以上もの間「経過観察」を続けるのみで何らの精査をしなかったというもので、このような異常事態について、「出血を疑う状況と評価することは難しい」との検事の説明に、私たちは一瞬言葉を失いました。
私たちは、これだけの異常所見が揃っていながら、「肝生検後の出血を疑う状況と評価することは難しい」と判断した根拠を検事に尋ねたのですが、そこで、さらに検事は驚くべき説明を展開します。
それは、「意見を求めた2人の医師が、『私でも経過観察をしていたと思う』と言っているから」というものでした。
私たちは、医療事件を扱っていて、明らかに中立性、公正性に欠ける不合理な鑑定意見書をしばしば目にします。
本来、あってはならないことですが、現実には、医療機関や保険会社の意向に沿った、身内庇いとしかいいようのない意見書が出され、協力医の方が呆れかえるということは決して稀なことではないのです。
もちろん、患者側が提出する意見書であっても、医学的知見に基づいたものでなくてはならないわけで、結論がどちらに寄っているにせよ、大切なことは、述べられている意見が正しいものか否かが医学的な見地からきちんと検証されなくてはならないということです。
しかし、担当した検事にそのような姿勢があるようには到底感じられませんでした。
上記の2人の医師の意見については、そこで述べられている見解の医学的根拠を丁寧に検証していけば、その誤謬に容易に気づくことができるはずだし、本件はまさにそのような事案だからです。
そんな検事の説明に対して、ご遺族から「2人の医師とおっしゃいますが、その分母はいくつですか」と尋ねた場面がありました。
すると、検事は、言いにくそうに「9人です」と答えたのです。
つまり、9人のうちの2人だけが「私でも経過観察をしていたと思う」と述べたということは、ほかの7人はそうではないと言っていることになります(もっとも、話しているうちに、もう1人微妙な意見の医師がいるという説明が加わりましたが)。
もちろん、このような問題は多数決で判断することではなく、医学的知見に基づく見解としてどちらが正しいかの話ではありますが、「経過観察と判断し続けたことに問題がある」と判断した医師の方が圧倒的に多いにもかかわらず、そちらを無視して、「私でも経過観察をしていたと思う」という意見があったことをことさらに強調して、起訴はできないとの判断を正当化しようとする姿勢には違和感しかなく、強い憤りを感じざるを得ませんでした。
ほかにも、検事はご遺族の面前で信じがたいような発言を繰り返します。
たとえば、血液検査は結論が出るのに時間がかかるなどとして、血液検査をしなかったことを正当化するような発言をしたので(時間がかかることが、検査をやらないことを正当化する理由にならないことはいうまでもありませんが)、「しかし、腹部エコー検査はベッドサイドで簡単にできるし、出血兆候を容易に確認できるのだから、それすらやらなかったことは過失といえるではないか」と述べたところ、「エコーをすれば、体が動いて、かえって出血が増えるリスクもある」などとして、エコーをやらなかったことを正当化する説明をしたのです。
しかし、患者は乳児であり、看護師が体を抑えれば済むことですし、そもそも、異常所見の原因を精査しなければ手遅れになることだってあるわけで、およそ本末転倒というほかないのですが、とにかく、検事の説明は、万事が万事、そんな感じでした。
また、当時の研修医で被疑者の一人となっていた方が書いた陳述書には過失があったことを認める記述があるのに、なぜそれを無視するのかと聞いたところ、これに対しても、驚くべき返答が返ってきました。
まず、陳述書の中には、当時の過失を明確に認める記述があるにもかかわらず、「当時、過失があったということを認めたものとは読めないと判断した」と強弁するのです。
もし、本当にそう思うなら、研修医の方の事情聴取をすべきではないかと尋ねたところ、その必要はないと判断したと答えるばかりでした。
ちなみに、過失の前提となる出血死の予見可能性について、検事は「そこはグレー」という言い方を何度かしていたので、「予見可能性がグレーというなら、なおのこと、事故の当事者である当時の研修医に話を聴くべきではないか」と迫りましたが、「もう結論は決めたので、事情を聴くつもりはない」と開き直るような受け答えでした。
さらに驚いたのは、検事が、「当時の医療水準では、経過観察としたことに問題はない」と述べたことでした。
確かに医療過誤で「医療水準」が問題になることはありますが、出血性ショックに対する対処は、医師にとってイロハのレベルの問題で、10年前も今も、やるべきことに何ら変わりはなく、医療水準など、およそ問題になる余地はありません。
率直に言って、この検事は、医療事故をまともに扱ったことがないのではないかとすら感じました。
とにかく、こんなやりとりが2時間余り続いたのですが、強く感じたことは、「不起訴という結論が先にありき」だったのではないかということでした。
実は、去年の年末に不起訴と判断した検事との会話でも強くそういう印象を持ったのですが、必要な補充捜査もせず、必要な医学的な検討もろくにしないまま、不起訴不当の議決からわずか40日で「嫌疑不十分」という結論を維持した検事に対しては、心の底から、「法律家として恥ずかしくないのか」「真相を解明して正義を実現しようという覚悟はないのか」と、強い憤りを感じながら私たちは席を立ったのです。
率直にいえば、本件の場合、少なくとも5年以上もの間、検察官がずっと警察からの送検の受理を拒み続けたという怠慢も非常に重大な過誤なのではないかとも思いますし、不起訴不当議決後に担当することになった検事にとっては、とばっちりのような面があるようにも感じています。
実際、今回対応した検事も、私たちとのやりとりの中で、時間不足で十分検討できなかった面があることを認めていました(それを認めて不起訴とすること自体、ひどい話ではありますが)。
しかし、ご遺族にとっては、いい加減な捜査の繰り返しで幕を引かれ、幼い子を失ったことについて正義が実現されないこと、そしてそれをおよそ納得できないような説明でごまかそうとされたことは本当にショックなことであり、お二人が落胆される様子を見て、私たちも本当につらく、持って行き場のない憤りとやるせなさを感じました。
ともあれ、刑事事件としてはこれで一区切りとなります。
事件の真相については確信を持っておりますので、今後は、引き続き、民事裁判の手続の中で、真相解明と医療側の責任追及を図って行く覚悟です。
そして、この民事裁判の中で明らかにされることが、この先に向けて、医療事故を減らすこと、さらにはより良い医療現場の実現につながるはずだという確信もあります。
それゆえ、今後も裁判の進行に合わせ、いろいろとご報告、ご提言をさせていただくつもりですので、医療関係者の方々も含め、広く関心を持って見守っていただければと希望しております。