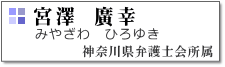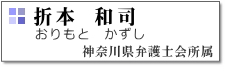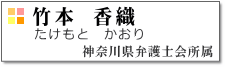PART1で指摘したとおり、本件訴訟では、医療側がもう一つ、明らかに不合理な医学的主張を執拗に展開していました。
それは、局所麻酔薬中毒で心停止になった患者に対し、アドレナリンの点滴投与を行うべきではないという主張でした。
しかし、アドレナリン(エピネフリン)は、冠動脈を拡張し、末梢血管を収縮させるため、血圧を上昇させ、心臓や脳の灌流圧を上げる(血流を増やす)効果があるとされており、また、心筋収縮力増加、心拍数増加、気管支拡張、脱顆粒抑制などの薬理作用によりアナフィラキシーの治療に適しているともされているので、胸骨圧迫(心臓マッサージ、心マ)とあわせて施行すれば脳への血流が増強されることから、二次救命処置として心マ、気管挿管とともに必須の処置であることは医学的に確立された知見ですし、アドレナリンは、その第一選択薬とされています。
この点、被告のクリニックでは、アドレナリンを常置していながら、本件患者の心停止時にアドレナリンを使うことはありませんでしたので、私たちは、その点を踏まえ、適切な救命処置が執られなかったことを医師の注意義務違反として主張したのです。
被告側は、この点に対し、「アドレナリン投与は長期予後を改善せず、投与自体が予後不良因子となるとされ、また生存退院率、中枢神経予後の有意差がないばかりか、悪化したという報告書すらある」などとして、アドレナリン投与を行わなかったこと自体、不適切ではないという主張を展開し始めたのです(ほかにも局所麻酔薬中毒と絡めた主張も行っていますが、それこそ無意味だし、また長くなりますので、ここでは端折ります)。
この被告側の主張を読んで、協力医は唖然としていました。
アドレナリンに上記のような薬理作用があることは明らかで、臨床現場では、心マと並行してアドレナリンを投与すれば、早期の蘇生につながることは臨床現場ではごく常識的なこととされているからです。
現に、本件患者に対しても、救急隊員、そして搬送先の大学病院でもアドレナリンが投与され、自己心拍再開に至っています(すでに重篤な低酸素脳症に陥っており、手遅れではありましたが)。
私たちは、ここでも、医学の常識に反するような被告主張につき、それを論破するためにかなりの時間と労力を割かざるを得なくなりました。
実は調べて行くうちにわかったことですが、被告の「アドレナリンが長期予後を改善しないという報告がある」という主張は議論の前提からして誤りでした。
それは、医療機関外の心停止か医療機関内の心停止かの違いによるものです。
つまり、医療機関内で起きた心停止であれば、通常は心停止後早期に心マやアドレナリン投与が開始されるのに対し、医療機関外で起きた心停止の場合、心マやアドレナリン投与の開始が遅れてしまうことが多いからです。
当然ながら、心停止から救命処置までに時間を要すれば要するほど、脳などの主要臓器がダメージを受けますので、救命の可能性は低下することになります。
結局、長期予後を改善しないという報告は、あくまでも医療機関外での心停止で対応が遅れた場合の比較であり、医療機関内における心停止の場合にはアドレナリン投与の有用性が確認されているのです。
私たちは、そのことを証明するために、海外の文献にまであたり、その翻訳文書までをも証拠として提出するという労を強いられました。
さらに、おまけで触れておきますと、被告側が、「そもそも院外心停止の場合であっても、アドレナリン投与が意味がない」ような主張をしていることについても、多くの協力医の助言も得た上で、それ自体が誤ったものであり、論破すべきと考えました。
なぜならば、医療側の主張が、心停止患者に対し、アドレナリン投与を怠ったことの過ちを認めないための虚構であり、そのようなでたらめな主張が今後の医療過誤訴訟でまかり通るようなことがあってはならないからです。
私たちは、大阪大学において行われたある検証結果の発表を証拠として引用することにしました。
それは、「院外心停止した小児へのアドレナリン投与の有効性を確認した」というものですが、そのポイントは、「蘇生時間バイアス」でした。
蘇生時間バイアスとは、院外心停止で心拍再開が得にくい症例ほど、アドレナリン投与を含む高度の救命処置を受けやすくなるということであり、となると、そのバイアスに修正をかけた検証をしないと、院外心停止におけるアドレナリン投与の有効性が正確に判断できないことになります。
大阪大学では、独自の解析を実施し、バイアスに修正をかけた結果、アドレナリン投与を受けた患者の方が、受けなかった患者より、自己心拍再開は有意に高く、1か月後の生存率、社会復帰率も高い傾向にあることを確認したのです。
以上のとおり、心停止時におけるアドレナリンの有用性は明らかであり、にもかかわらず、医療側が、誤った知見でその有用性を否定し、さらには、一刻を争う場面でアドレナリン投与が躊躇されることなど、万が一にもあってはならないことです。
PART2でも書きましたが、心停止患者に対し、アドレナリンを投与すべきという医学的にはごく当たり前のことが争われ、それを論破するのに膨大な労力を割かなくてはならない今の医療訴訟のあり方には疑問を感じざるを得ません。
PART2で引用した判例の法理を踏まえ、被告側の根拠に乏しい主張を早期に排斥するような裁判所の踏み込んだ姿勢、発想の転換が求められるところです。
私たちは、なんとかたどり着けましたが、アドレナリンの投与がなされないであるとか、遅れてしまったというような症例で、医療側代理人か同種の主張が繰り返されることは今後も危惧されるところです。
医療側代理人は、実質的には保険会社の代理人であり、勝つための戦術を蓄積していると思われるからです。
ここで敢えて丁寧にこのことを取り上げたのは、患者側がそのような戦術に負けないように、あるいは裁判所が「騙されないように」して行く必要があると感じているからです。
ちなみに、被告の医師が、アドレナリンを使用しなかった理由ですが、私たちが訴訟前に話を聞いた時には、医師は「まったく意味ないと思う。むしろ、だって、呼吸が確保できなくて、心臓止まって、点滴入れられないじゃないですか。回ってないんですから、循環が」と答えています。
心臓が止まった状態で脳などの主要臓器への血流を確保するために心マを行うわけですが、この整形外科医は、救急救命措置の意味すら理解していなかったのです。
ペインクリニックの専門医が言われていたことですが、局所麻酔薬を扱う医師は、その危険性や命に関わる事態に陥った時の退所について、あらかじめスタッフの教育も含めた備えをしておかなければならないし、逆にそのような備えができてない医師、医療機関は、局所麻酔薬を扱ってはいけないとまで言っておられました。
医療者の方々は、心して取り組んでいただきたいと強く申し上げておきたいと思います。
神経ブロック、トリガーポイントといった治療は、市中の整形外科医にとっては、日常のルーティーン的な医療行為となっています。
肩こりの治療で命を落とすなんて、やはりどう考えても理不尽なことであり、ここで取り上げることが、事故の回避につながればと願ってやみません。
このお話はもう一回だけ続きます。