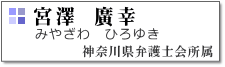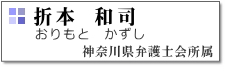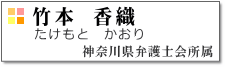遺言が存在する相続案件で出てくる権利が「遺留分」です。
民法1042条以下で定められていますが、2019年7月1日を境に制度改正がなされていてその前後で扱いが異なる点もあるので注意が必要です。
その内容については各所で取り上げますが、実際には遺留分はいろんな局面で登場してきます。
当事務所の弁護士が扱った事件や関連判例などに言及しつつ、幾度かに分けて取り上げてみたいと思います。
まず、遺留分とは何かですが、遺言があっても留保される権利(取得分)ということになります。
大まかにいえば、遺留分は法定相続分の2分の1とされています。
つまり、たとえば、配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1(複数いれば按分されます)となりますが、遺留分はその2分の1となり、配偶者、も子も4分の1となるわけです。
ただ、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
子も親もいない場合、兄弟姉妹にも法定相続分が認められているのですが、被相続人が遺言を遺していれば、兄弟姉妹に遺留分がないので、遺言の内容に異を唱えて権利主張することはできないというわけです。
被相続人の死後に遺言が出てきたときには、遺留分権利者は遺留分を主張することができますが、法律上の用語で、それを遺留分侵害額請求権(旧法では「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました)といいます(現時点では改正前の旧法の適用場面の事件も多いので、以下の記事では時期に応じて使い分けさせていただきます)。
ただ、この遺留分侵害額請求権の行使についても一定のルールがあります。
何より重要なことは権利行使に期間制限があるということです。
法定相続と異なり、被相続人の意思で遺言が作成されている以上、原則的にはそれが尊重されるべきであり、不利な内容の遺言だと知った遺留分権利者がいつまでも権利行使をしない場合にいつまでも権利行使が可能とすることは法的な権利関係を不安定にしてしまうからです。
遺留分侵害額請求権行使の期間は、自身の遺留分を侵害している内容の遺言の存在を知ってから1年以内です。
新法の条文上の表現では「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」となっています(民法1048条。同条文では、もう一つ、相続開始から10年で消滅するという規定も設けられていますが、これは不利な遺言の存在をずっと知らないままであった場合の定めです)。
現実には、遺言は被相続人の自宅内にあるか、相続人の一人、あるいは第三者(弁護士、税理士、銀行など)が保管していることが多く、通常は被相続人の死後にそれが開示されるか、自筆証書遺言の場合だと、家庭裁判所で「検認」という手続が取られなくてはなりませんので、そうしたタイミングで他の法定相続人も遺言の存在を知ることになります。
いずれにしても、遺留分侵害額請求権は自身に不利な遺言の存在を知ったその日から1年以内に行使しなければ以後はまったく主張することができなくなるわけです。
注意すべきは、遺言の効力を争うような場合であっても、遺留分侵害額請求権を期間内に行使することを絶対に怠ってはならないということです。
現実には、必ずしも被相続人の真意とは考えにくいような偏った内容の遺言が死後になって突如として出てきたり、遺言の作成時期がすでに判断能力の衰えつつある段階のものであったり、あるいは被相続人を一部の家族が抱え込んで他の家族を遠ざけてしまっていたりとか、遺言を巡っては様々な事情や経緯があったりします。
それゆえ、中には遺言の効力そのものを争いたくなるような事案も少なからず存在するわけですが、そこで遺言の効力の方にばかりに気を取られていると、遺留分侵害額請求権の行使のことは失念してしまいがちなものです。
しかし、現実には遺言の効力を争うといってもそのハードルはかなり高いので、有効とされた場合に備えて遺留分侵害額請求権の主張を時効期間内に行っておくことは必須となります。
この点、弁護士にとって首筋が寒くなるような判例もあります。
それは、遺言無効の訴えの事件を受任した弁護士が、遺留分侵害額請求権の行使につき助言を怠ったため、それが弁護士の善管注意義務違反にあたるとして依頼者からの損害賠償請求が認められたというものです。
ともあれ、遺留分侵害額請求権は時効期間経過前に行使さえしておけば、そこからは腰を据えて検討することができますので、内容証明郵便という証拠の残る形で意思表示を行っておくことが肝要です。
次回は、遺留分放棄の許可について取り上げます。