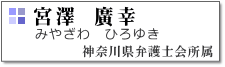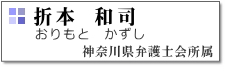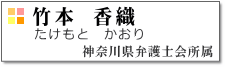医療事件で、多くの弁護士が最も苦労し、負担となるのが鑑定意見書の問題です。
もちろん、鑑定意見書といっても、患者側、医療側がそれぞれ自ら依頼して作成してもらう私的鑑定意見書と、裁判所の手続として行われる公的鑑定意見書では準備の手順も異なるのですが、いずれも我々にとっては非常な負担となることに変わりはありません。
いろいろな苦労がありますが、本日は鑑定事項の設問の表現ということに焦点を当てて取り上げてみます。
私的鑑定意見書の何が大変かというと、医療事故の争点に合致する協力医を見つけて、鑑定意見書の作成に協力してもらうところまでたどり着くこと自体が、決して容易ではないということです。
もちろん、争点を理解してもらうための面談や資料の提示、説明に労を要しますし、裁判の展開の中で、私的鑑定意見書の作成をお願いしなければならなくなったときは、いきなり目の前に3000メートル級の山が聳え立ったという感じで暗澹たる気分になることも少なくありません。
これに対し、公的鑑定意見書では、鑑定医のリストは裁判所が用意してくれるので、その点ではまったくゼロから探すのとは違いますが、実際にはそこから適切な鑑定医の選任に至るまでで医療側や裁判所との協議を経る必要があり、相当な苦労があります。
もっとも、鑑定医の選任に関する協議と並行して、鑑定事項を詰めていく作業があり、こちらもかなり大変となることが少なくありません。
最近では、訴訟手続きの中で争点整理を早い段階で行うことが増えているので、大体の争点は共有できているのですが、鑑定事項の中にどこまでそれを反映させるかについては議論になってしまうこともあります。
最近も経験したことなのですが、鑑定事項の設問の表現を巡って議論となり、明らかにおかしいと思うことがありました。
それは何かというと、過失に関する鑑定事項の末尾の表現について、医療者の個々の診療行為が過失にあたるか否かを尋ねるにあたって、「不適切でしょうか」と問うか、「適切ではないでしょうか」と問うかということに関する議論です。
この点、裁判所の傾向としては、「不適切でしょうか」と問うように求めてくることが多くなっているようです。
この違いがどのくらい重要な意味を持つか、ピンとこない方が多いと思いますが、実際に医療訴訟に関わっている立場からすると、結構重大な分岐点になることも少なくありません。
まず、そもそも、裁判所は、なぜ「不適切でしょうか」と問うように求めてくるのでしょうか。
裁判官と話していたら、「適切ではないという答えは、イコール過失を意味しないからだ」との返答がありました。
現に裁判官がそのような見解を滔々と述べている文章もあります。
しかし、適切でないと第三者の医師が指摘するような医療行為が過失にあたらないなんてことがあり得るでしょうか。
実際にいろいろな医師の方にお会いしていて感じるのは、現実にその医療行為に携わっておらず、患者も診ていない第三者の医師としては、軽々にミスを指摘できないというのが医師の心情としては率直なところだということです。
そのような前提からすれば、鑑定医が当該医療行為について「適切ではない」という意見を述べるということ自体、相当踏み込んだ表現であり、それは医療ミスを明確に指摘したものとできると思います。
裁判所の一部にある「適切ではないという答えがイコール過失を意味しない」という発想は、言葉遊びに等しく、まさに机上の空論だと感じざるを得ません。
もう1つ、実務的にはこの点がとても重要なのですが、「不適切でしょうか」と問いだと、「不適切とまではいえません」という意見が引き出されてしまうことがあるという問題があります。
これは答える側の人間の心理の問題でもありますが、鑑定医が当該医療行為は間違っていると感じている場合、「適切でしょうか」との問いに対しては、さすがに「適切です」とは答えにくいのに対し、「不適切でしょうか」との問いに対しては、「不適切とまではいえません」という曖昧な答えが出てくる可能性が少なからずあります。
特に鑑定医としては、当該医療事故に直接関わっていない以上、断言しづらいという心理が働くこともありますし、同業者のミスを積極的に指摘しづらいという心理が働くことも否定できません。
鑑定事項の表現については、このような鑑定医の心理への影響も踏まえて検討されるべきだと思います。
裁判所があくまで「不適切でしょうか」と問いに固執するのであれば、それこそ「不適切にもほどがある」のではないでしょうか。
医療裁判の領域は、まだまだ発展途上であり、これからも試行錯誤は続くと思いますが、鑑定に関する裁判所の運用のあり方についても、どのようなやり方が真相解明に資するかという視点を忘れずに取り組んで行ってもらいたいし、患者側代理人としてもきちんと訴えて変えて行かなくてはならないと思います。