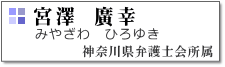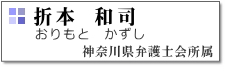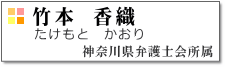先週、横浜地方裁判所において、肝生検後の大量出血による乳児の死亡事故について提訴しましたので、ご報告いたします。
長くなりますが、興味があればお読みください。
本件医療事故の概要
本件医療事故は、平成22年9月1日に神奈川県内で小児の肝生検を多く扱っているとされている総合病院において起こりました。
被害者となった患者は、生後11か月の乳児で女児です。
患者は、ビリルビンの値が高く、精査のため、当該病院に転院となり、経皮的針肝生検を受けることになります。
経皮的針肝生検とは、皮膚の表面から針を刺して、肝臓の組織を採取するというものです。
肝生検実施の前に、両親が「まだ赤ん坊なんですが、大丈夫なんでしょうか?」と質問をしたところ、医師からは、「うちの病院は、小児の肝臓では日本一ですし、検査はベテランの医師がやるから大丈夫です」という説明があったそうです。
しかし、実際に行われた肝生検では、最初、穿刺を担当したのは、まだ若く経験の浅い医師でした。
その若い医師が手技を行っている間に患者の体動が激しくなり、いわゆるブリッジで反り返るようなこともあったため、再度麻酔薬を投与し、その後もこの医師が肝生検を実施し続け、計3回の穿刺が実施されます。
しかし、結局、組織の採取は不成功に終わり、上司にあたる別の男性医師に交代します。
別の医師に交代してからも、患者の体動が激しいため、再び麻酔薬が投与され、この医師により計3回の穿刺が実施され、肝生検は終了します。
計3回の麻酔と、通算で計6回の穿刺が実施されたことになりますが、両親は無事終了したとしか聞かされていません。
検査が終わって、1時間半が経過したころに、付き添っていた親御さんが子どもの呼吸が激しくなっていることに気づき、看護師を呼びます。
その時は知らされていませんが、脈拍数210、呼吸数52回と、明らかな頻脈、頻呼吸に陥っていました。
しかし、医師が訪室することはなく、そのままの状況が続きます。
カルテによりますと、それから30分後、つまり肝生検終了からちょうど2時間後ですが、その時点で、脈拍数230、呼吸数64回に達し、さらに手足は冷たくなり、顔色も悪くなります。
看護記録にも、四肢冷感、口唇チアノーゼと記載されています。
しかし、この時点でも、何の検査も実施されません。
この後に病室に訪れた、検査を行った医師とは別の若い医師は、「まだ大丈夫です」と言って、検査の指示もせず、病室を去ります。
以後もずっと同様の症状が続き、最初の頻脈、頻呼吸初見から2時間半もの間、検査も治療も行われることはありませんでした。
そして、検査終了から4時間後、最初の頻脈、頻呼吸初見から2時間半以上が経過した時点で、やっと医師が訪室したものの、それ以前はずっと保たれていた血圧はすでに測定不能となっています。
以後、強心剤の投与などの処置はなされていますが、すでに非代償性ショックの状態となっており、結局、肝生検が終了してから約13時間後、患者は、生後わずか11か月で死亡したのです。
死後行われた司法解剖により、「肝生検に起因する出血死」であることが死体検案書にも明記されています。
腹腔内には360mlの出血があったことが確認されていますが、通常、体重の8%(子供の場合はもう少し低いとされています)が体内の総血液量とされていますので、女児の体重が約8㎏であることからすると、体内の循環血液量の半分を優に超える致死的出血があったことになります。
また、肝臓には6か所の穿刺痕があることが確認されています。
死に至る医学的機序と医療側の責任
本件の幼い患者が死亡に至った機序ですが、肝生検の際の生検針の穿刺の際にそのルート上にある主要血管が損傷されてその損傷部位から血液が腹腔内に漏出し、それが遷延化したことによる出血死であることに疑う余地はありませんでした。
血液が血管から大量に漏出してしまえば、体内の循環血液量が減少して、主要臓器に血液が十分に回らなくなれば、循環血液量減少性ショックとなることは常識的な医学的知見なのです。
実際に、肝生検終了後1時間半後に患者に現れた異常所見は、200/分を優に超える頻脈や50/分を優に超える頻呼吸であり、その後30分後には、頻脈、頻呼吸はさらに増悪し、四肢冷感、口唇チアノーゼ等も看護記録に明記されていますが、これらの異常所見は、体内の循環血液量が減少したことによる代償作用として現れる典型的な所見です。
もちろん、本件では、本来、安静の指示に従えない患者に行うについては非常にリスクの高い経皮的針肝生検を実施し(訴状ではこの点も過失として主張しています)、計6回の穿刺に及んでいる上、カルテには「体動が激しい中、穿刺が行われた」との記述もありますし、肝生検の手技の間に3回も麻酔薬を投与しているのですから、血管損傷等の合併症が生じていた可能性もより強く念頭に置くべきといえます。
しかも、患者は乳児ですから、自身の症状、苦痛を言葉で訴えることすらできません。
にもかかわらず、当該病院の医師、看護師は、明らかな容態変化があり、それがずっと継続していたにもかかわらず、一度も出血を疑って精査を行うということすらしなかったのです。
本件においては、病院の医師、看護師らに診療行為上の過失が存することは明白といわざるを得ません。
ところで、前述のとおり、本来、人間の体には、代償機能というものが備わっています。
本件のように体内を循環する血液量が減少したような場合においても、心拍数や呼吸数でカバーしようとします。
本件の患者に起きた、頻脈、頻呼吸は、まさに人間の体に備わっている代償機能が働いている状況で、循環動態が破綻する直前まで血圧は正常を保っており、医学的には代償性ショックといわれる状態なのです。
この、代償機能が作用し、血圧が何とか維持されている代償性ショックの間に、止血処置を行い、輸血、輸液などを実施してあげれば、患者の救命は十分に可能なのです。
医療側には、代償性ショックを疑うべき指標が現れて以降、2時間半もの時間の余裕がありましたので、その間に止血処置を行い、輸血、輸液などを実施してさえいれば、幼い患者の命を救うことができたはずなのです。
本件については、医療側が法的責任を負うことは極めて明白な事件であり、私たちが相談した複数の専門医からも、同趣旨の見解を得ています。
事故後の病院側の対応についても、本件では、憤りを感じざるを得ない点が多々ありますが、ここでは触れません。
今後、病院側が訴訟においてどのような対応をして来るのかは現時点ではわかりませんが、不毛な争い方はやめ、真摯な対応をしていただきたいと心から願っております。
原告ら遺族は、一刻も早い真相究明と病院側の心からの謝罪を望んでいます。
そして、それを死亡した子供の墓前に報告したいと希望しています。
それと、もう一つ、原告ら、そして私たち代理人の願いは、医療側が本件事故を反省し、事故に対し真摯に向き合うことによって、同じような物言えぬ幼い子供に対する悲惨な医療事故が二度と起きないようにしてもらいたいということです。
もし、相手方病院が、小児の肝臓について日本一の病院でありたいと思うのであれば、何よりも、事故によって幼い患者が命を落とすことのないよう、誠実に本件事故に向き合い、事故を教訓にする謙虚な姿勢こそが必要だと思うのです。
そうやって、医療の質を高め、患者本位の医療を実現するという姿勢が、本件のような医療事故をなくすことにもつながると思うのです。
原告らご遺族と私たち代理人弁護士はそうしたことを願って、本件提訴に踏み切りましたので、その旨ご報告申し上げます。
本件訴訟の経過については、今後、可能な限りホームページにおいてご報告してまいりたいと考えています。