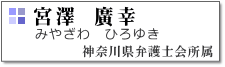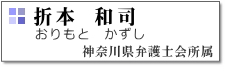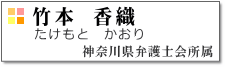本年6月25日付で、横浜の検察審査会において、私たちが担当している肝生検による乳児の死亡に関する医療事故について、不起訴不当の議決が出ましたので、ちょっと長くなりますが、経緯についてご報告するとともに、私たち代理人弁護士が感じている様々な想いを述べてみたいと思います。
まず、本件事故の経緯ですが、このホームページで何度も取り上げているとおり、平成22年9月1日に横浜市内のある総合病院の医師らが、生後11か月の女児に対して肝生検を実施したところ、術後1時間半くらいが経過したあたりから脈拍数が分あたり200回を超え、呼吸数も分あたり50回から60回を超え、そこから約3時間後に容態が急変して死亡したというものです。
ところが、死亡直後の9月2日未明の時点で、病院側は、両親に対して、「死因は不明だが、病院に責任はない」「真相を知りたければその調査のために数百万円はかかる」などと言い放ち、そのあまりに無責任な発言にショックを受けた両親が警察への通報を求め、警察介入となります。
司法解剖の結果、女児の肝臓には6個もの穿刺痕があったことが確認され、腹腔内に貯留した出血量は体内の総血液量の2分の1を優に超える360mlに達していたことが判明し、解剖医は、肝生検後の出血性ショックによる死亡と判断します。
ところが、病院側は、女児に何らかの代謝異常が起きたのだとして、出血性ショックによって説明のつく事象を、別の病気にこじつけるような主張を行うようになり、悲しみに暮れる遺族にもいきなりそのような趣旨の手紙を送りつけます。
警察は慎重に捜査を進め、長く時間はかかりましたが、事件は昨年11月に検察庁に送致されます。
その後、被疑者の内、当時研修医だった方の医師が、自身の弁護士を通じて、私たちに連絡をして来て、事故から9年以上の月日が流れてはいましたが、昨年12月に両親との直接の面会が実現しました。
研修医だった医師は、当時、患者の容態にずっと疑問や不安を感じながらも、経験が足りなかったことに加え、彼が所属していたチームにおいては、上級医の意向と異なるような医療行為ができない関係性があったため、上級医に何度も患者の異常を伝えてはいたものの、致死的な急変に至るまで何もしてあげられなかったことをその後ずっと悔やんでいたそうです。
また、この病院では、以前にも同種の事故が起きていたという情報もあったのですが、この研修医は、その当時はこの病院におらず、以前の事故のことは全く知らなかったそうです。
謝罪に来た医師は、その後経験を積んでおり、あらためて振り返れば、この事故が肝生検後の出血によるものであること、代償性ショックの段階なので、その時点で適切に対処していれば救命できたはずの事故であったとその場で明言していました。
私たちは、この研修医の謝罪を受けて、検察官に申し入れをしようと思っていたのですが、この面談の日からわずか半月後、送検からわずか40日しか経っていない昨年末の時点で、突然、検事から嫌疑不十分で不起訴にするとの連絡が入ったのです。
いうまでもないことですが、医療過誤は、経験を積んだ弁護士にとっても、症例ごとに幅広く医学的な検討をしなくてはならない事件領域であり、特に医療側が医学的に特異な主張を行っている場合には、その主張に矛盾点や不合理な点があるか否かを見極めるためには相当な時間と労力、さらには医師の協力などを要します。
たとえば、医療側は、裁判でも、急変時のヘモグロビン値の低下は出血では説明がつかないと主張していますが、本件では輸液が行われていたことに加え、大量出血が起きると、血管外から血管内に水分が戻って来るという機序もあり、ヘモグロビン値の低下は出血によるものと見るのが医学的には合理的なのであって医療側の説明には明らかに誤りが含まれているのですが、民事、刑事を問わず、医療事件においては、このような医学的なメカニズムの検証を一つ一つの事象について行わなければならないのです。
しかし、担当した検察官は、送致からわずか1ヶ月余りで、しかも、医師の内の一人がミスを認め、救命できたはずだとの認識を遺族に示し、謝罪の手紙まで渡している中で、嫌疑不十分不起訴という結論を出したわけですから、およそ上記のような検証がなされたとは考えられませんし、結論先にありきで役割を放棄したようにしか見えず、遺族が納得できないのも当然のことでした。
また、担当検察官は、遺族に対する説明の中で、公訴時効が迫っており、検察審査会の手続に入るためにも早めに結論を出してあげた方がいいと考えたと言っており、本末転倒で何をかいわんやというほかなく、私たちがその話を聞いた時には思わず絶句してしまいました。
不起訴処分が出た直後は民事裁判の方の次回期日の準備が佳境に差し掛かっていたこともあり、少し準備には手間取りましたが、私たちは、内部告発をしてくれた医師や、謝罪の意思を示してくれた(不起訴処分を受けた当事者でもある)研修医の方の陳述書を付して、検察審査会に審査の申立をしました。
その後、コロナウイルス感染の広がりで、手続が遅れているのではないかという心配もあったので、上申書を提出するなどして、結論が出るのを待っていたところ、6月25日付で検察審査会から、上級医に対する不起訴処分は不当であるとの議決が出たのです。
研修医の方については、理由は特に書いてありませんでしたが、不起訴処分が維持されています。
不起訴不当の議決の判断の理由の中では、肝生検の際の6回に及ぶ穿刺により、出血が続いており、脈拍数や呼吸数の異常があったにもかかわらず、出血兆候を見逃がし、救命処置を取らなかった過失が明確に指摘されており、また、その時点で適切に輸血、輸液、止血処置などが取られていれば救命できたはずとして死亡との因果関係についても明示されており、当たり前の結論ではあるのですが、まだ途中経過ではありますが、努力が報われてよかったという気持ちになりました(もちろん、勇気を振り絞って内部告発をしてくれた医師や、葛藤を乗り越え、謝罪に赴いてくれた研修医の方の協力があればこそですが)。
患者側の代理人として、様々な事件を扱ってまいりましたが、本件事故は、単なるヒューマンエラーと捉えるべきでない、今の医療現場が抱える様々な問題を含んでいるように思います。
前にも取り上げたことですが、本件では警察が介入した9月2日の未明には、巧妙な電子カルテの改ざんが行われています(今年放映された現代版「白い巨塔」におけるカルテの改ざんと同じ手口です)。
研修医の方から伺ったところでは、事故後、上級医から口裏合わせ的な指示もなされていたそうです。
前述したとおり、出血によって起きたものと説明のつく事象を、およそあり得ないような別の病気によるものとこじつけるような主張も繰り返されています。
しかし、本件事故くらい、シンプルな出血死の事故はありません。
意見書を書いてくださった協力医の方もおっしゃっているのですが、こんな明白な医療ミスの事故において、なぜ不毛な争いを行うのか、信じられない気持ちになります。
医療過誤を扱っていると、医療者に対する感謝の気持ちはむしろ強くなります。
ミスを犯した医師に対しても、それを責めるというよりも、臨床現場でリスクと向き合っておられることに対しては敬意を表したいと思うことも少なくありません(ですので、医療事故を起こした医師について、原則的には刑事処分を求めるという対応をしてはいません)。
ですが、本件事故におけるように、あまりに不毛で見苦しい争い方をする医療者や医療機関が存在することについては、そうした対応が、さらなる医療不信を招くことになるし、臨床現場もかえっておかしくなってしまうのではないかという危惧を感じたりもします。
今の率直な気持ちとして申し上げれば、本件事故については、体重わずか8キログラムの乳児の小さな肝臓に太い生検針を6回も刺し、出血死に追いやり、反省も謝罪もなく、医療側がカルテの改ざんを行い、裁判においても、明らかに出血死によるものと評価できるはずの事象を別の病気にこじつけるような主張を重ねている経緯に照らしても、この上級医に対しては、起訴して裁判による裁きを受けてもらいたいし、公開の法廷で事実が明らかとされることで、このような痛ましい、あってはならない事故が繰り返されず、また医療現場で働く医療者がきちんと医療に向き合えるようにするための教訓にしてもらいたいと心から強く願っております。