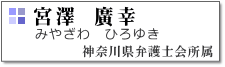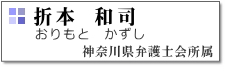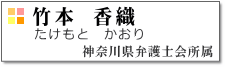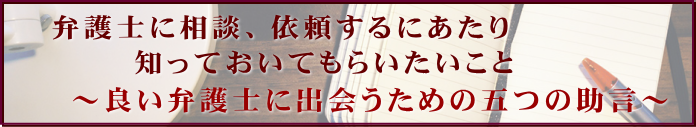
гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒӘгҒ„гҒ—дҫқй јгӮ’гҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®зөҢйЁ“гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢеҠ©иЁҖгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«жұӮгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢдҪ•гҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒдҫқй јгҒ—гҒҹгҒ„ејҒиӯ·еЈ«гӮӮз•°гҒӘгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖгҒӨгҒ®еҠ©иЁҖгҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ®зҠ¶жіҒгӮ„гҒҠжӮ©гҒҝгҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰгҖҒгҒ”еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒеҲқгӮҒгҒ«з”ігҒ—гҒӮгҒ’гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒёгҒ®зӣёи«Үпјқдҫқй јгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖе®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢеҸ—гҒ‘гӮӢзӣёи«ҮгҒ®еҶ…гҒ®еҚҠеҲҶд»ҘдёҠгҒҜзӣёи«ҮгҒ гҒ‘гҒ§зөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжі•зҡ„гҒ«гҒҜдҪ•гӮӮгҒ—гҒҰе·®гҒ—гҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҠж–ӯгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒҢдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҠ©иЁҖгӮ’гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§и§ЈжұәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйӣўе©ҡгҒ®и©ұгҒ—еҗҲгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ”еӨ«е©ҰгҒ®дёҖж–№гҒҢзӣёи«ҮгҒ«жқҘгӮүгӮҢгҒҰгҖҒйӣўе©ҡгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒ®жқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰжҸҗзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гҒҢеҰҘеҪ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢеҗҰгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжқЎд»¶гӮ’зӣёжүӢж–№гҒ«жҸҗзӨәгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘзӣёи«ҮгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҰӘжЁ©гҖҒйӨҠиӮІиІ»гҖҒиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҖҒж…°и¬қж–ҷгҖҒйқўдјҡдәӨжөҒгҖҒе№ҙйҮ‘еҲҶеүІгҒӘгҒ©гҒ®и«ёжқЎд»¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒӢгӮүеҠ©иЁҖгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮҢгҒ°гҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ§гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«и§ЈжұәгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒқгҒҶгҒ—гҒҹж„Ҹе‘ігҒ§гӮӮгҖҒиәҠиәҮгҒӣгҒҡгҒ«гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨгҒҜиЁјжӢ иЈҒеҲӨдё»зҫ©гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдё»ејөгӮ’иЈҸд»ҳгҒ‘гӮӢиЁјжӢ гҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еӢқгҒҰгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰжңүеҲ©гҒӘиЁјжӢ гӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгҒӢгҒҢиЈҒеҲӨгҒ®её°и¶ЁгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҠҪиұЎзҡ„гҒ«иЁјжӢ гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘиЁјжӢ гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰйӣҶгӮҒгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢж„ҸеӨ–гҒ«йӣЈгҒ—гҒ„е•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒдёҚеҲ©гҒӘиЁјжӢ гҒҜгҖҒйҡ гҒәгҒ„гҒ•гӮҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжңүеҲ©гҒЁгҒӘгӮӢдәӢе®ҹгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гҒҢгҖҒзҙӣдәүгҒ«е·»гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒқгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйҖ”з«ҜгҒ«еҸЈгӮ’гҒӨгҒҗгӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰзҸҚгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒҢдҪ•гӮүгҒӢгҒ®зҙӣдәүгҒ«е·»гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®иў«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹжҷӮгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҖҒзҙӣдәүи§ЈжұәгҒ®гғ—гғӯгҒ§гҒӮгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҖҒгҖҢгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁјжӢ гӮ’йӣҶгӮҒгҒҹгӮүгӮҲгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеҠ©иЁҖгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдёӢжә–еӮҷгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгӮ„еҠҙзҒҪгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮӮи§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢзҙӣдәүгҒ«гҒӮгҒҰгҒҜгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖе®ҹйҡӣгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨдәӢ件гҒ§гӮӮгҖҒдәӢж•…еҫҢгҒ«еҪ“дәӢиҖ…гҒ®ж–№гҒҢеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«иЁәзҷӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢе®ҹзөҢйҒҺгӮ’е°ӢгҒӯгҖҒз–‘е•ҸзӮ№гӮ’гҒ¶гҒӨгҒ‘гҒҰеӣһзӯ”гӮ’еҫ—гҒҰгҒҠгҒӢгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰжұәе®ҡзҡ„гҒӘиЁјжӢ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдәӢдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®гғҡгғјгӮёгҒ§и§ҰгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҖҖгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒиҝӮй—ҠгҒ«еӢ•гҒҸгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒгҒҫгҒҡејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҒ”жӨңиЁҺгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҖиЈҒеҲӨгҒҜжүӢз¶ҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰжүӢз¶ҡгҒ«гҒҜжөҒгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжі•зҡ„гҒӘгғҲгғ©гғ–гғ«гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠиЈҒеҲӨжІҷжұ°гҒ«гҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ®гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзҙӣдәүгҒ«зҷәеұ•гҒ—гҖҒзҙӣдәүгҒҢйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гҒҰгҖҒдәӨжёүгҖҒиЈҒеҲӨгҒёгҒЁз§»иЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹж„Ҹе‘ігҒ§гӮӮжөҒгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒҢд»ҠгҖҒгҒқгҒ®жөҒгӮҢгҒ®дёӯгҒ®гҒ©гҒ“гҒ«гҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁиҰӢжҘөгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ”иҮӘиә«гҒ®зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹзҠ¶жіҒгҒҢгҖҒдәӢ件гҒ®жөҒгӮҢгҒ®дёӯгҒ®дҪ•еҮҰгҒ«гҒ„гӮӢгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒӘгҒҷгҒ№гҒҚеҜҫеҮҰгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖе®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®еӨ§еҲҮгҒӘеҪ№еүІгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒзҙӣдәүгҒ®дәҲйҳІгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйҒәиЁҖгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒиүҜгҒ„дҫӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжҖқгҒ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҸйҒәиЁҖгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжӯ»еҫҢгҒ®зӣёз¶ҡдәәй–“гҒ®зҙӣдәүгӮ’йҳІжӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҚҒеҲҶгҒ«жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖжөҒгӮҢгҒ«иә«гӮ’д»»гҒӣгҒҰгҖҒдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§жҷӮгҒҢйҒҺгҒҺгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒйҳІгҒ’гҒҹгҒҜгҒҡгҒ®зҙӣдәүгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҹгҒ гҖҒйҖҶгҒ«гҖҒзҙӣдәүгҒҢйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гҒҰгҖҒеҫҢжҲ»гӮҠгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒӘгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜеёёгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖд»ҠгҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹзҠ¶жіҒгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’иҰӢжҘөгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒ°гҖҒиҮӘгҒҡгҒЁгҖҒдҪ•гӮ’гҒӘгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰгҖҒеҜҫеҮҰгҒ®еҝ…иҰҒгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгӮүгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҖҖејҒиӯ·еЈ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӣёи«ҮиҖ…гҖҒдҫқй јиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгӮҲгӮҠжңүеҠ№гҒӘеҠ©иЁҖгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒңгҒІгҖҒеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҖеҢ»зҷӮгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒҜгҖҒд»ҠгӮ„еёёиӯҳгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®дё–з•ҢгҒ§гӮӮгҖҒгӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігҒҜйқһеёёгҒ«жңүз”ЁгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖе®ҹйҡӣгҖҒеҢ»зҷӮгҒЁејҒиӯ·еЈ«гҒ®д»•дәӢгҒҜгҖҒдјјгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖеҢ»зҷӮгҒ«гҒӣгӮҲгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®д»•дәӢгҒ«гҒӣгӮҲгҖҒе°Ӯй–ҖжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиЈҸгӮ’иҝ”гҒӣгҒ°гҖҒе°Ӯй–Җ家гҒ®дёҖе®ҡгҒ®иЈҒйҮҸгҒ«е§”гҒӯгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„е ҙйқўгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»–ж–№гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгҒ”иҮӘиә«гҒҢжұәгӮҒгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢиҮӘе·ұжұәе®ҡгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖеҢ»зҷӮгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢжӮЈиҖ…гҒ®иҮӘе·ұжұәе®ҡжЁ©гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢгӮӨгғігғ•гӮ©гғјгғ гғүгӮігғігӮ»гғігғҲгҖҚпјқгҖҢеҚҒеҲҶгҒӘжғ…е ұгӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҒ®еҗҢж„ҸгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®еҒҙгҒ«гҖҢиӘ¬жҳҺзҫ©еӢҷгҖҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒЁдҫқй јиҖ…гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒҢгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖжі•зҡ„гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№йҮқгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰиЎҢгҒҸгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ®гҒҜдҫқй јиҖ…иҮӘиә«гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж–№йҮқгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘжғ…е ұгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«гҒҜиӘ¬жҳҺзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӮгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒҢз«ӢгҒҰгҒҹж–№йҮқгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒӢгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘжғ…е ұгҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ®гҒҝгҒ§еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒӮгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒӢгӮүгҖҒиЈҒеҲӨгӮ’гӮ„гӮҠгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮгҖҒи»ҪгҖ…гҒ«гҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«еҫ“гҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҲҘгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҷӮгҒ«йқһеёёгҒ«жңүз”ЁгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеҢ»зҷӮгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮӮеҫ—жүӢдёҚеҫ—жүӢгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒзӣёи«ҮгҒ•гӮҢгҒҹй ҳеҹҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮзҡ„зўәгҒӘеҠ©иЁҖгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒи‘—дҪңжЁ©е•ҸйЎҢгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ®дәәжЁ©гҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨзӯүгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠзү№ж®ҠгҒӘйғЁйЎһгҒ«е…ҘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеӨ§йғЁеҲҶгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒҢжүұгҒЈгҒҹзөҢйЁ“гҒ®гҒӮгӮӢйӣўе©ҡдәӢ件гӮ„еӮөеӢҷж•ҙзҗҶзі»гҒ®дәӢ件гҒ§гӮӮгҖҒеұҖйқўгӮ„дәӢжЎҲгҒ®еҶ…е®№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒиӘ°гӮӮгҒҢеҗҢж§ҳгҒ«жүұгҒҲгӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігҒҜеӨ§еҲҮгҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖж°‘дәӢгҖҒ家дәӢгҒӘгҒ©иӘ°гҒ«гҒ§гӮӮиө·гҒҚеҫ—гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдәӢ件гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз«Ӣе ҙгҒӢгӮүз”ігҒ—дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ®гҖҒгҖҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘еҢ»гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮж°—и»ҪгҒ«зӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒҢиә«иҝ‘гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеҝғдёҲеӨ«гҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢдјҒжҘӯгҒ®йЎ§е•ҸејҒиӯ·еЈ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҜҺжңҲйЎ§е•Ҹж–ҷгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖдҪ•гҒӢгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гҒ”зёҒгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ®й–“гҒ§з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘдҝЎй јй–ўдҝӮгӮ’зҜүгҒ„гҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°гҖҒгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶжҷӮгҒ«гҖҒжҗәеёҜйӣ»и©ұгҖҒгғЎгғјгғ«гҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҒҗгҒ«йҖЈзөЎгҒҢеҸ–гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгҒ—гҖҒдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒЁе·ЎгӮҠеҗҲгҒҲгҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ