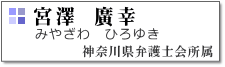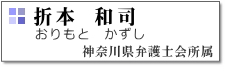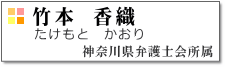еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұпҪһеҢ»зҷӮзі»гҒ®дәӢ件гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігҒ®еӢ§гӮҒ
еүҚгҒ«гӮӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁжӣёгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮзі»гҒ®дәӢ件гӮ’ж•°еӨҡгҒҸжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒ»гҒӢгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒ•гӮ“гҒӢгӮүгҒ®зӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎиҮӘиә«гӮӮзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮзі»гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮж©ҹеәҸгӮ„йҒҺеӨұгҒ®и©•дҫЎгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢе ҙйқўгҒ§еҢ»еӯҰзҡ„гҒӘйӣЈе•ҸгҒ«гҒ¶гҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒе•ҸйЎҢзӮ№гҒҜгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҒқгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’гӮӮгӮүгҒҲгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҖҒйӣЈгҒ—гҒ„зҠ¶жіҒгҒ«йҷҘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒдәӨйҖҡдәӢж•…гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҡңе®ігҒ®и©•дҫЎгӮ„еӣ жһңй–ўдҝӮгҒ®е•ҸйЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе ҙйқўгҒ§гӮӮеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘжӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮгҒҢй–ўгӮҸгӮӢдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮзі»гҒ®дәӢ件гҒ®еӨ§еӨүгҒ•гҒ®дёҖгҒӨгҒҜгҖҒеҢ»еӯҰгҒ®жЈ®гҒ®еҘҘж·ұгҒ•гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒзңҹзӣёгҒ«иҫҝгӮҠгҒӨгҒҚгҖҒи§ЈжұәгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®йҒ“гҒ®гӮҠгҒ§гҖҒе№ҫеәҰгӮӮе№ҫеәҰгӮӮгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘйӣЈе•ҸгҒ«гҒ¶гҒЎеҪ“гҒҹгӮҠгҖҒиЎҢгҒҚи©°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶеұҖйқўгҒ«еҮәгҒҸгӮҸгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’иӨҮж•°еҸ—д»»гҒЁгҒҷгӮӢдё»гҒҹгӮӢзҗҶз”ұгҒҜгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еұҖйқўжү“й–ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиӯ°и«–гҒ—гҒҰзҹҘжҒөгӮ’еҮәгҒ—еҗҲгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҖҡеёёдәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒз”ҹгҒ®дәӢе®ҹгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжі•зҡ„и©•дҫЎгӮ’еҠ гҒҲгҒҰиЎҢгҒ‘гҒ°гҒ„гҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјҲгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҲӨдҫӢгӮ„жі•и§ЈйҮҲгҒ®жӨңиЁјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз°ЎеҚҳгҒӘдәӢжЎҲгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢпјүгҖҒзү№гҒ«еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒз”ҹгҒ®дәӢе®ҹгҒӢгӮүеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘдәӢе®ҹпјҲж©ҹеәҸпјүгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгғҹгӮ№гҒ®жңүз„ЎгӮҲгӮҠеүҚгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®еҢ»еӯҰзҡ„дәӢе®ҹгӮ’и§ЈжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸе ҙйқўгҒ§гҒ®еҢ»еӯҰзҡ„гҒӘжӨңиЁҺгҒҢжңҖгӮӮеӨ§еӨүгҒӘдҪңжҘӯгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒҠи…№гҒҢз—ӣгҒ„гҒЁгҒӢзҷәзҶұгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҹгҒ®з—ҮзҠ¶гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҖҒдҪ•гҒ«иө·еӣ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҜзӣҙгҒЎгҒ«еҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
Xз·ҡгӮ„CTгҒӘгҒ©гҒ®з”»еғҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒзҷҪиЎҖзҗғгҒӘгҒ©гҒ®жӨңжҹ»жүҖиҰӢгӮӮеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҺҹеӣ з–ҫжӮЈгҒҢгҒӮгӮӢзЁӢеәҰзү№е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘз—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹе…ёеһӢзҡ„гҒӘгӮұгғјгӮ№гҒЁгҒ®гҖҢгҒҡгӮҢгҖҚгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒзҹӣзӣҫгҒӘгҒҸиӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮжӨңиЁјгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲе®ҹйҡӣгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҖҢгҒҡгӮҢгҖҚгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҖҒеҢ»еӯҰи«–дәүгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®з—ҮдҫӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒзөҗжһңгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еӨүгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒйҒҺеӨұгӮ„еӣ жһңй–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҗҢж§ҳгҒ«еҢ»еӯҰзҡ„гҒӘзҹҘиҰӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸжӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдёҖеұұи¶…гҒҲгҒҰгӮӮгҒқгҒ®е…ҲгҒ«гҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгҒ®еұұгҒҢз«ӢгҒЎгҒҜгҒ гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж°—еҲҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮзі»гҒ®дәӢ件гҒҜеҘҘж·ұгҒҸгҖҒжң¬еҪ“гҒ«йӣЈгҒ—гҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒжүӢз¶ҡзҡ„гҒӘеұҖйқўеұҖйқўгҒ§гҒ®еҜҫеҝңгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гӮӮгҖҒйҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢдәӢ件гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒ®жүӢй ҶгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ«зўәиӘҚгҒҷгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгҒ®гҒҫгҒЁгӮҒж–№гҖҒжҸҗиЁҙеҫҢгӮӮгҖҒиЁәзҷӮзөҢйҒҺдёҖиҰ§иЎЁгҒ®дҪңжҲҗж–№жі•гҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®дәүгҒ„ж–№гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҜҫеіҷж–№жі•гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®иЁҙиЁҹжҢҮжҸ®гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„ж–№зӯүгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨұзӨјгҒӘиЁҖгҒ„ж–№гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®жүұгҒ„ж–№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒжүӢз¶ҡгҒ®йҖІгӮҒж–№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйҖҡеёёдәӢ件д»ҘдёҠгҒ«з·Ҡејөж„ҹгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰиҮЁгҒҫгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„е ҙйқўгҒ«е№ҫеәҰгӮӮеҮәгҒҸгӮҸгҒҷгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§иЈҒеҲӨе®ҳгҒЁгғҗгғҲгғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гӮҮгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжңҖиҝ‘гҒ§гӮӮгҖҒгҒӮгӮӢиЈҒеҲӨгҒ§еҢ»зҷӮеҒҙгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҠгҒӢгҒ—гҒӘиЁәзҷӮзөҢйҒҺдёҖиҰ§иЎЁгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҖҢгӮ„гӮҠж–№гҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜиЁәзҷӮзөҢйҒҺдёҖиҰ§иЎЁдҪңжҲҗгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«гҒқгҒҗгӮҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁдҪ•еәҰгӮӮжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҸҚеҝңгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢдәӨд»ЈгҒ—гҒҹгӮүгҖҒж–°гҒ—гҒ„иЈҒеҲӨе®ҳгҒҜжүӢз¶ҡгӮ’гӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«гҒқгҒ®зӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҖҒдҪңжҲҗж–№жі•гӮ’ж”№гӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҢҮзӨәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒжүӢз¶ҡгҒ®еҗ„е ҙйқўгҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§жӮ©гӮҖй »еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гӮӮеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зү№еҫҙгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ ж–№гҒ§гҖҒдәӢжЎҲгҒ®иӘҝжҹ»жӨңиЁҺгӮ„жүӢз¶ҡгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§иЎҢгҒҚи©°гҒЈгҒҹгӮҠжӮ©гӮ“гҒ гӮҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҢгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зөҢйЁ“иұҠеҜҢгҒӘејҒиӯ·еЈ«гҒёгҒ®зӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгӮӮгҒ—еҝғеҪ“гҒҹгӮҠгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгӮүйҒ ж…®гҒӘгҒҸеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҫгҒ§гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
йҒ ж–№гҒ®ж–№гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ§еҠ©иЁҖгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҫ®еҠӣгҒӘгҒҢгӮүгҒҠеҠӣгҒ«гҒӘгӮҢгӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұпҪһгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ®дёӯгҒ§еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§иө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁ
е…Ҳж—ҘгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«гҒӨгҒҚгҖҒз—ҮдҫӢжӨңиЁҺгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзңҢеҶ…гҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«жүҖеұһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒҢгҖҒеӨҡеҝҷгҒӘдёӯгҖҒжҷӮй–“гӮ’еүІгҒ„гҒҰеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«жқҘгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®з—ҮдҫӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒйқһеёёгҒ«дёҒеҜ§гҒ«гҒҠи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ§з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹиіҮж–ҷгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒзҡ„зўәгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§гҖҒд»ҠгҒ®еҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЎқж’ғзҡ„гҒӘгҒҠи©ұгӮ’дјәгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒзңӢйҒҺгҒ—йӣЈгҒ„дёҚжқЎзҗҶгҒӘзҸҫе®ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®гҒҠи©ұгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒҢеәғгҒҢгӮӢдёӯгҖҒжңҖгӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢй ҳеҹҹгҒ®дёҖгҒӨгҒҢеҢ»зҷӮгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜз•°и«–гҒ®гҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиҲӘз©әгҖҒиҰіе…үгҖҒж—…иЎҢгҖҒеӨ–йЈҹгҖҒйўЁдҝ—гҖҒиҮӘеӢ•и»Ҡз”ЈжҘӯгҒӘгҒ©гҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒйқһеёёгҒ«иӢҰгҒ—гҒҸгҖҒе…ҲгҒҢиӘӯгӮҒгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз”ЈжҘӯгҒҜж•°еӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҖҒиЈҪйҖ гҒ®зҸҫе ҙгҒӢгӮүжң«з«ҜгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гҒҫгҒ§еӨ§еӨҡж•°гҒ®еӣҪж°‘гҒҢж·ұеҲ»гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮгҒҜгҒҫгҒҹйҒ•гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ®еӨ§еӨүгҒ•гӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®иҮЁеәҠзҸҫе ҙгҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«ж„ҹжҹ“гҒ—гҒҹгҒӢгҖҒж„ҹжҹ“гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒҢиЁӘгӮҢгҖҒиЁәж–ӯгҖҒжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒҶжңҖеүҚз·ҡгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«ж„ҹжҹ“гҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гӮ’ж•‘гҒҶгҒ№гҒҸгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒж—ҘгҖ…гҖҒиҮӘгӮүгҒҢж„ҹжҹ“гҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒЁиғҢдёӯеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҖҒе‘ҪгӮ’еүҠгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰй—ҳгҒ„з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒЁгҒ®й—ҳгҒ„гҒ«ж•—гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҖҒе®ҹдҪ“зөҢжёҲгҒ®еӣһеҫ©гҒ©гҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзӨҫдјҡгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеҙ©еЈҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒд»ҠгҖҒгҒқгҒ®жңҖеүҚз·ҡгҒҜгҒ®гҒЈгҒҙгҒҚгҒӘгӮүгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒйқўи«ҮгҒ®йҡӣгҒ«еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒ«гӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®еҪұйҹҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠе°ӢгҒӯгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢгҒқгӮҢгҒҜгӮӮгҒҶеӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒҶгҒЎгҒ®з—…йҷўгӮӮжҪ°гӮҢгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжң¬еҪ“гҒ«еҺігҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгӮҲгҖҚгҒЁгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®з—…йҷўгҒҜгҖҒй•·гҒҸз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢең°еҹҹгҒ®еҹәе№№з—…йҷўгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢж–№йҮқгҒӘгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒзҷәзҶұгҒ®жӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢйҡӣгҖҒеӨ§йғЁеұӢгӮ’дҪҝгҒҶе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒж„ҹжҹ“гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҗҢгҒҳйғЁеұӢгҒ«гҒ»гҒӢгҒ®жӮЈиҖ…гӮ’е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®з—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒе·®йЎҚгғҷгғғгғүд»ЈгҒҜеҸ–гӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҷгғғгғүгҒҢеҠ№зҺҮзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢгғҖгғЎгғјгӮёгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ—гҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒгӮігғӯгғҠж„ҹжҹ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠұгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®иІ жӢ…гҒҜгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒӘйқўгҒ§гӮӮйқһеёёгҒ«ж·ұеҲ»гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ«й©ҡгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®з—…йҷўгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗҢгҒҳгӮЁгғӘгӮўгҒ«гҒӮгӮӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ®еҜҫеҝңгӮ’дјәгҒЈгҒҹжҷӮгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®з·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒзҷәзҶұжӮЈиҖ…гҒҜгҒқгӮӮгҒқгӮӮеҸ—иЁәгҒҷгӮүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгӮігғӯгғҠж„ҹжҹ“гғӘгӮ№гӮҜгҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гҒҜдёҖеҲҮеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеёӮеҶ…гҒ®дҝқеҒҘжүҖгҖҒж¶ҲйҳІзҪІгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзҷәзҶұе…ҶеҖҷгҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜз«ҜгҒӢгӮүгҒқгҒ®з—…йҷўгҒ«гҒҜйҖҒгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯгӮ’гҒҷгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҖҒеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гҒ—гӮҸеҜ„гҒӣгҒҜзҷәзҶұжӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢз—…йҷўгҒ®гҒҝгҒ«жқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зўәгҒӢгҒ«гҖҒгҒІгҒЁгҒҹгҒігҖҒйҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒҢиө·гҒҚгӮӢгҒЁгҖҒз—…жЈҹй–үйҺ–гҖҒеӨ–жқҘдёӯжӯўгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҜҫеҝңгӮ’иҝ«гӮүгӮҢгӮӢгҒ—гҖҒйўЁи©•иў«е®ізҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’еҗ«гӮҒгҖҒз—…йҷўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзөҢе–¶дёҠгӮӮж·ұеҲ»гҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз—…йҷўгҒҢгҒқгӮҢгӮ’йҒҝгҒ‘гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢзҷәжғіиҮӘдҪ“гҒҜзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжӮЈиҖ…жң¬дҪҚгҒ®иүҜеҝғзҡ„гҒӘз—…йҷўгҒҜгҖҒзҷәзҶұжӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§йҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠұгҒҲгӮӢдёҠгҖҒйқһеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘйҒӢе–¶гӮ’еј·гҒ„гӮүгӮҢгҒҰиөӨеӯ—гҒ«йҷҘгӮүгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҗҪе·®гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«зҗҶдёҚе°ҪгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹз—…йҷўгҒҜгҒӨгҒ¶гӮҢгҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„з—…йҷўгҒ°гҒӢгӮҠгҒҢз”ҹгҒҚж®ӢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„дәӢж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…Ҳж—ҘиҰӢгҒҹгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјиЁҳдәӢгҒ§гҖҒиҒ–и·ҜеҠ еӣҪйҡӣз—…йҷўгҒ®йҷўй•·гӮӮиҝ°гҒ№гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ®жңҖеүҚз·ҡгҒ§жҮёе‘ҪгҒ«й—ҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҒ“гҒқгҖҒж”ҝеәңгҒӢгӮүжүӢеҺҡгҒ„иЈңеҠ©гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷпјҲгғӘгӮ№гӮҜгҒ®гҒӮгӮӢжӮЈиҖ…гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„з—…йҷўгӮ’йқһйӣЈгҒҷгӮӢи¶Јж—ЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ«еј•гҒҚжҸӣгҒҲгҖҒд»ҠгҒ®е®үеҖҚж”ҝжЁ©гҒҢгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®йҶңжӮӘгҒ•гҒҜзӣ®гҒ«дҪҷгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮўгғҷгғҺгғһгӮ№гӮҜгҒ«ж•°зҷҫе„„еҶҶгӮ’無駄гҒ«иІ»гӮ„гҒ—гҖҒйҮ‘иһҚеёӮе ҙгҒ°гҒӢгӮҠгҒ«гҒҳгӮғгҒ¶гҒҳгӮғгҒ¶гҒЁйҮ‘гӮ’жіЁгҒҺиҫјгҒҝгҖҒгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ®гҒ©гҒ•гҒҸгҒ•гҒ«гҒҫгҒҺгӮҢгҒҰгҖҒжӨңеҜҹеәҒжі•гӮ„зЁ®иӢ—жі•гҒ®ж”№жӯЈжЎҲгҒӘгҒ©гҒ®дёҚиҰҒдёҚжҖҘгҒӢгҒӨеӣҪж°‘гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүе®із„ЎзӣҠгҒӘжі•жЎҲгӮ’еӣҪдјҡгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҖҒеј·иЎҢзӘҒз ҙгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠеҜҫзӯ–гҒЁз§°гҒ—гҒҰгҖҒйӣ»йҖҡгӮ„гғ‘гӮҪгғҠзӯүгҒ«дҫҝе®ңгӮ’еӣігӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒеӣҪгҒЁгҒ®й–“гҒ«гғҲгғігғҚгғ«дјҡзӨҫгӮүгҒ—гҒҚгӮӮгҒ®гӮ’жҢҹгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гғ”гғігғҸгғҚгҒҢжЁӘиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮүгҒ—гҒҚе®ҹж…ӢгҒҫгҒ§гӮӮгҒҢжҳҺгӮӢгҒҝгҒ«еҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎеӣҪж°‘гҒҜгҖҒд»ҠгҒ“гҒқгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠзӣ®гӮ’иҰӢй–ӢгҒҚгҖҒгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ«жӯЈйқўгҒӢгӮүеҜҫеіҷгҒ—гҒҰжҗҚеҫ—жҠңгҒҚгҒ«й—ҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮ„ж©ҹй–ўгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ“гҒқгҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹиЈңеҠ©гҖҒдёӢж”ҜгҒҲгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮӮз№°гӮҠиҝ”гҒ—иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮгҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎеӣҪж°‘гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰе‘ҪгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж¬ гҒҸгҒ№гҒӢгӮүгҒ–гӮӢгӮ»гғјгғ•гғҶгӮЈгғҚгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгӮ»гғјгғ•гғҶгӮЈгғҚгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®еҢ»зҷӮгӮ’и»ҪгӮ“гҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж”ҝзӯ–гҒҢз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹзөҗжһңгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®зөҢе–¶гҒҜгҒІгҒЈиҝ«гҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒҢз–ІејҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲгҒқгӮҢгҒҢе®ҹйҡӣгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®иҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮ
гҒҷгҒ§гҒ«гҒқгӮ“гҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒд»ҠгҒ®гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңҖеүҚз·ҡгҒ§й—ҳгҒҶеҢ»зҷӮиҖ…гҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ’зҠ¬жӯ»гҒ«гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒ„гӮҸгҒ‘гҒҢгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгӮ»гғјгғ•гғҶгӮЈгғҚгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҢ»зҷӮгҒҢеҒҘе…ЁгҒ«ж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж”ҝзӯ–еҜҫеҝңгӮ’зңҹеүЈгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚжҷӮгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҝғгҒӮгӮӢж”ҝ治家гҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҢгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒиә«гӮ’е‘ҲгҒ—гҒҰй—ҳгҒҶеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢзөҢе–¶з ҙ綻гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒгҒқгҒ“гҒ§еғҚгҒҸеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®еҠҙиӢҰгҒҢе ұгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒйҮҚзӮ№зҡ„гҒ«дҝқйҡңгҒ•гӮҢгӮӢж”ҝзӯ–гҒ«ж–№еҗ‘жҖ§гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒдҪ“гӮ’ејөгҒЈгҒҰй ‘ејөгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®йҒёжҢҷгҒ§гҒҜгҖҒзңҹгҒ«еӣҪж°‘гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҝзӯ–гӮ’з«ӢжЎҲгҖҒе®ҹиЎҢгҒ§гҒҚгӮӢдәәгӮ’з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®д»ЈиЎЁиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰйҒёгҒ°гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгӮ’ж”ҜгҒҲгҒҰжқҘгҒҹеҢ»зҷӮгҒҢеӨүиіӘгҒ—гҖҒеҙ©еЈҠгҒ—гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒеј·гҒҸеҚұжғ§гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһеІЎжұҹд№…зҫҺеӯҗгҒ•гӮ“гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҖқгҒҶгҒ“гҒЁ
еҘіе„ӘгҒ®еІЎжұҹд№…зҫҺеӯҗгҒ•гӮ“гҒҢгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«ж„ҹжҹ“гҒ—гҒҰдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғүгғ©гғһгӮ„гҖҒгӮҜгӮӨгӮәз•Әзө„гҖҒжңқгҒ®гғҜгӮӨгғүгӮ·гғ§гғјзӯүгҒ§гҒҡгҒЈгҒЁжҙ»иәҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжҳҺгӮӢгҒҸиҰӘгҒ—гҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҒ«ж„ӣгҒ•гӮҢгҒҹеҘіе„ӘгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе…ҲгҒ®еҝ—жқ‘гҒ‘гӮ“гҒ•гӮ“еҗҢж§ҳгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒЁгҒҰгӮӮж®ӢеҝөгҒ§гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®дәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®зөҢз·ҜгӮ’зҹҘгӮӢгҒ«гҒӨгҒ‘гҖҒгҒ“гҒ®жӯ»гҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒдәәзҒҪгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӣёгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒҢиЎЁйқўеҢ–гҒ—гҒҰд»ҘйҷҚгҖҒж”ҝеәңгӮ„еҺҡеҠҙзңҒгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҙ©еЈҠгӮ’жӢӣгҒҚгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжӨңжҹ»е®ҹж–ҪгҒ«гҒӨгҒҚгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гӮӮжүӢз¶ҡзҡ„гҒ«гӮӮиҰҒ件гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гӮ’дёҠгҒ’гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе®үеҖҚйҰ–зӣёиҮӘгӮүгҒҢдёҖж—Ҙпј’дёҮ件гҒ®жӨңжҹ»гҒҢеҸҜиғҪгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжңӘгҒ гҒ«дёҖж—Ҙж•°еҚғ件гҒ®е®ҹж–ҪгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж”ҝзӯ–гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮгҒҡгҒЈгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒйҒҺеҺ»гҒ®иЁҳдәӢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒ“гҒ®й–“гҖҒе…ЁеӣҪеҗ„ең°гҒ§йҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒ«гӮҲгӮӢгӮҜгғ©гӮ№гӮҝгғјгҒ®зҷәз”ҹгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиӘ°гҒҢж„ҹжҹ“иҖ…гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒз—…йҷўеҶ…гӮ’дәәгҒҢгҒҶгӮҚгҒӨгҒ‘гҒ°йҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒҢйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°еӯҗдҫӣгҒ§гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘи©ұгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҷўеҶ…ж„ҹжҹ“гҒ®еәғгҒҢгӮҠгҒҜгҖҒжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгҒҢдёҚеҫ№еә•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®зөҗжһңгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дҪ•еәҰгӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒҜгҖҒгӮӨгғігғ•гғ«гӮЁгғігӮ¶гӮҲгӮҠгӮӮзҷәз—ҮгҒҫгҒ§гҒ®жҪңдјҸжңҹй–“гҒҢй•·гҒҸгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҒқгҒ®й–“гҒ«ж„ҹжҹ“гҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӨңжҹ»гӮ’еҫ№еә•гҒ—гҒҰж„ҹжҹ“иҖ…гҒ®жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гӮ’гҒ—гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒж„ҹжҹ“гҒ®зөӮжҒҜгҒҜе®№жҳ“гҒ«иҰӢиҫјгӮҒгҒҡгҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«еӣҪж°‘з”ҹжҙ»гӮӮз–ІејҠгҖҒеҠЈеҢ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж”ҝеәңгӮӮгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«жқҘгҒҰгӮ„гҒЈгҒЁжӨңжҹ»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжҢҮйҮқгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгҒ„еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§жӨңжҹ»гҒҢеҚҒеҲҶгҒ«е®ҹж–ҪгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе®үеҖҚйҰ–зӣёгӮӮеҠ и—ӨеҺҡеҠҙеӨ§иҮЈгӮӮгҒҫгӮӢгҒ§д»–дәәдәӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁҖгҒ„йҖғгӮҢгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе‘ҶгӮҢгҒҰгӮӮгҒ®гҒҢиЁҖгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҹгҒігҒ®еІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®жӯ»гӮӮгҖҒдёҖдәәдёҖдәәгҒ®еӣҪж°‘гҒ®е‘ҪгӮ’и»ҪиҰ–гҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҹж”ҝеәңгҒ®иӘӨгҒЈгҒҹж”ҝзӯ–гҒ«гӮҲгӮӢзҠ зүІгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҢж§ҳгҒ®зҠ зүІиҖ…гҒҢгҒ»гҒӢгҒ«гӮӮеӨ§еӢўгҒ„гӮӢгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•зҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гҒ«еҠ гҒҲгҖҒгҖҢж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гӮӮдәӨгҒҲгҒҰжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒе ұйҒ“гҒ«гӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒпј”жңҲпј“ж—ҘгҒ«зҷәзҶұгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒдё»жІ»еҢ»гҒӢгӮүгҖҢиҮӘе®…гҒ§пј”пҪһпј•ж—Ҙж§ҳеӯҗгӮ’иҰӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҒЁгҒ®жҢҮзӨәгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®жҢҮзӨәгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒжӨңжҹ»гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘе®…гҒ§йқҷйӨҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒпј“ж—ҘеҫҢгҒ®жңқгҒҫгҒ§гҒ«жҖҘжҝҖгҒ«з—ҮзҠ¶гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҖҒз—…йҷўгҒ«жҗ¬йҖҒгҒ•гӮҢгҖҒжӨңжҹ»гҒ§йҷҪжҖ§еҸҚеҝңгҒҢеҮәгҒҰгҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёеҷЁгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒӘгҒ©гҒ®жІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒжІ»зҷӮгҒ®з”Іж–җгҒӘгҒҸеё°гӮүгҒ¬дәәгҒЁгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘжғ…е ұгҒҜгҖҒеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒҢд№ізҷҢгӮ’жӮЈгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҖҒзӣҙеүҚгҒҫгҒ§ж”ҫе°„з·ҡжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒе•ҸйЎҢгҒҜж”ҫе°„з·ҡжІ»зҷӮгӮҲгӮҠзҷҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒзі–е°ҝз—…гӮ„зҷҢгҒӘгҒ©гҒ®жҢҒз—…гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢж–№гҒҜгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„гҒ«гҒҜгҖҢжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҖҚгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еӯ—гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒеҒҘеёёгҒӘдәәгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰж„ҹжҹ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹж„ҹжҹ“гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«йҮҚзҜӨеҢ–гҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢжӮЈиҖ…гҒ§гҒҷгҖӮ
зҷҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒе…ғгҖ…гҖҒдәәй–“гҒ®дҪ“еҶ…гҒ§гҒҜгҒ”гҒҸжҷ®йҖҡгҒ«зҷҢзҙ°иғһгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҰжқҘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзҷҢгҒ®зҷәз—ҮгҒ«зөҗгҒід»ҳгҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒзҷҪиЎҖзҗғдёӯгҒ®гғҠгғҒгғҘгғ©гғ«гӮӯгғ©гғјзҙ°иғһпјҲпј®пј«зҙ°иғһпјүгҒӘгҒ©гҒ®е…Қз–«зі»зҙ°иғһгҒҢзҷҢзҙ°иғһгӮ’йҖҖжІ»гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒе…Қз–«зі»гҒҜиӨҮйӣ‘гҒӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒ®дёҠгҒ«жҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§гҒҫгҒӢгҒ«гҒ„гҒҶгҒЁгҖҒдҪ“еҶ…гҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҖҒе…Қз–«зі»гҒҢжҡҙиө°гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе…Қз–«жҠ‘еҲ¶зҙ°иғһгҒҢгҖҒзҷҢзҙ°иғһгҒ®еў—ж®–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еў—еҠ гҒ—гҖҒе…Қз–«зі»зҙ°иғһгҒ®жҙ»еӢ•гӮ’еј·гҒҸжҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҰгҖҒзҷҢзҙ°иғһгҒёгҒ®ж”»ж’ғгӮ’гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰзҷҢзҙ°иғһгҒҢгҒ•гӮүгҒ«еў—ж®–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж©ҹеәҸгҒҢеӯҳгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒзҷҢжӮЈиҖ…гҒ®дҪ“еҶ…гҒ§гҒҜгҖҒе…Қз–«жҠ‘еҲ¶зҙ°иғһгҒҢеӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдҪ“еҶ…гҒ®е…Қз–«гҒҜеҚҒеҲҶгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫеңЁгҖҒз§ҒгҒҜгҖҒж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…жЎҲ件гӮ’иӨҮж•°жҠұгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒҢиө·гҒҚгӮӢе°‘гҒ—еүҚгҒ«гҖҒеӣҪеҶ…гҒ§и‘—еҗҚгҒӘж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ«й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҷҢжӮЈиҖ…гҒҢжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢзҷҢжӮЈиҖ…гӮ„зі–е°ҝз—…жӮЈиҖ…гҒӘгҒ©гҒ®жҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж„ҹжҹ“з—ҮгӮ’иө·гҒ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгӮҲгӮҠйҮҚзҜӨеҢ–гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҖҢгҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®зҷәз—ҮгҖҒеў—жӮӘгҒ«гҒӨгҒҚгӮҲгӮҠеҺійҮҚгҒӘиЁәеҜҹгҒЁж„ҹжҹ“з—ҮеҜҫеҝңгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁжҳҺзўәгҒӘжҢҮж‘ҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҝ»гҒЈгҒҰгҖҒд»ҠеӣһгҒ®еІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®е ҙеҗҲгӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒи©ізҙ°гҒӘдәӢжғ…гҒҜдёҚжҳҺгҒӘгҒҢгӮүгҖҒдё»жІ»еҢ»гҒҢгӮӮгҒ—еІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®зҷҢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҖҒдҪ•гҒҜгҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҖҒжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгҒЁз—…йҷўеҶ…гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҺійҮҚгҒӘиҰіеҜҹгҒёгҒЁгғӘгғјгғүгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ®пј°пјЈпјІжӨңжҹ»е®ҹж–ҪгҒ®е®ҹж…ӢгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҢ»её«гҒ®иҗҪгҒЎеәҰгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ«зӯүгҒ—гҒ„гҒ»гҒ©гҒ®й«ҳгҒ„гғҸгғјгғүгғ«гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹеӣҪгҒ®иӘӨгҒЈгҒҹж–№йҮқгҒҢжӢӣгҒ„гҒҹзөҗжһңгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒй ҶеәҸгҒҢйҖҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢжӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»®гҒ«з—ҮзҠ¶зҡ„гҒ«гҒҜи»ҪгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜжӨңжҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒйҷҪжҖ§гҒӢеҗҰгҒӢгҒ®еҲӨж–ӯгӮ’гҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§йҷҪжҖ§гҒ®зөҗжһңгҒҢеҮәгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜпјҲеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®е ҙеҗҲгҒҜзөҢз·ҜгҒӢгӮүгҒ—гҒҰеҪ“然гҒ«йҷҪжҖ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖҒд»®гҒ«гҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢжҜ”ијғзҡ„з©ҸгӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢж„ҹжҹ“з—ҮгӮ’иө·гҒ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгӮҲгӮҠйҮҚзҜӨеҢ–гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖҚжҳ“ж„ҹжҹ“жҖ§жӮЈиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒдҪ•гӮ’жҺӘгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒе…ҘйҷўгӮ’жҢҮзӨәгҒ—гҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁж„ҹжҹ“з—ҮеҜҫзӯ–гӮ’еҸ–гӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜиҮӘжҳҺгҒ®зҗҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜжұәгҒ—гҒҰзөҗжһңи«–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдёҠиЁҳгҒ®ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжң¬зҡ„зҹҘиҰӢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒеҪ“然гҒ®и«–зҗҶзҡ„её°зөҗгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжӨңжҹ»гҒ®зөҗжһңгҒҢйҷҪжҖ§гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҖҚгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжҢҒз—…гӮ’жңүгҒ—гҒӘгҒ„дәәгҖҒе‘јеҗёеҷЁзі»гҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ„жӮЈиҖ…гҒҜиҮӘе®…еҫ…ж©ҹгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜзӣёеҝңгҒ®ж–ҪиЁӯеҶ…гҒ§гҒ®иҰіеҜҹгҒ§гҒ„гҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒ®гӮ№гӮҝгғјгғҲгғ©гӮӨгғігҒҜжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒеҗҢж§ҳгҒ«жӨңжҹ»гҒ•гҒҲеҸ—гҒ‘гӮҢгҒҡгҒ«иҮӘе®…еҫ…ж©ҹгҒ®гҒҫгҒҫдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹжҳ“ж„ҹжҹ“з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӣҪгҒ®иӘӨгҒЈгҒҹжҢҮйҮқгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢе…ҘйҷўгҒ—гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘжІ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢж©ҹдјҡгӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгҒҹгҖҚгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ®е…ӢжңҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеҪўгҒ®жҙ»еӢ•гҒ®иҮӘзІӣгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҒ„гҒЈгҒҹеҠӘеҠӣгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢпјҲгҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜз•°и«–гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢпјүгҖҒжӨңжҹ»гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гӮ’з„Ўз”ЁгҒ«й«ҳгҒҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰж„ҹжҹ“иҖ…гҒ®жүұгҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӣ–жҳ§гҒӘж–№йҮқгӮ’й ‘гҒӘгҒ«з¶ӯжҢҒгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢд»ҠгҒ®ж”ҝеәңгӮ„еҺҡеҠҙзңҒгҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒ§гҒҜгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§зөҢгҒЈгҒҰгӮӮж„ҹжҹ“гҒҢзөӮжҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ зүІиҖ…гҒҢгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮеў—гҒҲгҒҰиЎҢгҒҸгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеј·гҒҸеҚұжғ§гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гӮӮеІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜж°·еұұгҒ®дёҖи§’гҒ«гҒҷгҒҺгҒҡгҖҒжң¬еҪ“гҒӘгӮүжӯ»гӮ’йҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®ж–№гҒҢеӣҪгҒ®ж”ҝзӯ–гҒ®иӘӨгӮҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«зӣёеҪ“еӨҡж•°зҠ зүІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжӨңжҹ»гҒҢйҖҹгӮ„гҒӢгҒ«е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°зўәе®ҹгҒ«еҠ©гҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгӮұгғјгӮ№гғҗгӮӨгӮұгғјгӮ№гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӘӨгҒЈгҒҹжҢҮйҮқгӮ’й ‘гҒӘгҒ«з¶ҡгҒ‘гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§йҒ©еҲҮгҒӘжІ»зҷӮгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’еҘӘгҒЈгҒҹеӣҪгӮ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ®еӣҪе®¶иі е„ҹиІ¬д»»гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе®ҹдҫӢгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢгғ’гғҘгғјгғһгғігӮЁгғ©гғјгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒгҒқгҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒӮгӮӢз–ІејҠгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ®е®ҹж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҢ»зҷӮгӮ’е·ЎгӮӢж§ҳгҖ…гҒ®з’°еўғзҡ„гҒӘеҲ¶зҙ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҒ«зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁз—ӣж„ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҒ•гӮүгҒӘгӮӢиғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮиІ»еүҠжёӣгҒ«еҒҸгҒЈгҒҹеӣҪгҒ®иӘӨгҒЈгҒҹж”ҝзӯ–гҒҢж №гҒЈгҒ“гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжӨңжҹ»е®ҹж–ҪгҒ®дёҚеҫ№еә•гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®дёҚи¶ігҖҒйӣҶдёӯжІ»зҷӮе®ӨгҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёеҷЁгҒӘгҒ©гҒ®еҝ…иҰҒгҒӘиЁӯеӮҷгҒ®дёҚи¶ігҒЁгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгҒ®ж”№е–„гӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒдҝқеҒҘжүҖгҒ®еҪ№еүІгӮ’и»ҪиҰ–гҒ•гӮҢгҖҒжёӣгӮүгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҖҒеӣҪгҒҢгҖҒеӣҪж°‘гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгӮ»гғјгғ•гғҶгӮЈгғҚгғғгғҲгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢеҢ»зҷӮгӮ’и»ҪгӮ“гҒҳгҒҰжқҘгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиғҢжҷҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒ—гӮҸеҜ„гҒӣгҒ§гҖҒжӮЈиҖ…гҒҢйҒ©еҲҮгҒӘеҢ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜжұәгҒ—гҒҰиҰӢйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еІЎжұҹгҒ•гӮ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиў«е®іиҖ…гӮ’гҒ“гӮҢд»ҘдёҠеў—гӮ„гҒ•гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜжӨңжҹ»е®ҹж–ҪгҒ®еҫ№еә•гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®ж©ҹдјҡгҒ«гҒ“гҒқгҖҒдёҖдәәдёҖдәәгҒ®еӣҪж°‘гҒҢйҒ©еҲҮгҒӘеҢ»зҷӮгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ№гҒҸеҢ»зҷӮгҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’еҶҚж§ӢзҜүгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒҢжӮЈиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҢ»зҷӮгҒ«жү“гҒЎиҫјгӮҒгӮӢз’°еўғгҒҢе®ҹзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸйЎҳгӮҸгҒҡгҒ«гҒҜгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһгҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹгҖҢйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҖҚгҒ®ж”№гҒ–гӮ“ж–№жі•
гғҶгғ¬гғ“жңқж—ҘгҒ§гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ®гғӘгғЎгӮӨгӮҜзүҲгҒҢж”ҫжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒігҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒиЁҖгӮҸгҒҡгҒЁзҹҘгӮҢгҒҹеұұеҙҺиұҠеӯҗеҺҹдҪңгҒ®еҗҚдҪңеҢ»зҷӮгғүгғ©гғһгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҺҹдҪңгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒҜгӮӢгҒӢжҳ”гҒ®жҳӯе’ҢгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҺҹдҪңгӮ’еҝ е®ҹгҒ«жҸҸгҒ‘гҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁзӯүгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гғӘгғЎгӮӨгӮҜзүҲгҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҹгӮўгғ¬гғігӮёгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ§еӯҰз—…йҷўгҒҢиҲһеҸ°гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢеҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгғүгғ©гғһгҒ®дёӯгҒ§гҒӢгҒӘгӮҠйҮҚиҰҒгҒӘдҪҝгӮҸгӮҢж–№гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӢгҒ„гҒӨгҒҫгӮ“гҒ§жӣёгҒҸгҒЁгҖҒдё»дәәе…¬гҒ®иІЎеүҚеҢ»её«гҒҢеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҖҒйғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒ«еҸЈиЈҸеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’жҢҮзӨәгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹжүӢиЎ“иЁҳйҢІгҒҢж”№гҒ–гӮ“гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒ®ж–№жі•гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸдёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҒ гҒЁдҪ•гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ®дёӯгҒ§жӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹж”№гҒ–гӮ“жүӢжі•гҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢдёҖгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒігҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ«гғ«гғҶгҒ®ж”№гҒ–гӮ“ж–№жі•гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶдёҠгҒ«йғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒҢжӣёгҒ„гҒҹжүӢиЎ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳијүгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«дёҚеҲ©гҒӘеҶ…е®№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиЁҳијүгҒ—гҒҹеҢ»её«гӮ’иІЎеүҚеҢ»её«гҒҢе‘јгҒігҒӨгҒ‘гҖҒгҒқгҒ®иЁҳијүгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®гҖҢд»®зҷ»йҢІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж®өйҡҺгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҖҢд»®зҷ»йҢІгҒӘгӮүгҖҒжӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҢеҸҜиғҪгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ®иЁҳиҝ°гҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲпјҲж”№гҒ–гӮ“пјүгӮ’иҝ«гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
йғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒҜгҖҒиӢҰжӮ©гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®жҢҮзӨәгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒдёҚеҲ©гҒӘиЁҳијүгӮ’жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒзңҹзӣёгҒ®и§ЈжҳҺгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§дёҚйғҪеҗҲгҒӘиЁҳдәӢгӮ’жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢзӮәгҒҢгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢдёҖгҒ®жүӢеҸЈгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЁҳдәӢгӮ’йҖ”дёӯгҒҫгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ«жӣёгҒҚи¶ігҒ—гҒҹгӮҠгҖҒиЁӮжӯЈгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒжҖҘгҒ«еҲҘгҒ®жӮЈиҖ…еҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮе…ЁеҗҰе®ҡгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢд»®зҷ»йҢІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжүӢжі•гӮ’жӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жӣҙж–°еұҘжӯҙгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒд»®зҷ»йҢІдёӯгҒ«жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒеүҠйҷӨгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹиЁҳијүгҒҢгҖҒжӣҙж–°еұҘжӯҙдёӯгҒ«гҒҜеҮәгҒҰжқҘгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒе…ғгҖ…дҪ•гҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдәӢж•…гҒ§дҪ•гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гҖҢжң¬зҷ»йҢІгҖҚгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжӣҙж–°еұҘжӯҙгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӨңиЁјгҒҢеҸҜиғҪгҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒд»®зҷ»йҢІдёӯгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёи§ЈжҳҺгӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚеӨ§гҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҷгғігғҖгғјгҒ«гӮҲгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮӮгҒ—гҒҡгҒЈгҒЁд»®зҷ»йҢІгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒдәӢж•…еҫҢгҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮж”№гҒ–гӮ“гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜгҒқгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒд»®зҷ»йҢІгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёгӮ’йҡ гҒәгҒ„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҡ гӮҢи“‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®з–‘еҝөгӮ’жҠұгҒӢгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гғүгғ©гғһгҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®гӮ«гғ«гғҶж”№гҒ–гӮ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨгӮ·гғјгғігҒ§еҢ»зҷӮеҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ—гҒҹиЁјжӢ гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁеҸҚи«–гҒ—гҖҒж”№гҒ–гӮ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹжҳҺзҷҪгҒӘиЁјжӢ гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гӮҶгҒ гҒӯгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гғјгғігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁз•°и«–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒҜжӣҙж–°еұҘжӯҙдёҠгҒ«гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиЎЁгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№дёҠгҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“еүҚеҫҢгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®жҷӮеҲ»гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰиЁҳйҢІгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ—гҒӨгҒ“гҒҸжұӮгӮҒгҒҹзөҗжһңгҖҒгҒӮгҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®з—•и·ЎгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®д»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж”№гҒ–гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢз«Ӣе ҙгҒ«з«ӢгҒҰгҒ°гҖҒйқһеёёгҒ«з”ұгҖ…гҒ—гҒҚе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жӮӘиіӘгҒӘжүӢеҸЈгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ«иӘҚзҹҘгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶеҸҚйқўгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҒ«гҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§гҒ“гҒ®жүӢжі•гҒҢжЁӘиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒйқһеёёгҒ«гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹиЁҳдәӢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гӮӮжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢзңҹжӯЈжҖ§гҖҚгҖҢиҰӢиӘӯжҖ§гҖҚгҖҢдҝқеӯҳжҖ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёүеҺҹеүҮгҒҢзӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и©ізҙ°гҒҜгҒқгҒЎгӮүгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҰҒгҒҜгҖҒеҫҢгҒ§гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжӨңиЁјгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘд»•зө„гҒҝгҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®д»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒҜгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ“гҒ®дёүеҺҹеүҮгӮ’йҖёи„ұгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—©гҒ„и©ұгҖҒд»®зҷ»йҢІгҒЁгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгҒҜгҒ•гҒЈгҒ•гҒЁз„ЎгҒҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
еҢ»зҷӮиҖ…гҒҜгҖҒиЁҳијүйҖ”дёӯгҒ§гӮӮгҖҒз·ҠжҖҘеҜҫеҝңгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒиЁҳијүйҖ”дёӯгҒ§гӮӮгҖҒжң¬зҷ»йҢІгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҠ зӯҶиЁӮжӯЈгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгӮүгҖҒжӣҙж–°гҒҷгӮҢгҒ°и¶ігӮҠгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫе ҙгҒ§гҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒдәӢж•…гҒ®жӨңиЁјгҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгҒ—гӮҚгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰгғүгғ©гғһгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҖҒ公然гҒЁгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”№гҒ–гӮ“гҒ®ж–№жі•гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеӣҪж°‘гҒ®еҒҘеә·гҖҒз”ҹе‘ҪгҒ«гҒӨгҒҚиІ¬д»»гӮ’иІ гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҺҡеҠҙзңҒгҒҢзҺҮе…ҲгҒ—гҒҰйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®ж¬ йҷҘгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжҠңжң¬зҡ„гҒӘж”№е–„гӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжүӢгӮ’жү“гҒӨгҒ№гҒҚгҒ гҒЁеј·гҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ«й–ўгҒҷгӮӢж„ҹжғігҒҜгҒқгҒЈгҒЎгҒ®гҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«иҲҲе‘іж·ұгҒҸй‘‘иіһгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұпҪһеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ®дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒӨгҒ„е…Ҳж—ҘгҖҒпј’жӯігҒ®еӯҗдҫӣгҒ®иҷ«жӯҜжІ»зҷӮгҒ§гҖҒжӯҜ科еҢ»её«гҒҢжӯҜиҢҺгҒ«гғӘгғүгӮ«гӮӨгғігҒЁгҒ„гҒҶеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе°„гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒз—ҷж”ЈгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҖҒдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ӣгҒҫгҒ—гҒ„дәӢж•…гҒ®е ұйҒ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒ»гҒјеҗҢдёҖеҶ…е®№гҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҸҫеңЁиЁҙиЁҹдҝӮеұһдёӯгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гӮ„дёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҒёгҒ®жіЁж„Ҹе–ҡиө·гҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮиҫјгӮҒгҒҰгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж•…гҒ®дәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒҜгҖҒжҰӮз•Ҙд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
иӢҘгҒ„з”·жҖ§жӮЈиҖ…гҒҢиӮ©еҮқгӮҠгҒ®жІ»зҷӮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иЎҢгҒҚгҒӨгҒ‘гҒ®ж•ҙеҪўеӨ–科гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ«иЎҢгҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҖҒйҰ–гҒӢгӮүиғҢдёӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰеұҖжүҖйә»й…”и–¬гғӘгғүгӮ«гӮӨгғігӮ’жіЁе°„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зӣҙеҫҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҜеҢ»её«гҒ®зӣ®гҒ®еүҚгҒ§ж„ҸиӯҳгӮ’ж¶ҲеӨұгҒ—гҖҒеҝғеҒңжӯўгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҜгҖҒеҗҢгҒҳиЎҢж”ҝеҢәеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢеӨ§еӯҰз—…йҷўгҒ«ж•‘жҖҘжҗ¬йҖҒгҒ•гӮҢгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“иҳҮз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«йҮҚзҜӨгҒӘдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзөҗеұҖдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғӢгғҘгғјгӮ№е ұйҒ“гҒ•гӮҢгҒҹдәӢж•…гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒжӯҜ科еҢ»гҒЁж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®йҒ•гҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®зӮ№гҒҜйқһеёёгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒ§ж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®еҢ»её«гҒҢиЎҢгҒЈгҒҹжіЁе°„гҒҜгҖҒең§з—ӣзӮ№гҒ«еұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе…ҘгҒҷгӮӢгғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгӮ„ж•ҙеҪўеӨ–科гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжіЁе°„гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’и„ігҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеӢ•и„ҲгҒ«иӘӨжіЁе…ҘгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒжҖҘжҝҖгҒӘж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҖҒеҝғеҒңжӯўгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҜҫеҮҰгӮ’иӘӨгӮӢгҒЁе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдәӢж•…гҒ®зҷәз”ҹгӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҢгҒҫгҒҡйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒз©ҝеҲәеҫҢгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе…ҘгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгғҗгғғгӮҜгғ•гғӯгғјгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжіЁе°„йҮқгӮ’гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“еј•гҒҚжҲ»гҒ—гҖҒиЎҖгҒҢж··гҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢжүӢжҠҖгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢпјҲиЎҖгҒҢж··гҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°жіЁе°„йҮқгҒҜиЎҖз®ЎеҶ…гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’е°‘йҮҸгҒҡгҒӨе…ҘгӮҢгҒӘгҒҢгӮүж§ҳеӯҗгҒ®еӨүеҢ–гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢпјҲз—ҮзҠ¶гҒҜжҖҘжҝҖгҒ«еҮәгҒҰжқҘгҒҫгҒҷпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж…ҺйҮҚгҒӘжүӢй ҶгӮ’иёҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҮдёҖдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҰгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®е®№ж…ӢгҒҢжҖҘеӨүгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»ҠеәҰгҒҜж…ҢгҒҰгҒҡгҒ«йҖҹгӮ„гҒӢгҒӘж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гӮ’еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮиӮқиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҖҘеӨүгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®е…·дҪ“зҡ„еҜҫеҮҰгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеј•гҒҚйҮ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒ®иЎҖдёӯжҝғеәҰгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҮҰзҪ®гӮӮеҝ…иҰҒгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢеҝғеҒңжӯўгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮе„Әе…ҲгҒ—гҒҰе®ҹж–ҪгҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒиғёйӘЁең§иҝ«гҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғіжҠ•дёҺгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж•‘жҖҘиҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дәәй–“гҒ®дҪ“гҒ§гҒҜи„ігҒҢй…ёзҙ гҒ®пј”еүІгӮ’ж¶ҲиІ»гҒ—гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒи„ігҒёгҒ®й…ёзҙ дҫӣзөҰгҒҢдёҖе®ҡжҷӮй–“д»ҘдёҠйҖ”зө¶гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒи„ігҒ«йҡңе®ігҒҢж®ӢгӮҠгҖҒдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҹгҒ гҒЎгҒ«и„ігҒёгҒ®й…ёзҙ дҫӣзөҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жүӢжҠҖгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзӣёи«ҮгҒ—гҒҹгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒҢзөҢйЁ“и«ҮгҒЁгҒ—гҒҰиӘһгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҖҒеұҖжүҖйә»й…”дёӯжҜ’гҒ«гӮҲгӮӢеҝғеҒңжӯўгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«иғёйӘЁең§иҝ«гҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғіжҠ•дёҺзӯүгҒ®иҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒЁжҖҘйҖҹгҒӘијёж¶ІзӯүгӮ’иЎҢгҒҲгҒ°гҖҒжӮЈиҖ…гҒҜгҖҒгҒ»гҒ©гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒЈгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҒҷгӮ“гҒӘгӮҠгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§дҪ•дәӢгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«зӣ®иҰҡгӮҒгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгӮӮгҖҒд»ҠеӣһгҒ®е ұйҒ“гҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ж—ҘеёёгҒ®иЁәзҷӮгҒ®й ҳеҹҹгҒҢгҖҒе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гӮ„еёӮдёӯгҒ®гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ§гҒ®дәӢж•…гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§е…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ«жӮЈиҖ…гҒҢзӣ®гҒ®еүҚгҒ§еҝғеҒңжӯўгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјҲе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҒқгҒҶгҒ§гҒҷпјүгҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒҜгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢеҢ»её«гҒ«дҪҝз”Ёжі•гӮ’иӘӨгӮӢгҒЁе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢи–¬еүӨгӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҚұж©ҹж„ҹгҒҢд№ҸгҒ—гҒ„еҢ»её«гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’йқһеёёгҒ«еҚұжғ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁи©ұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж•…гӮ„д»ҠеӣһгҒ®е ұйҒ“гҒ®дәӢж•…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒ®жҠ•дёҺгҒ«гҒҜе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢдәӢж…ӢгӮ’жӢӣгҒҸгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеҶ…еңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’йә»й…”еҮҰзҪ®гӮ„зҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжІ»зҷӮгҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж—Ҙеёёзҡ„гҒ«дҪҝгҒҶеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮж…ҺйҮҚгҒӘжүӢжҠҖгҒ®гғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҒ®еҫ№еә•гҒЁгҖҒж•‘е‘ҪиҳҮз”ҹгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢдәӢж…ӢгҒёгҒ®еӮҷгҒҲгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гҒ®е‘ҪгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӮҷгҒҲгӮ„еҚұж©ҹж„ҸиӯҳгҒҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒе®үжҳ“гҒ«еұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе®ҹж…ӢгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ§гӮӮгҖҒж•ҙеҪўеӨ–科еҢ»гҒҜгҖҒж•‘е‘ҪиҳҮз”ҹгҒ®з¬¬дёҖйҒёжҠһи–¬гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігӮ’еёёеӮҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҝғеҒңжӯўеҫҢгҖҒгҒӘгҒңгҒӢгҒқгӮҢгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігҒ«гҒҜеҝғжӢҚгӮ’еў—еј·гҒ—гҖҒжң«жўўгҒ®иЎҖз®ЎгӮ’з· гӮҒгӮӢдҪңз”Ёж©ҹеәҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒи„ігҒӘгҒ©гҒ®дё»иҰҒиҮ“еҷЁгҒёгҒ®иЎҖж¶ІеҫӘз’°пјҲгҒӨгҒҫгӮҠй…ёзҙ дҫӣзөҰпјүгҒҢе„Әе…Ҳзҡ„гҒ«зўәдҝқгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒҜгҖҒж•‘жҖҘйҡҠе“ЎгҒ§гӮӮжҠ•дёҺеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨгҒ®еүҚгҒ«дәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹж•ҙеҪўеӨ–科еҢ»гҒ«дјҡгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе°ӢгҒӯгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢиЎҖжөҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиғёйӘЁең§иҝ«гӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢж„Ҹе‘ігҒҷгӮүгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иғёйӘЁең§иҝ«гӮ„дәәе·Ҙе‘јеҗёзӯүгҒҜгҖҒгҖҢж•‘жҖҘиҳҮз”ҹгҒ®пјЎпјўпјЈгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒеӨ§еӯҰгӮ„иҮЁеәҠгҒ®е®ҹзҝ’гҒ§еӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒ®гҒ”гҒҸеҲқжӯ©зҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҷгӮүзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҢ»её«гҒҢеҝғеҒңжӯўгҒ®еҚұйҷәгӮ’еӯ•гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’гҒ”гҒҸж—Ҙеёёзҡ„гҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫзҠ¶гҒ«гҒҜз©әжҒҗгӮҚгҒ—гҒ•гҒҷгӮүж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠгӮҲгҒқе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ®гҖҒгҖҢиӮ©еҮқгӮҠгҖҚгӮ„гҖҢиҷ«жӯҜгҖҚгҒ®жІ»зҷӮгҒ§гҒӘгҒңеӨ§еҲҮгҒӘе‘ҪгҒҢеҘӘгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹжӮЈиҖ…гӮ„гҒқгҒ®гҒ”йҒәж—ҸгҒ®з„ЎеҝөгҒ•гӮ’жҖқгҒҶгҒЁгҖҒж•‘жҖҘиҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒҷгӮүгҒҫгҒЁгӮӮгҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»её«гҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жүұгҒҶиіҮж јгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒҷгӮүжҖқгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒ®йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒҜеӨ§дёҲеӨ«гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
еҢ»зҷӮиҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰдёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжіЁж„Ҹе–ҡиө·гӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иЁҳдәӢгӮ’жӣёгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ