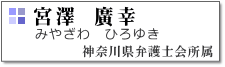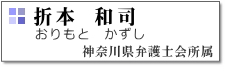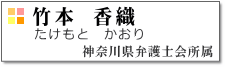еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҒӮгӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®жҸҗиЁҙ
гҒ“гҒ“гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӢгҒӘгӮҠгҒ®жҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁжә–еӮҷгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒӮгӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒд»ҠйҖұгҖҒжҸҗиЁҙгҒ®жүӢз¶ҡгӮ’еҸ–гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢ件гҒҜгҖҒжӯ»дәЎдәӢж•…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдәӢж•…еҫҢгҒ®з—…йҷўеҒҙгҒ®иӘ¬жҳҺгҒҢжӯ»гҒ«зӣҙзөҗгҒ—гҒҹйҮҚеӨ§гҒӘдәӢе®ҹгӮ’йҡ гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹеҺҹеӣ гҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒиӘҝжҹ»гӮ’йҮҚгҒӯгҒҰиЎҢгҒҸдёӯгҒ§гҖҒгӮ„гҒЈгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒҢйҡ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖҢйҮҚеӨ§гҒӘдәӢе®ҹгҖҚгҒ«иҫҝгӮҠзқҖгҒ‘гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢжЎҲгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
д»ҠеҫҢгҖҒиЁҙиЁҹгҒ®йҖІеұ•гҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ®гҒ”дәҶи§ЈгҒҢгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢзҜ„еӣІгҒ§гҖҒгҒқгҒ®зөҢйҒҺе ұе‘ҠгҒӘгҒ©гӮӮиЎҢгҒЈгҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®йҒҺгҒЈгҒҹеҜҫеҝңгҒҢгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰжӮЈиҖ…гӮ„гҒ”йҒәж—ҸгҒ®еҢ»зҷӮдёҚдҝЎгӮ’й«ҳгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеҢ»зҷӮй–ўдҝӮиҖ…гҒ®ж–№гҒ«гҒҜгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁгҒӨгҒҸгҒҘгҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҲ‘дәӢжүӢз¶ҡгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжӣ–жҳ§гҒӘиӘ¬жҳҺгҒҢжӮЈиҖ…гӮ„гҒ”йҒәж—ҸгҒ®дёҚдҝЎж„ҹгӮ’еӢҹгӮүгҒӣгҖҒжң¬жқҘгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®еҲ‘дәӢдәӢ件еҢ–гӮ’жӢӣгҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжң¬д»¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒжҸҗиЁҙеүҚгҒ«гҖҒеҢ»зҷӮеҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒ«гҖҒйҡ и”ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹдәӢе®ҹгҒЁгҒқгӮҢгҒҢжӯ»гҒ«з№ӢгҒҢгҒЈгҒҹйҮҚеӨ§гҒӘйҒҺеӨұгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰз©ҸдҫҝгҒӘи§ЈжұәгӮ’еӣігӮӢгӮҲгҒҶжұӮгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒҜгҖҒгҒ‘гӮҖгҒ«е·»гҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдёҚеҸҜи§ЈгҒӘиӘ¬жҳҺгҒ§гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®жұӮгӮҒгӮ’жӢ’гҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзөҗеұҖгҖҒжҸҗиЁҙгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒҢеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®йҮҚеӨ§гҒӘйҒҺеӨұгҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎдәӢж•…гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгӮ’еҸ–гӮҠгҖҒеұ•й–ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®е°Ӣе•ҸгҒӘгҒ©гҒ®е®ҹж–ҪгҒ«иҮігӮүгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдёҚжҜӣгҒ гҒ—гҖҒзҺҮзӣҙгҒӘеҝғжғ…гҒЁгҒ—гҒҰз”ігҒ—дёҠгҒ’гӮҢгҒ°гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®йқһгӮ’гҒӮгҒ’гҒӨгӮүгҒЈгҒҰж”»ж’ғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰжң¬ж„ҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жҷӮгҒ«з–‘е•ҸгҒ«жҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®д»ЈзҗҶдәәгҒҜгҖҒиӘ°гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д»ЈзҗҶдәәжҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
жң¬жқҘгҒ®дҫқй јиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®еҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ„еҢ»её«гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жҙ»еӢ•гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒЁгҖҒиғёгӮ’ејөгҒЈгҒҰиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„ж–№гӮӮгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
дәӨжёүгӮ„иЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒиі е„ҹйҮ‘гӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘жү•гҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„дҝқйҷәдјҡзӨҫгҒ®еҲ©зӣҠгҒ®гҒҹгӮҒпјҲгҒ гҒ‘пјүгҒ«жҙ»еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжі•е»·гҒӘгҒ©гҒ§гҖҒгҒқгҒ®иЁҖи‘үгҒҢе–үе…ғгҒҫгҒ§еҮәгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒдҝқйҷәдјҡзӨҫгҒ®еҲ©зӣҠгҒЁеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ„еҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®еҲ©зӣҠгҒҜжҷӮгҒ«зӣёеҸҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®жҷӮгҒ«гҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’е„Әе…ҲгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒзӯ”гҒҲгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
и©ұгҒҢгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁйҖёгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬д»¶дәӢж•…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®еҸ–гӮӢгҒ№гҒҚеҜҫеҝңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜж•ҷиЁ“гҒЁгҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®дәӢиұЎгҒҢгҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҖҒдҪ•еҮҰгҒӢгҒ§гҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮӮеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһи…•гҒҫгҒҸгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢеҢ»иҖ…
гҒҫгҒҹгӮӮгӮ„еӨ§и…ёзҷҢзөЎгҒҝгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®гҒҠи©ұгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгӮӢе№ҙй…ҚгҒ®з”·жҖ§гҒҢи…№з—ӣгӮ’иЁҙгҒҲгҖҒгҖҢжҖҘжҖ§и…№з—ҮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒЁгҒӮгӮӢз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«е…ҘйҷўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒ иӢҘгҒ„ж¶ҲеҢ–еҷЁеҶ…科гҒ®еҢ»её«гҒҢжӢ…еҪ“еҢ»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҢ»её«гҒҜгҖҒи…№йғЁи¶…йҹіжіўжӨңжҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹдёҠгҒ§е°ҝз®ЎзөҗзҹігҒ®иЁәж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зөҗи«–гҒӢгӮүиЁҖгҒҶгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜиӘӨиЁәгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜеӨ§и…ёзҷҢз”ұжқҘгҒ®и…ёй–үеЎһпјҲгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№пјүгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®иӘӨиЁәгҒҜгҒқгҒ®еҫҢгҒ®жІ»зҷӮж–№йҮқгҒ«йҮҚеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒе°ҝз®ЎзөҗзҹігҒ®е ҙеҗҲгҖҒж¶ҲеҢ–з®ЎгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒйЈҹдәӢж‘ӮеҸ–гӮӮOKгҒ гҒ—гҖҒж°ҙеҲҶгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгӮҖгҒ—гӮҚз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еӨҡгҒҸж‘ӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒЁгҒ®жҢҮзӨәгҒҢеҮәгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§и…ёзҷҢз”ұжқҘгҒ®гӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒи…ёз®ЎгҒ®йҖҡйҒҺйҡңе®ігҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ“гҒ«ж‘ӮеҸ–гҒ—гҒҹйЈҹзү©гӮ„ж°ҙгҒҢгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“е…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ§жқҘгӮҢгҒ°гҖҒи…ёз®ЎгҒҢгҒ•гӮүгҒ«жӢЎејөгҒ—гҖҒгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒҜжӮӘеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеӨ§и…ёзҷҢз”ұжқҘгҒ®гӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒзҷҢгҒҢи…ёз®ЎгӮ’еЎһгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдҝқеӯҳзҷӮжі•гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҷҢгҒ®еҲҮйҷӨгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒи…ёз®ЎгҒ®йҖҡйҒҺйҡңе®ігҒҜи§ЈйҷӨгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒи…ёз®ЎгҒ®жёӣең§гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒзө¶йЈҹгҖҒзө¶ж°ҙгӮ’гҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§и…№з—ӣгҒҢеў—еј·гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®з”·жҖ§гҒҜжҲ‘ж…ўгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒжӢ…еҪ“еҢ»гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢе°ҝз®ЎзөҗзҹігҒӘгӮ“гҒӢгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҖӮз—ӣгҒ„гҒ®гҒҜгҒҠи…№гҒ гҒӢгӮүгҒЎгӮғгӮ“гҒЁиӘҝгҒ№гҒҰгҒҸгӮҢгҖҚгҒЁиЁҙгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҢ»её«гҒҢжӮЈиҖ…гҒ®иЁҙгҒҲгӮ’иҒһгҒҚе…ҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жӮЈиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«и…№гӮ’з«ӢгҒҰгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒеҢ»её«гҒҜгҖҒи…•гҒҫгҒҸгӮҠгӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҖҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜеҢ»иҖ…гҒ®гҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢиҒһгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖӮгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒ•гҒЈгҒ•гҒЁйҖҖйҷўгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„ж”ҫгҒӨгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®жҷӮгҒҜгҖҒгҒқгҒ°гҒ«гҒ„гҒҹ家ж—ҸгӮ„зңӢиӯ·её«гҒҢгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“еҸ–гӮҠгҒӘгҒ—гҒҰгҒқгҒ®е ҙгӮ’еҸҺгӮҒгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…жң¬дәәгҒҜгҖҒз—ӣгҒҝжӯўгӮҒгҒҜеҠ№гҒӢгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгҒҠи…№гҒҢејөгҒЈгҒҰиӢҰгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзөҗеұҖгҖҒгҖҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒ„гҒҹгӮүж®әгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚгҒЁзңӢиӯ·её«гҒ«иЁҖгҒ„ж®ӢгҒ—гҒҰеӢқжүӢгҒ«йҖҖйҷўгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жӮЈиҖ…гҒҜгҖҒгҒқгҒ®и¶ігҒ§йҡЈгҒ®еёӮгҒ®з—…йҷўгҒ«иЎҢгҒҚгҖҒжӨңжҹ»гӮ’дҫқй јгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®з—…йҷўгҒ§гғ¬гғігғҲгӮІгғіжӨңжҹ»гӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒӘгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№жүҖиҰӢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жіЁи…ёйҖ еҪұжӨңжҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®и…№з—ӣгҒ®еҺҹеӣ гҒҜгҖҒе°ҝз®ЎзөҗзҹігҒӘгҒ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ«гӮҲгӮӢгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒеүҚгҒ®з—…йҷўгҒ®еҢ»её«гҒ®иЁәж–ӯгҒҢе®Ңе…ЁгҒӘиӘӨиЁәгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иӘӨиЁәгҒ®йқһеёёгҒ«гҒҫгҒҡгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҖҒе°ҝз®ЎзөҗзҹігҒҜйЈҹдәӢж‘ӮеҸ–гҒҢе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ°гҒӢгӮҠгҒӢгҖҒж°ҙеҲҶгҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒҜз©ҚжҘөзҡ„гҒ«ж‘ӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгҒ«гҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒи…ёз®Ўжёӣең§гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзө¶йЈҹгҖҒзө¶ж°ҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ®е ҙеҗҲгҒЁгҒҜжІ»зҷӮж–№йҮқгҒҢзңҹйҖҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҖҘжҖ§и…№з—ҮгҒ§жқҘйҷўгҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒҚгҖҒжҷӮгҒ«зҡ„еӨ–гӮҢгҒӘиЁәж–ӯгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еӣәеҹ·гҒ—гҒҰгҖҒиӘӨгҒЈгҒҹиЁәзҷӮж–№йҮқгӮ’з«ӢгҒҰгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжІ»зҷӮгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’еӨұгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢдҫӢгҒ«гҒҜжҷӮжҠҳгӮҠеҮәгҒҸгӮҸгҒҷгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«жң¬д»¶гҒҜгҖҒжҖҘжҖ§и…№з—ҮжӮЈиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе®үжҳ“гҒ«жұәгӮҒгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж…ҺйҮҚгҒ«й‘‘еҲҘиЁәж–ӯгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«еӨ§еҲҮгҒӢгӮ’зӨәгҒҷе…ёеһӢдҫӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒз«ӢдҪҚгҒ®гғ¬гғігғҲгӮІгғігӮ’иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгғӢгғңгғјпјҲйҸЎйқўеғҸпјүгҒЁгҒ„гҒҶеҚҠжҘ•еҶҶеҪўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ¬гӮ№еғҸгҒҢзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢеӨ§и…ёзҷҢгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒӢгҖҒзҷ’зқҖгҒӘгҒ©еҲҘгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒӢгҒ®й‘‘еҲҘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӨ§и…ёеҶ…иҰ–йҸЎгӮ„жіЁи…ёйҖ еҪұжӨңжҹ»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӨңжҹ»гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзө¶йЈҹгҖҒзө¶ж°ҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒӢеҗҰгҒӢгҒ®еҲӨж–ӯгҒҜгҒ“гҒ®гғ¬гғігғҲгӮІгғіжӨңжҹ»гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжң¬д»¶гҒ§гҖҒж¬ЎгҒ®з—…йҷўгҒ§е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹжіЁи…ёйҖ еҪұжӨңжҹ»гҒ§гҒҜгҖҒгӮўгғғгғ—гғ«гӮігӮўпјҲгғӘгғігӮҙгҒ®иҠҜпјүгӮөгӮӨгғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖҒйҖІиЎҢеӨ§и…ёзҷҢгҒ§гӮҲгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢе…ёеһӢзҡ„гҒӘз”»еғҸгҒҢйҖ еҪұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгҒӮгҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®и…•гҒҫгҒҸгӮҠгӮ’гҒ—гҒҹеҢ»её«гҒҢе°ҝз®ЎзөҗзҹігҒЁиЁәж–ӯгҒ—гҒҹгӮЁгӮігғјжӨңжҹ»з”»еғҸгӮ’е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ«иҰӢгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе°ҝз®ЎзөҗзҹігӮүгҒ—гҒҚжүҖиҰӢгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҰӢеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰеёёгҖ…жҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе‘ҪгӮ„еҒҘеә·гҒ«й–ўгӮҸгӮӢеҢ»её«гҒЁгҒ„гҒҶд»•дәӢгҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒ«еӨ§еӨүгҒ гҒ—гҖҒе°Ҡ敬гҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚиҒ·жҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘жӮЈиҖ…гҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒҶиҮЁеәҠзҸҫе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж…ҺйҮҚгҒ•гҒЁеӢӨеӢүгҒ•гҖҒеҢ»еӯҰгӮ„жӮЈиҖ…гҒ®иЁҙгҒҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи¬ҷиҷҡгҒ•гҖҒйҖ”дёӯгҒ§иЁәж–ӯгӮ„ж–№йҮқгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷжҹ”и»ҹгҒ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж§ҳгҖ…гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶйҮҚгҒ„д»•дәӢгҒӘгҒ®гҒ гҒЁгҖҒгҒӨгҒҸгҒҘгҒҸгҒқгҒҶжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз ”дҝ®еҢ»гҒЁеҢ»зҷӮдәӢж•…part2
д»ҘеүҚгҖҒжң¬гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӮгҖҒз«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«з ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«йҒӯйҒҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒж”№гӮҒгҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒзөҢйЁ“гҒ®жө…гҒ„з ”дҝ®еҢ»гҒ«иЁәзҷӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’еҚҳзӢ¬гҒ§гҒ•гҒӣгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒеҝ…гҒҡдёҠзҙҡеҢ»гҒҢжҢҮе°ҺгҖҒгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜеҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒжңҖиҝ‘йҒӯйҒҮгҒ—гҒҹз—ҮдҫӢгҒ§гӮӮдёҠзҙҡеҢ»гҒ«гӮҲгӮӢжҢҮе°ҺгҖҒгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹеҪўи·ЎгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҶ…гҒ®пј‘件гҒ®ж–№гҒ§гӮ«гғ«гғҶгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒ®еҢ»её«иЁҳйҢІйғЁеҲҶгҒ®гҖҒеҢ»её«еҗҚгҒ®еүҚгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҖҢпјӘпј‘гҖҚгҖҢпјӘпј’гҖҚгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖзһ¬гҖҒгӮөгғғгӮ«гғјгҒ®пјӘгғӘгғјгӮ°гҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®зөҢйЁ“е№ҙж•°гӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢиЎЁиЁҳгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒқгҒ®з—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢпјӘпј‘гҖҚгҒЁгҒҜеүҚжңҹз ”дҝ®еҢ»гҒ®пј‘е№ҙзӣ®гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒгҖҢпјӘпј’гҖҚгҒЁгҒҜеүҚжңҹз ”дҝ®еҢ»гҒ®пј’е№ҙзӣ®гӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒJгҒҜгӮёгғҘгғӢгӮўгҒ®ж„Ҹе‘ігҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гҒқгӮҢгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒд»ҘеүҚгҖҒеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹдәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҫҢжңҹз ”дҝ®еҢ»гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еүҚжңҹз ”дҝ®гҒ®пј’е№ҙгҒ®зөҢйЁ“гӮ’зөҢгҒҹпј“е№ҙзӣ®д»ҘйҷҚгҒ®еҢ»её«гҒ«гӮҲгӮӢдәӢж•…гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®дәӢж•…гҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«зөҢйЁ“гҒ®е°‘гҒӘгҒ„пј‘пҪһпј’е№ҙзӣ®гҒ®ж–°зұіеҢ»её«гҒ®й–ўдёҺгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеј•гҒҚиө·гҒ“гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®гҖҢпјӘпј‘гҖҚгҖҢпјӘпј’гҖҚгҒЁгӮ«гғ«гғҶгҒ«иЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒж•—иЎҖз—ҮгҒЁгҒ„гҒҶиЁәж–ӯгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгғҗгӮӨгӮҝгғ«зӣЈиҰ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғўгғӢгӮҝгғјгӮӮиЁӯзҪ®гҒӣгҒҡгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®жҖҘеӨүгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒҢйҒ…гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»её«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж•—иЎҖз—ҮгҒ§гҒҜгҖҒж„ҹжҹ“гҒ«гӮҲгӮҠе…Ёиә«гҒ«еӨҡж§ҳгҒӘжүҖиҰӢгҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгӮ·гғ§гғғгӮҜгҒӘгҒ©гҖҒж•—иЎҖз—ҮгҒӢгӮүз”ҹгҒҳгӮӢеҗҲдҪөз—ҮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӯ»дәЎгҒ«иҮігӮӢеҚұйҷәжҖ§гӮӮй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжҠ—з”ҹеүӨгӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒе‘јеҗёгҖҒи„ҲжӢҚгҖҒдҪ“жё©гҒӘгҒ©гӮ’еҺійҮҚгҒ«з®ЎзҗҶгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгғўгғӢгӮҝгғјгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҖҒиЎҖең§гҖҒи„ҲжӢҚгҖҒе‘јеҗёгҒӘгҒ©гӮ’зөҢжҷӮзҡ„гҒ«иҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒе°ҝйҮҸгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ„еӢ•и„ҲиЎҖж¶ІгӮ¬гӮ№еҲҶжһҗгҒӘгҒ©гӮ’й »еӣһгҒ«гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҖҒз—…ж…ӢгҒ®еӨүеҢ–гҒ«еҝңгҒҳгҒҹйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫеҮҰгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз ”дҝ®еҢ»гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒҜгҖҒзҹҘиӯҳгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒиҮЁеәҠзҸҫе ҙгҒ§гҒӘгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҢиә«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒе®№ж…ӢгҒ®еӨүеҢ–гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиҮЁж©ҹеҝңеӨүгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зөҢйЁ“еҖӨгӮӮгҖҒгғҷгғҶгғ©гғігҒ®еҢ»иҖ…гҒ«жҜ”гҒ№гӮҢгҒ°еҪ“然д№ҸгҒ—гҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гӮ’гҖҒгҒҹгҒ гҒЎгҒ«жі•зҡ„гҒӘйҒҺеӨұгҒЁи©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒдәӢж•…гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷйҮҚеӨ§гҒӘиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«гҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒ—гҖҒжң¬иіӘзҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒе…Ҳж—ҘгҖҒеҲҘгҒ®иЁҳдәӢгҒ§и§ҰгӮҢгҒҹеӨ§и…ёзҷҢгҒ®иҰӢиҗҪгҒЁгҒ—гҒ®дәӢж•…гӮӮгҖҒе®ҹгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘеұҖйқўгҒ«з ”дҝ®еҢ»гҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒ—гҖҒгҒ»гҒӢгҒ«гӮӮз ”дҝ®еҢ»гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢиӢҘжүӢгҒ®еҢ»её«гҒ«д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ§жҖҘеӨүгҒ«еҜҫеҮҰгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
и©ұгӮ’жҲ»гҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«з ”дҝ®еҢ»зөЎгҒҝгҒ®з—ҮдҫӢгӮ’зӣ®гҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеҚҳгҒӘгӮӢе·ЎгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒЁгҒҜгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҖғгҒҲгҒҘгӮүгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еүҚгҒ®иЁҳдәӢгҒ§гӮӮжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдәә件費еүҠжёӣгҒ®гҒҹгӮҒгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдәәжқҗгҒ®зўәдҝқгҒҢеӨ§еӨүгҒ гҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒжң¬еҪ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж§ӢйҖ зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹиҮЁеәҠеҢ»гҒ®ж–№гҒ®иЁҳдәӢгӮ’зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иӘӨи§ЈгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҢиЁәзҷӮиЎҢзӮәгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иӢҘгҒ„еҢ»её«гҒҢзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгӮҖгҒ“гҒЁгҒҜеӨ§еҲҮгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжӮЈиҖ…гҒ®е‘ҪгӮ’й җгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’зөҢйЁ“гҒ®д№ҸгҒ—гҒ„з ”дҝ®дёӯгҒ®еҢ»её«гҒ«д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹеҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёҠзҙҡеҢ»гҒ®жҢҮе°ҺгҖҒгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’жҖ гӮүгҒӘгҒ„д»•зө„гҒҝгҒ«гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁеЈ°гӮ’еӨ§гҒ«гҒ—гҒҰиЁҖгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҢзӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒқгҒ®иЁҳдәӢгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҜдҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘйӣ‘з”ЁгӮ’гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ®е®ҹзҠ¶гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз ”дҝ®еҢ»гӮ’жҲҰеҠӣгҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„е®ҹж…ӢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹзҷәжғігҒҢеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮ„гӮүгҒӣгҒҰгҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгҒ®еўғз•Ңз·ҡгҒҢгӮҲгӮҠжӣ–жҳ§гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҚұйҷәгҒҢгӮҲгӮҠй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁгӮӮгҒҶдёҖгҒӨжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гӮ’д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ«гҒ•гӮҢгҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒҢгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҰгҒқгҒ®жӮЈиҖ…гӮ’жӯ»дәЎгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®з ”дҝ®еҢ»гҒҜгҒқгҒ®иІ гҒ„зӣ®гӮ’гҒҡгҒЈгҒЁж„ҹгҒҳз¶ҡгҒ‘гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҢ»её«гҒЁгҒ„гҒҶд»•дәӢгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»ҘеүҚгҖҒгҒӮгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒӢгӮүгҒҶгҒӢгҒҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҫҢиј©гҒ®еҢ»её«гҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢзҠҜгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гғЎгғігӮҝгғ«зҡ„гҒ«з—…гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гҖҒз—…йҷўгӮ’иҫһгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒ иӢҘгҒҸзөҢйЁ“гҒ®жө…гҒ„гҖҒе°ҶжқҘгҒ®гҒӮгӮӢеҢ»её«гҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҹиІ гҒ„зӣ®гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҢеҚҳзӢ¬гҒ§йӣЈгҒ—гҒ„еҲӨж–ӯгӮ’еј·гҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„д»•зө„гҒҝдҪңгӮҠгӮ’еҫ№еә•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҒЁеј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҲӨж–ӯгҒ«иҝ·гҒҶжҷӮгҒҜгҖҒиҮҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸдёҠзҙҡеҢ»гҒ®жҢҮзӨәгӮ’д»°гҒҗеӢҮж°—гӮ„иҰҡжӮҹгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҜжң¬еҪ“гҒ«еӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з—…йҷўгҒ®еҶ…йғЁдәӢжғ…гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүдёҠдёӢй–ўдҝӮгҒ§ж’ҘгҒӯгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®е‘ҪгӮ’й җгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүзөҢйЁ“иұҠеҜҢгҒӘеҢ»её«гҒ®еҲӨж–ӯгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒЁиёҸгӮ“ејөгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮз ”дҝ®еҢ»гҒ®ж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„зөҗжһңгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒңгҒІгҒқгҒҶгҒӮгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»зөЎгҒҝгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒҫгҒ гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒҫгҒҹеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеӨ§и…ёзҷҢгҒ®гҒҠи©ұ
гҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒж¶ҲеҢ–еҷЁзі»гҒ®дәӢ件гҖҒдёӯгҒ§гӮӮеӨ§и…ёзҷҢгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮжЎҲ件гҒҢгҒӢгҒӘгӮҠеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
е·ЎгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж°—гӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒзҷҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзөұиЁҲгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎиҖ…ж•°гҒҜгҖҒз”·жҖ§гҒ§гҒҜпј“дҪҚгҖҒеҘіжҖ§гҒ§гҒҜпј‘дҪҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰе№ҙй–“гҒ§зҙ„пј•дёҮдәәгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгӮӮгҖҒзөұиЁҲгҒ®жҺЁз§»гӮ’йҒЎгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒиғғзҷҢгӮ„иӮқиҮ“зҷҢгҒ®жӯ»дәЎиҖ…ж•°гҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢжЁӘгҒ°гҒ„гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ®жӯ»дәЎиҖ…ж•°гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еў—еҠ еӮҫеҗ‘гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҷҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжӨңжҹ»жҠҖиЎ“гӮӮжІ»зҷӮж–№жі•гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸйҖІжӯ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒӘгҒңеҗҢгҒҳж¶ҲеҢ–еҷЁзі»гҒ®зҷҢгҒ§гҒӮгӮӢиғғзҷҢгҒҢжёӣгӮҠгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰжӮЈиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ§и…ёзҷҢеў—еҠ гҒ®зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгӮҲгҒҸиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒйЈҹгҒ®ж¬§зұіеҢ–гҒ§гҒҷгҖӮ
иӮүгӮ„д№іиЈҪе“ҒгҒ®ж¶ҲиІ»гҒҢеў—гҒҲгҖҒйЈҹзү©з№Ҡз¶ӯгҒ®ж‘ӮеҸ–гҒҢжёӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҸгғҜгӮӨгҒ«з§»дҪҸгҒ—гҒҹж—Ҙжң¬дәәгҒ®зҷәз—ҮзҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе ұйҒ“гҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒиҖҒе»ғзү©гҒҢжәңгҒҫгӮӢиҮ“еҷЁгҒ§гҒӮгӮӢеӨ§и…ёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢз–ҫжӮЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®йЈҹзҝ’ж…ЈгҒ®еӨүеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгҒҜзўәгҒӢгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ®еҜҝе‘ҪгҒҢ延гҒігҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒж¶ҲеҢ–еҷЁзі»гҒ®зҷҢгҒ®зҷәз—ҮзҺҮгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮ№гғҲгғ¬гӮ№зӨҫдјҡгҒ®еҪұйҹҝгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҢҮж‘ҳгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒдёҖж–№гҒ§гҖҒиғғзҷҢгҒ®жӯ»дәЎзҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеҗҢгҒҳж¶ҲеҢ–еҷЁзі»гҒ§гҒӮгӮӢеӨ§и…ёзҷҢгҒ®жӯ»дәЎзҺҮгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜдҪ•ж•…гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гҒҫгҒҡгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжҜ”ијғзҡ„иҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҢд№ҸгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҷәиҰӢгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжӮЈиҖ…гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиғғгӮ«гғЎгғ©гҒ«жҜ”гҒ№гҖҒеӨ§и…ёеҶ…иҰ–йҸЎгҒҜжӨңжҹ»гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжүӢи»ҪгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҪұйҹҝгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ®еҘҪзҷәйғЁдҪҚгҒҜзӣҙи…ёгҒӢгӮүпјізҠ¶зөҗ腸移иЎҢйғЁгҒӮгҒҹгӮҠгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁд»ҘеүҚгҒ«иҰӢгҒҹеҢ»зҷӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгғӢгғҘгғјгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒзөҗи…ёзҷҢгҒҢеў—гҒҲгҒҰжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғҮгғјгӮҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҶ…гҖҒзӣҙи…ёзҷҢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдҫҝз§ҳгҒЁдёӢз—ўгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶиҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гҒҢзҸҫгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒжӨңдҫҝгҒ§дҫҝжҪңиЎҖеҸҚеҝңгҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүзӣҙи…ёйҸЎжӨңжҹ»гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ§гҖҒжҜ”ијғзҡ„ж—©жңҹгҒ«зҷәиҰӢгҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒ„зҷҢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒдёҠиЎҢзөҗи…ёгӮ„жЁӘиЎҢзөҗи…ёгҒӘгҒ©гҒ®дёҠйғЁеӨ§и…ёгҒ®йғЁдҪҚгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢзҷҢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиҮӘиҰҡз—ҮзҠ¶гӮӮд№ҸгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒдҫҝжҪңиЎҖеҸҚеҝңгӮӮеҮәгҒ«гҒҸгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёӢйғЁеӨ§и…ёгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҖҒеӨ§и…ёеҶ…иҰ–йҸЎжӨңжҹ»гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ«д№—гӮҠгҒ«гҒҸгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзҷҢгҒ®зҷәиҰӢгҒҢйҒ…гӮҢгҒҢгҒЎгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒжңҖиҝ‘гҖҒзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹеӨ§и…ёзҷҢгҒ®з—ҮдҫӢгҒҜгҖҒдёҠйғЁзөҗи…ёзҷҢгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдёҠйғЁеӨ§и…ёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҷҢгҒ®зҷәз”ҹзҺҮгҒ®дёҠжҳҮгҒҢгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ®жӯ»дәЎзҺҮгҒ®дёҠжҳҮгҒ«зӣёеҪ“зЁӢеәҰеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзөұиЁҲгҒ®еҲҶжһҗгҒҜгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«е°Ӯй–Җй ҳеҹҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҙ дәәгҒҢи»ҪгҖ…гҒ«зөҗи«–гӮҒгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ®жӯ»дәЎиҖ…ж•°гҒҢеў—еҠ еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҺіз„¶гҒҹгӮӢдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰеӨ§и…ёзҷҢгҒ®ж—©жңҹзҷәиҰӢгҒ«еҠӘгӮҒгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ§и…ёзҷҢгҒ®ж—©жңҹзҷәиҰӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘж¶ҲеҢ–еҷЁзі»гҒ®и…«зҳҚгғһгғјгӮ«гғјжӨңжҹ»гҒ®е®ҹж–ҪгӮ„гҖҒпјЈпјҙжӨңжҹ»гҖҒеӨ§и…ёеҶ…иҰ–йҸЎжӨңжҹ»зӯүгӮ’е„„еҠ«гҒҢгӮүгҒҡгҒ«еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒзҸҫе®ҹгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҷгӮүгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®еҒҙгӮӮгҖҒеӨ§и…ёзҷҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҚұж©ҹж„ҸиӯҳгҒҢдҪҺгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ®зӣёи«ҮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒиғғгӮ«гғЎгғ©гҒ®е®ҹж–ҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨ§и…ёзҷҢгӮ’з–‘гҒҶгҒ№гҒҚжүҖиҰӢгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒеҢ»её«гҒҢгҒқгҒҶгҒ—гҒҹзҹҘиҰӢгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒеӨ§и…ёеҶ…иҰ–йҸЎжӨңжҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒӣгҒҡгҖҒжүӢйҒ…гӮҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖдәәдёҖдәәгҒ®жӮЈиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгӮ»гӮ«гғігғүгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғігӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжҷӮгҒ«йҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҜеҮәдјҡгҒЈгҒҹеҢ»её«гҒ«е‘ҪгӮ’й җгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠдёҖдәәдёҖдәәгҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’йҮҚгҒҸеҸ—гҒ‘жӯўгӮҒгҒҰгҖҒжӨңжҹ»жүҖиҰӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжүӢжҺӣгҒӢгӮҠгӮ’иҰӢиҗҪгҒЁгҒ•гҒҡгҖҒдёҒеҜ§гҒ«жӨңиЁјгҒҷгӮӢе§ҝеӢўгӮ’еёёгҒ«жҢҒгҒЎз¶ҡгҒ‘гҒҰеҢ»зҷӮгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢдҪ•гӮҲгӮҠеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһиӮқз”ҹжӨңеҫҢгҒ®д№іе…җгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®гҒҠи©ұPart2
е…Ҳж—ҘгҖҒгҒ“гҒ®ж¬„гҒ«жӣёгҒ„гҒҹгҖҢиӮқз”ҹжӨңеҫҢгҒ®д№іе…җгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®иЈҒеҲӨгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒпј‘пј’жңҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰ第1еӣһеҸЈй ӯејҒи«–жңҹж—ҘгҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒҜдёҚеҮәй ӯгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ第1еӣһгҒ®жңҹж—ҘгҒҜеҺҹе‘ҠеҒҙгҒ®йғҪеҗҲгҒ гҒ‘гҒ§жұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®жңҹж—ҘгҒ®еүҚгҒ«гҖҒиў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒӢгӮүгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®жӣёиЁјгҒҢеұҠгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иҰӢгҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁй©ҡгҒҚгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁе«ҢгҒӘж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”е ұе‘ҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®жӣёиЁјгҒЁгҒҜгҖҒпј“йҖҡгҒ®й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҢжҖҘеӨүзӣҙеҫҢгҒ«ж’®гӮүгӮҢгҒҹXз·ҡз”»еғҸгҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®зөҗи«–гҒҜгҖҒгҖҢеҗҢXз·ҡз”»еғҸдёҠгҒ«еҮәиЎҖгӮ’гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӣгӮӢжүҖиҰӢгҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬д»¶гҒҜгҖҒжӯ»дҪ“жӨңжЎҲжӣёгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢз”ҹеҫҢ11гҒӢжңҲгҒ®д№іе…җгҒ®иӮқиҮ“гҒ«6еҖӢгҒ®з©ҝеҲәз—•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒи…№и…”еҶ…гҒ«дҪ“еҶ…з·ҸиЎҖж¶ІйҮҸгҒ®2еҲҶгҒ®1гӮ’и¶…гҒҲгӮӢ360mlгҒ®иЎҖж¶ІгҒҢиІҜз•ҷгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢиӮқз”ҹжӨңгҒ«иө·еӣ гҒҷгӮӢеҮәиЎҖжӯ»гҖҚгҒЁгҒҫгҒ§ж–ӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәӢжЎҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиЈҒеҲӨгҒ§гҒ“гҒЎгӮүеҒҙгҒҢжҸҗеҮәгҒ—гҒҹй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒд»–гҒ®иӨҮж•°гҒ®еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒӢгӮүгӮӮгҖҒгҖҢжҖҘеӨүзӣҙеҫҢгҒ«ж’®гӮүгӮҢгҒҹеҗҢгҒҳXз·ҡз”»еғҸдёҠгҒ«еҮәиЎҖгӮ’гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӣгӮӢжүҖиҰӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜжҳҺзўәгҒӘж„ҸиҰӢгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиў«е‘ҠеҒҙгҒӢгӮүеұҠгҒ„гҒҹй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзңҹйҖҶгҒ®ж„ҸиҰӢгҒҢиҝ°гҒ№гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒиў«е‘ҠгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиӮқз”ҹжӨңгҒ«гӮҲгӮӢеҮәиЎҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гӮ’дәүзӮ№гҒ«гҒҷгӮӢж„Ҹеҗ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ§гҒқгҒ®зӮ№гӮ’жң¬ж°—гҒ§дәүгҒҶгҒӨгӮӮгӮҠгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁгҖҒжӯЈзӣҙгҖҒдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«ж„•з„¶гҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҒ®дҫқй јгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ®ж„ҸиҰӢжӣёгӮ’пј“дәәгӮӮгҒ®еҢ»её«гҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ§еҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’жүұгҒҶгҒ“гҒЁгҒ®жңҖеӨ§гҒ®йӣЈй–ўгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүеҒҙгҒӢгӮүгҒ®зӣёи«ҮгҒ«д№—гҒЈгҒҰж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгҒӨгҒҰгӮ’й јгҒЈгҒҰгҖҒеҠ©иЁҖгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢеҢ»её«гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§иЎҢгҒ‘гӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒ„гғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйқһеёёгҒ«дёҚеҲ©гҒӘй ҳеҹҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҖҒиӘӨи§ЈгӮ’жҒҗгӮҢгҒҡгҒ«гҒ„гҒҶгҒӘгӮүгҒ°гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ®еҚ”еҠӣеҢ»гҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҢдёӯз«Ӣе…¬жӯЈгҒӘгҖҚж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰдёӢгҒ•гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҒҜгҖҒеёёиӯҳзҡ„гҒӘеҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«жңүеҲ©гҒӘеҶ…е®№гҒ®й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒҢжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚеҗҲзҗҶгҒӘй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҝЎз”ЁжҖ§гӮ’ејҫеҠҫгҒ—гҖҒзңҹе®ҹгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзңҹзӣёз©¶жҳҺгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫзҠ¶гҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒҢдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰжқҘгӮӢгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҮәгҒҰжқҘгҒӘгҒ„гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®иүҜеҝғгҒ«е§”гҒӯгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ§зңҹзӣёгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒІгҒ„гҒҰгҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жёӣгӮүгҒ—гҖҒжӮЈиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҢ»зҷӮгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҢ»зҷӮиҖ…ж–№гҖ…гҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°гҒЁеј·гҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјҲй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҖҒйқһеёёгҒ«й©ҡгҒҸгҒ№гҒҚдҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҲҘгҒ®ж©ҹдјҡгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ“гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®ж¬Ўеӣһжңҹж—ҘгҒҜпј‘жңҲеҫҢеҚҠгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҺҹе‘ҠгҒ§гҒӮгӮӢиҰӘеҫЎгҒ•гӮ“гҒ®ж„ҸиҰӢйҷіиҝ°гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жқңж’°гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ§еӨ§еҲҮгҒӘе№јеӯҗгӮ’дәЎгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹиҰӘеҫЎгҒ•гӮ“гҒ®жғігҒ„гӮ„йЎҳгҒ„гҒҢиЈҒеҲӨжүҖгӮ„иў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒ«еұҠгҒ‘гҒ°гҒЁйЎҳгҒҶгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ