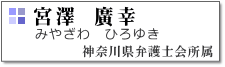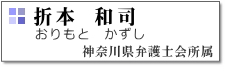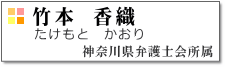дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ§еҝҷж®әгҒ•гӮҢгҒҹе№ҙжң«е№ҙе§ӢгҒ®гҒ“гҒЁ
гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиЁҳдәӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸдҪ•гӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ§гҒҠгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒе№ҙжң«гҖҒгҒқгӮҢгӮӮеӨ§гҒҝгҒқгҒӢгҒ«еҲ‘дәӢдәӢ件гӮ’еҸ—д»»гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
жӯЈзӣҙгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁе®ҝйЎҢгҒҢжәңгҒҫгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе№ҙжң«е№ҙе§ӢгҒ®гҒҠдј‘гҒҝгҒ®й–“гҒ«гҒқгӮҢгӮ’зүҮд»ҳгҒ‘гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®зӣ®и«–иҰӢгҒҜгӮӮгҒ®гҒ®иҰӢдәӢгҒ«еӨ–гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒе№ҙжң«гҒҢиҝ«гӮӢдёӯгҒ§гҖҒе‘ЁгӮҠгҒ®дәәгҒӢгӮүгҖҒгҖҢд»Ҡе№ҙгҒҜгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§еғҚгҒҸгҒ®гҒӢпјҹгҖҚгҒЁе•ҸгӮҸгӮҢгҖҒгҖҢеӨ§гҒҝгҒқгҒӢгҒҫгҒ§гҖҚгҒЁзӯ”гҒҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҢж–°е№ҙгҒҜгҒ„гҒӨгҒӢгӮүеғҚгҒҸгҒ®гҒӢпјҹгҖҚгҒЁиЁҠгҒӢгӮҢгҖҒгҖҢе…ғж—ҰгҒӢгӮүгҖҚгҒЁеҶ—и«ҮгҒ§зӯ”гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮҲгӮӮгӮ„гӮҲгӮӮгӮ„пјҲжңҖиҝ‘гҒ®жөҒиЎҢгӮҠиЁҖи‘үпјүгҒ§гҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒе……е®ҹпјҲпјҒпјҹпјүгҒ—гҒҹе№ҙжң«е№ҙе§ӢгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұгӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒеӨ§гҒҝгҒқгҒӢгҒ«жҺҘиҰӢгҒ«иЎҢгҒҸгҒЁгҖҒдәӢ件гҒ®дёӯиә«гӮӮгҒ•гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ«гҖҒгҒ”жң¬дәәгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гҒ«йҖЈзөЎгӮ’гҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„з·ҠжҖҘгҒ®дәӢжғ…гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒејҒиӯ·дәәгҒ«е°ұд»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘпјҲеӨ§гҒҝгҒқгҒӢпјүгҒ®еҶ…гҒ«гҖҒжң¬дәәгҒ®еёҢжңӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒ家ж—ҸгӮ„й–ўдҝӮиҖ…гҒЁйҖЈзөЎгӮ’еҸ–гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«гҖҒжң¬дәәгҒ«гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁзўәиӘҚгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒҰгҖҒзҝҢж—ҘгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе…ғж—ҰгҒ®гҒҠжҳјй ғгҖҒиӯҰеҜҹгҒ«жҺҘиҰӢгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҜгҖҒжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҖҘгҒҺгҒ§йҖЈзөЎгӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒ®гҒӮгӮӢ件гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҖҒжң¬дәәгҒЁй–ўдҝӮиҖ…гҒ®й–“гҒ§дјқиЁҖдҝӮгӮ’еӢҷгӮҒгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зөҗеұҖгҖҒпј‘йҖұй–“гҒ¶гҒЈйҖҡгҒ—гҒ§иӯҰеҜҹгҒ«жҺҘиҰӢгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеҖӢдәәзҡ„гҒӘйҖЈзөЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҲ‘дәӢејҒиӯ·гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгӮ„гӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәәгӮӮгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеёёгҖ…гҖҒз§ҒгҒҜгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҖғгҒҲж–№гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®иў«з–‘иҖ…гҖҒиў«е‘ҠдәәгҒ«гҒӘгӮӢгҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘иә«жҹ„жӢҳжқҹгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®дёҚеҲ©зӣҠгҒЁгҒҜгҖҒз„Ўе®ҹгҒ®зҪӘгӮ’зқҖгҒӣгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒиө·иЁҙгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒе®ҹеҲ‘гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘз”ұгӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзӨҫдјҡзҡ„гҒӘйқўгҒ§еҸ—гҒ‘гӮӢдёҚеҲ©зӣҠгӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҷӮгҒ«гҒҜгҒқгҒ®дёҚеҲ©зӣҠгҒ®ж–№гҒҢгӮҲгӮҠйҮҚеӨ§гҒӘе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒзӨҫдјҡжӯЈзҫ©гҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдёҚеҲ©зӣҠгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢйҷҗгӮҠеӣһйҒҝгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҪ№зӣ®гҒ гҒЁдҝЎгҒҳгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶз§ҒгҒӘгӮҠгҒ®дҝЎжқЎгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе®ҹйҡӣгҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒй–ўдҝӮиҖ…гҒ«йҖЈзөЎгӮ’гҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжң¬дәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе‘ЁгӮҠгҒ«гӮӮйҮҚеӨ§гҒӘдёҚеҲ©зӣҠгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ гҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжӯЈжңҲдј‘гҒҝгӮ’иҝ”дёҠгҒ—гҒҰгҖҒиӯҰеҜҹйҖҡгҒ„гҒ®жҜҺж—ҘгӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖж–№гҖҒдәӢ件гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе·®ж”ҜгҒҲгҒ®гҒӘгҒ„зҜ„еӣІгҒ§и§ҰгӮҢгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒӘгҒңгҒ“гҒ®д»¶гҒ§иӯҰеҜҹгҒҢйҖ®жҚ•гҒ«иёҸгҒҝеҲҮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒеӨ§гҒ„гҒ«з–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒпј‘жңҲпј”ж—ҘгҒ®еҫЎз”Ёе§ӢгӮҒд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒЁгӮӮдҪ•еәҰгҒӢи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҺҮзӣҙгҒ«иЁҖгҒЈгҒҰгҖҒиӯҰеҜҹгҒ®гҒҠгҒӢгҒ—гҒӘжҚңжҹ»гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгҒ№гҒҚжӨңеҜҹе®ҳгҒ®еҪ№зӣ®гҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸжһңгҒҹгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҒ—гҖҒиӯҰеҜҹгҒҢгҖҒиў«з–‘иҖ…гӮ’ж¬әгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘеҸ–гӮҠиӘҝгҒ№жүӢжі•гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’и««гӮҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе§ҝеӢўгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҡгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӨұжңӣгӮ’зҰҒгҒҳеҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгӮӮгҖҒеӢҫз•ҷ延長и«ӢжұӮгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүж„ҸиҰӢжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢйҖғдәЎгҒ®жҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ—гҒҰпј–ж—Ҙй–“гҒ®еӢҫз•ҷ延長гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҲӨж–ӯгӮӮгҒІгҒ©гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӢҫз•ҷ延長гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжә–жҠ—е‘ҠгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеӢҫз•ҷ延長гҒҜеҸ–гӮҠж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲи©ізҙ°гҒҜзңҒгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиў«з–‘иҖ…гҒҢйҖғдәЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©зө¶еҜҫгҒ«гҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ гҒЈгҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеӢҫз•ҷ延長гҒ®зҗҶз”ұгҒ®дёҖгҒӨгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖӮ
еӣҪеӨ–йҖғдәЎгҒ—гҒҹгӮ«гғ«гғӯгӮ№гғ»гӮҙгғјгғігҒ®иӮ©гӮ’жҢҒгҒӨиҖғгҒҲгҒҜгҒ•гӮүгҒ•гӮүгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ‘дәӢжүӢз¶ҡгҒ®е®ҹеӢҷгҒ«гҒҜгҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸгҖҢдәәиіӘеҸёжі•гҖҚгҒЁйқһйӣЈгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮд»•ж–№гҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘе®ҹж…ӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒд»ҠеӣһгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜеӢҫз•ҷ延長гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҺгӮҠгҒҺгӮҠеӢқиІ гҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒ§гҒҜгҖҒж—©жңҹгҒ«йҮҲж”ҫгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«е…Ёйқўзҡ„гҒ«йқһгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢдҫӣиҝ°гӮ’гҒ—гҒҹж–№гҒҢгҖҒгғҲгғјгӮҝгғ«гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜиў«з–‘иҖ…гҒ®еҲ©зӣҠгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒҢдҪ•еәҰгӮӮй ӯгӮ’жҺ гӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҲ‘дәӢеҸёжі•гҒ®зҸҫе®ҹгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„дәәгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“иҮӘзҷҪгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨгҒ§з„ЎзҪӘгӮ’дәүгҒҶиў«е‘ҠдәәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒз„Ўе®ҹгҒӘгӮүиҮӘзҷҪгҒ—гҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«йҖ®жҚ•гҖҒеӢҫз•ҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘеҚҳзҙ”гҒӘи©ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жӨңеҜҹе®ҳгҒҢиӯҰеҜҹгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғҒгӮ§гғғгӮҜж©ҹиғҪгӮ’жҖ гӮҠгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒе®үжҳ“гҒ«еӢҫз•ҷгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫе®ҹгҒҢж”№гӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж–№зӯ–гҒҢжҺЎгӮүгӮҢгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒгҖҢдәәиіӘеҸёжі•гҖҚгҒЁйқһйӣЈгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгҒ®жӯӘгӮ“гҒ еҲ‘дәӢеҸёжі•гҒ®еҒҘе…ЁеҢ–гҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁз—ӣж„ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиҖғгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҖҒиӯҰеҜҹйҖҡгҒ„гӮ’йҮҚгҒӯгҒҹе№ҙжң«е№ҙе§ӢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒд»ҠгӮӮгҖҒгҒқгҒ®еҫҢйҒәз—ҮгҒ§дј‘ж—Ҙиҝ”дёҠгҒ§д»•дәӢгҒ«иҝҪгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҡҶж§ҳгӮӮгҖҒгӮігғӯгғҠгҒ§еӨ§еӨүгҒӘзҠ¶жіҒгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҸгӮҢгҒҗгӮҢгӮӮгҒ”иҮӘж„ӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеҠҙзҒҪгҒ®еҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ§дёҚж”ҜзөҰеҮҰеҲҶгҒҢеҸ–гӮҠж¶ҲгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҒ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷеҠҙзҒҪгҒ®еҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ§гҖҒдёҚж”ҜзөҰеҮҰеҲҶгҒҢеҸ–гӮҠж¶ҲгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”е ұе‘ҠгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒдәӢ件гҒ®жҰӮиҰҒгӮ’гҒ”иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢгғҠгӮӨгғҲгӮҜгғ©гғ–гҒ§иө·гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҫ“жҘӯе“ЎгҒ§гҒӮгӮӢжқұеҚ—гӮўгӮёгӮўзі»гҒ®еӨ–еӣҪдәәеҘіжҖ§гҒҜгҖҒеҗҢеғҡгҒ®еҘіжҖ§гҒҢжҺҘе®ўдёӯгҒ«еёёйҖЈе®ўгҒ®з”·жҖ§гҒӢгӮүзөЎгҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒеҠ©гҒ‘гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеёёйҖЈе®ўгӮ’жӯўгӮҒгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жҖ’гҒЈгҒҹеёёйҖЈе®ўгҒҢеҘіжҖ§еҫ“жҘӯе“ЎгӮ’гӮҪгғ•гӮЎгғјгҒ§жҠјгҒ—еҖ’гҒ—гҖҒеҪјеҘігҒ®и¶ій–ўзҜҖгӮ’жҖқгҒ„еҲҮгӮҠгҒӯгҒҳгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеҘіжҖ§еҫ“жҘӯе“ЎгҒҜиҶқгҒ®еүҚеҚҒеӯ—йқӯеёҜгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢжүӢиЎ“гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒпј‘е№ҙеҚҠд»ҘдёҠзөҢгҒЈгҒҹд»ҠгӮӮжҷ®йҖҡгҒ«жӯ©гҒҸгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дәӢ件гҒҜгҖҒеҠҙзҒҪдәӢж•…гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж°‘дәӢгҒ®жҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮдәӢ件гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҪ“еҲқгҖҒзӨәи«ҮдәӨжёүдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰеҸ—д»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж°‘дәӢгҒ®жҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮгҒҜгҖҒеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүеҠ е®іиҖ…гҒ®з”·жҖ§гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгӮҲгӮӮгӮ„еҠҙзҒҪгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁзӯүгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҠҙзҒҪгҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒдёҚж”ҜзөҰжұәе®ҡгҒҢеҮәгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зҗҶз”ұгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜй©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҢиҮӘжӢӣиЎҢзӮәгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҘӯеӢҷдёҠзҒҪе®ігҒЁи©•дҫЎгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гҒ гҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжҖӘжҲ‘гҒҜиҮӘгӮүжӢӣгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§жҘӯеӢҷгҒ«иө·еӣ гҒӣгҒҡеҠҙзҒҪгҒ«гҒҜгҒӮгҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯгҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеҠҙеҹәзҪІгҒ®иӘҝжҹ»гҒ§гҒҜгҖҒеёёйҖЈе®ўгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиў«е®іиҖ…гҒ«еҠ©гҒ‘гӮ’жұӮгӮҒгҒҹеҘіжҖ§еҫ“жҘӯе“ЎгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еёёйҖЈе®ўгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ«жІҝгҒҶдҫӣиҝ°гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®еҲӨж–ӯгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дёҚеҗҲзҗҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮзҸҫе ҙгҒ§гҒқгҒ®е ҙйқўгӮ’зӣ®ж’ғгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәәзү©гҒҢдҪ•дәәгӮӮгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҠҙеҹәзҪІгҒ®жӢ…еҪ“е®ҳгҒҜгҒқгӮҢгӮүгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒӢгӮүе…ЁгҒҸдәӢжғ…гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҠ е®іиҖ…гҒҢзңҹе®ҹгӮ’и©ұгҒҷгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дәәзү©гҒҜеёёйҖЈе®ўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ«жІҝгҒҶдҫӣиҝ°гӮ’гҒ—гҒҹеҘіжҖ§гҒҜеә—гҒ®еҫ“жҘӯе“ЎгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеә—еҒҙгҒ«жҢҮзӨәгҒ•гӮҢгҒҰиҷҡеҒҪгҒ®иЁјиЁҖгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«гҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒеҠҙеҹәзҪІгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ«еұ…еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹиӨҮж•°гҒ®зӣ®ж’ғиҖ…гҒ®и©ұгӮ’иҒһгҒ“гҒҶгҒЁгӮӮгҒӣгҒҡгҖҒеҠ е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ’йөңе‘‘гҒҝгҒ«гҒ—гҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®дё»ејөгӮ’иҷҡеҒҪгҒ гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжұәе®ҡзҡ„гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҠ е®іиҖ…гҒҜгҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®жҖӘжҲ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ«зӘҒгҒЈгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰжқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжҢҜгӮҠжү•гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒи¶ігӮ’гҒІгҒӯгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖгҒ„еҲҶгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиў«е®іиҖ…гҒҢиІ гҒЈгҒҹиҶқгҒ®еүҚеҚҒеӯ—йқӯеёҜгҒ®жҗҚеӮ·гҒҜжҢҜгӮҠжү•гӮҸгӮҢгҒҰи¶ігӮ’жҚ»гҒЈгҒҹзЁӢеәҰгҒ§з”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁзӯүзө¶еҜҫгҒ«гҒӮгӮҠеҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®дёҖзӮ№гҒ®гҒҝгҒ§гҖҒеҠ е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒҢеҳҳгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒзӣ®ж’ғиҖ…гҒ®иЁјиЁҖгҒ®йҢІйҹігҖҒйҢІз”»гӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҖҒеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ“гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ§еҲӨж–ӯгҒҜиҰҶгӮӢгҒЁжҘҪиҰіиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒжҘӯеӢҷдёӯгҒ®з¬¬дёүиҖ…гҒ«гӮҲгӮӢиІ еӮ·гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷиө·еӣ жҖ§гӮ’жҺЁе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҖҡйҒ”гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒиӨҮж•°гҒ®зӣ®ж’ғиҖ…гҒҢгҒҠгӮҠгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„и©•дҫЎгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгӮӮиҮӘжӢӣиЎҢзӮәгҒ®иӘҚе®ҡгҒҜз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиёҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ®зөҗжһңгҒҜеүҚгҒЁеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
жӯЈзӣҙгҖҒ愕然гҒЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒдҫқй јиҖ…гҒ®иҗҪиғҶгҒҜйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгӮ’иЎҢгҒҶгҒӢгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮӢгҒӢгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢжЎҲгҒ®еҶ…е®№гҒӢгӮүгҒ—гҒҰгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒҫгҒҡй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸеҲӨж–ӯгҒҜиҰҶгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзўәдҝЎгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиЁҙиЁҹгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒзӣёжүӢгҒҜеӣҪгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒзӣёеҪ“гҒӘеҠҙеҠӣгҒЁжҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®№жҳ“гҒ«жғіеғҸгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дёҖж–№гҖҒеҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒҜгҖҒж—©жңҹгҒ«еҲӨж–ӯгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзөҗжһңгҒҢиҰҶгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜиЈҒеҲӨгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁдҪҺгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгӮӮгҒ—гҖҒеҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ§еҲӨж–ӯгҒҢиҰҶгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүиЁҙиЁҹгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒдәҢеәҰжүӢй–“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиҝ·гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдҫқй јиҖ…гҒЁгӮӮзӣёи«ҮгҒ—гҖҒзөҗеұҖеҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ®жүӢз¶ҡгҒ§гҒҜгҖҒжҢҮзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®жӣёйқўгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«еёҢжңӣгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°еҠҙеғҚдҝқйҷәеҜ©жҹ»дјҡгҒ«еҮәй ӯгҒ—гҒҰиіӘз–‘гҒ«еҝңгҒҳгҒҹгӮҠеҸЈй ӯгҒ§ж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гҖҒгӮігғӯгғҠгҒ®еҪұйҹҝгҒҢжӢЎеӨ§гҒ—е§ӢгӮҒгҒҹжҷӮжңҹгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҜ©жҹ»дјҡгҒҜй–ӢгҒӢгӮҢгҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§еҜ©жҹ»е“ЎгҒ®ж–№гҖ…гҒЁеҜҫйқўгҒ§гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҜ©жҹ»дјҡгҒ®жүӢз¶ҡгҒҜгҖҒгӮҸгӮҠгҒЁгҒӮгҒЈгҒ•гӮҠзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜеҜ©жҹ»е“ЎгҒӢгӮүгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁе°ӢгҒӯгӮүгӮҢгҖҒгҒҫгҒҹиҝҪеҠ иіҮж–ҷгҒ®жҸҗеҮәгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеҜ©жҹ»дјҡгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ®жүӢеҝңгҒҲгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒҢжӢЎеӨ§гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеӨҸеүҚгҒ«гҒҜеҮәгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹзөҗи«–гҒҜгҖҒз§ӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮеұҠгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дҫқй јиҖ…гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒҶгҒЁгҖҒгҒҳгӮҠгҒҳгӮҠгҒ—гҒҹж—ҘгҖ…гҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒпј‘пјҗжңҲеҫҢеҚҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁеҗүе ұгҒҢеұҠгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҺҹеҮҰеҲҶгӮ’еҸ–гӮҠж¶ҲгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶеҶ…е®№гҒ§гҖҒе¬үгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒдёҖеұұи¶…гҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғӣгғғгҒЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжӯЈзӣҙгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢ件гҒҜгҒҫгҒ з¶ҡгҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ®зөҢз·ҜгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гӮӢгҒЁгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒеҠҙеҹәзҪІгҒ®еҲӨж–ӯгҒЁеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒҠгӮҲгҒқгғ—гғӯгҒ®д»•дәӢгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒйқһеёёгҒ«и…№з«ӢгҒҹгҒ—гҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒ®е ҙеҗҲгҖҒдәӢе®ҹгӮ’иҮӘ然гҒ«гҒЁгӮүгҒҲгҒҰе®ўиҰізҡ„гҒ«иЁјжӢ гӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҠ е®іиҖ…еҒҙгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒҜзӯӢгҒҢйҖҡгӮүгҒҡгҖҒиҷҡеҒҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдёҖзӣ®зһӯ然гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дёӯгҒ§гӮӮжұәе®ҡзҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеүҚиҝ°гҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҖҒжҢҜгӮҠжү•гӮҸгӮҢгҒҰгҖҒи¶ігӮ’жҚ»гҒЈгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒиҶқгҒ®еүҚеҚҒеӯ—йқӯеёҜгӮ’жҗҚеӮ·гҒҷгӮӢгҒҜгҒҡзӯүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘдёҚеҗҲзҗҶгҒ•гҒҜгҖҒжүӢиЎ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹеҢ»её«гҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮҢгҒ°гҒҷгҒҗгҒ«гӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒиӘҝжҹ»гҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҹжӢ…еҪ“иҖ…гӮүгҒҜеҢ»её«гҒёгҒ®иҒһгҒҚеҸ–гӮҠгҒҷгӮүиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҺҹеҮҰеҲҶгҒ§гҒҜеҠ е®іиҖ…гҒ®дҫӣиҝ°гҒ«жІҝгҒҶиЁјиЁҖгӮ’гҒ—гҒҹеҘіжҖ§еҫ“жҘӯе“ЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢеҳҳгӮ’гҒӨгҒҸзҗҶз”ұгҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒқгҒ®иЁјиЁҖгҒҜдҝЎз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиӘҚе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеёёйҖЈе®ўгӮ’гҒӢгҒ°гҒҠгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеә—еҒҙгҒҢеҫ“жҘӯе“ЎгҒ«иҷҡеҒҪгҒ®иЁјиЁҖгӮ’гҒ•гҒӣгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’жҙһеҜҹгҒҷгӮӢжғіеғҸеҠӣгҒҷгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҒЁиЁҖгҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒиӘҝжҹ»гҒ®йҒҺзЁӢгҒ§гҖҒиӨҮж•°гҒ„гҒҹзӣ®ж’ғиҖ…гҒӢгӮүгӮӮгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒҠгӮҲгҒқдҝЎгҒҳйӣЈгҒ„жүӢжҠңгҒҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжң¬д»¶гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеүҚиҝ°гҒ—гҒҹйҖҡйҒ”гӮӮгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’з„ЎиҰ–гҒҷгӮӢгҒҢгҒ”гҒЁгҒҸдёҚеҲ©зӣҠгҒӘиӘҚе®ҡгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒӘгҒҠгҒ•гӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒІгҒ©гҒ„гҒЁгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүеҠҙеҹәзҪІгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз«ҜгҒӢгӮүеҠҙзҒҪгҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘еҝөгҒ•гҒҲ湧гҒ„гҒҰгҒҸгӮӢгҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨжҖқгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚеҪ“гҒӘеҮҰеҲҶгҒҢеҮәгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгӮ’иҰҶгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®иў«е®іиҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒҜгҒӘгӮ“гҒЁгҒӢеҶҚеҜ©жҹ»и«ӢжұӮгҒ§еҲӨж–ӯгӮ’гҒІгҒЈгҒҸгӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҠҙзҒҪгҒ«йҒӯгҒЈгҒҹиў«е®іиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ®жүӢй–“жҡҮгӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜеӨ§еӨүгҒӘиІ жӢ…гҒ§гҒҷгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮӮејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҠ©еҠӣгҒӘгҒ—гҒ§гҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӣ°йӣЈгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеӨ–еӣҪдәәеҠҙеғҚиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜиЁҖи‘үгҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒ«еӨ§еӨүгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒеҠҙзҒҪгҒЁгҒ—гҒҰжЁ©еҲ©ж•‘жёҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚдәӢжЎҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдёҚж”ҜзөҰгҒ®еҮҰеҲҶгҒҢеҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒжіЈгҒҚеҜқе…ҘгӮҠгҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹдәәгҒҢеӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҠҙзҒҪгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ«ж°‘дәӢиі е„ҹгӮ’жҺ§гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®е ҙйқўгҒ§жқңж’°гҒӘдёҚеҲ©зӣҠиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒж°‘дәӢиі е„ҹгҒ«гӮӮйҮҚеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгҒҢеҸҠгҒігҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дёҚеҲ©зӣҠгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠҙзҒҪгҒҜгҖҒеҲӨдҫӢгҒ®и“„з©ҚгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁиӘҚе®ҡеҹәжә–гҒҜеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®иӘҚе®ҡгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжҒЈж„Ҹзҡ„гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢдёҚеҗҲзҗҶгҒӢгҒӨдёҚеҲ©зӣҠгҒӘеҲӨж–ӯгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдәӢж•…гҒ«йҒӯгӮҸгӮҢгҒҰгҖҒеҠҙзҒҪгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“дёҚж”ҜзөҰгҒ®еҮҰеҲҶгҒҢеҮәгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮзҙҚеҫ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒи«ҰгӮҒгҒҡгҖҒгҒҠдҪҸгҒ„гҒ®ең°еҹҹгҒ§еҠҙзҒҪгҒҢжүұгҒҲгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгӮҲгҒҶгҒҠеӢ§гӮҒгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҖҢдҝқдҪҗгҖҚгҒ®еӢ§гӮҒ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ®иІЎз”ЈгӮ„иҖҒеҫҢгҒ®з”ҹжҙ»гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжҲҗе№ҙеҫҢиҰӢгҒ®еҲ©з”ЁгҒҢе®ҡзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй–ўйҖЈгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢдҝқдҪҗгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжүӢз¶ҡгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е№ігҒҹгҒҸгҒ„гҒҲгҒ°еҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒ®йҒ•гҒ„гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҙ°гҒӢгҒҸиҰӢгҒҰиЎҢгҒҸгҒЁеҫҢиҰӢгҒЁгҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҰҒ件гҒ•гҒҲжәҖгҒҹгҒҷгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢдҝқдҪҗгҖҚгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰзҸҚгҒ—гҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҫҢиҰӢгҒЁгҒ®з•°еҗҢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒӨгҒӨгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒ«дҝқдҪҗгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡеҫҢиҰӢгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҫҢиҰӢгҒҜиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢзІҫзҘһдёҠгҒ®йҡңе®ігҒ«гӮҲгӮҠеҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒҢж¬ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮгҒ«д»ҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒдҝқдҪҗгҒҜгҖҢзІҫзҘһдёҠгҒ®йҡңе®ігҒ«гӮҲгӮҠдәӢзҗҶејҒиӯҳиғҪеҠӣгҒҢи‘—гҒ—гҒҸдёҚеҚҒеҲҶгҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮгҒ«д»ҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёЎиҖ…гҒ®й–“гҒ«гҒҜеҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§жҳҺзҷҪгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҫҢиҰӢдәәгҒҢйҒёд»»гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжң¬дәәпјқеҫҢиҰӢдәәгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеҘ‘зҙ„гҒӘгҒ©гҒ®жі•еҫӢиЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе…Ёйқўзҡ„гҒӘд»ЈзҗҶжЁ©гӮ’жҢҒгҒӨеҫҢиҰӢдәәгҒ«гҒ—гҒӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дёҖж–№гҖҒдҝқдҪҗгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдҝқдҪҗдәәгҒҜгҖҒйҒёд»»гҒ®йҡӣгҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҖҢйҮҚиҰҒгҒӘжі•еҫӢиЎҢзӮәгҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҗҢж„ҸжЁ©гӮ„дёҖе®ҡгҒ®жүӢз¶ҡгӮ’иёҸгӮ“гҒ дёҠгҒ§гҒ®д»ЈзҗҶжЁ©гӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҒёд»»жүӢз¶ҡгҒ®й–ўдҝӮгҒ§гҒҜгҖҒеҫҢиҰӢгҒ®е ҙеҗҲгҒЁз•°гҒӘгӮҠгҖҒжң¬дәәгҒ«дёҖе®ҡгҒ®еҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжң¬дәәгҒ®ж„ҸжҖқзўәиӘҚгҒ®жүӢз¶ҡгҒҢеҸ–гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дҝқдҪҗдәәгҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®дҝқдҪҗдәәгҒ®гӮ„гӮӢгҒ№гҒҚд»•дәӢгҒҜгҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜеҫҢиҰӢгҒЁгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е№ҙгҒ«пј‘еәҰгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒёгҒ®е ұе‘ҠгӮ„гҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®еҮҰеҲҶгӮ„йҒәз”Јзӣёз¶ҡгҒ®жүӢз¶ҡзӯүгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеұҖйқўгҒ§гҒ®еҜҫеҝңгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰйҒ•гҒ„гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒдҝқдҪҗеҲ©з”ЁгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҒ©гҒ“гҒ«гҒӮгӮӢгҒӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖгҒӨгҒҜеҸ–ж¶ҲжЁ©гҒ§гҒҷгҖӮ
дҝқдҪҗдәәгҒҜгҖҒжң¬дәәгҒҢеҚҳзӢ¬гҒ§гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°йЁҷгҒ•гӮҢгҒҰдёҚеӢ•з”ЈгӮ’еҮҰеҲҶгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®дёҚеҲ©зӣҠгҒӘеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҖҒи©җж¬әгӮ„и„…иҝ«гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮ’гҒ„гҒЎгҒ„гҒЎе•ҸйЎҢгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҒқгҒ®еҘ‘зҙ„гӮ’еҸ–гӮҠж¶ҲгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒдҝқдҪҗгҒҜгҖҒжң¬дәәгҒ®иІЎз”ЈгӮ’дҝқе…ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӮҷгҒҲгҒЁгҒ—гҒҰйқһеёёгҒ«жңүз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…гҒ®ж–№гҒЁгҒҠи©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгҒҜжҷ®йҖҡгҒ«гҒ§гҒҚгҒҰгӮӮгҖҒиҝ‘гҒ„жҷӮжңҹгҒ®гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳжҶ¶гҒҢжӣ–жҳ§гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘйғЁеҲҶгҒ®еҲӨж–ӯгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒж··д№ұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе ҙйқўгҒ«гҒ—гҒ°гҒ—гҒ°еҮәгҒҸгӮҸгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹж–№гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҗҚеҫ—гӮ„йҒ©еҗҰгҒ®еҲӨж–ӯгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әгӮ„и©җж¬әзҡ„е•Ҷжі•гҒҢжЁӘиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әе•Ҷжі•гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®зҠҜзҪӘгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹдәәй–“гҒҜгҖҒжң«з«ҜгҒ®дәәй–“гҒ§гӮӮеҺізҪ°гҒ«еҮҰгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҲ¶еәҰж”№йқ©гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гӮӮгҒӢгҒҸгҒ«гӮӮй«ҳйҪўиҖ…гҒҢиў«е®ігҒ«йҒӯгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жңҖгӮӮзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘеӮҷгҒҲгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢдҝқдҪҗгҖҚгҒҜжңүеҠ№гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒе°‘гҒ—еұҖйқўгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҝқдҪҗгҒЁеҫҢиҰӢгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒжң¬дәәгҒҢдёҖе®ҡгҒ®иІЎз”ЈгӮ’дҝқжңүгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҰгҖҒзӣёз¶ҡзЁҺеҜҫзӯ–гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҒәиЁҖгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒ§гҒҷгҖӮ
еҫҢиҰӢдәәгҒҢйҒёд»»гҒ•гӮҢгҒҰд»ҘйҷҚгҒ гҒЁгҖҒзӣёз¶ҡзЁҺеҜҫзӯ–гҒ§гҒ®иҙҲдёҺгҒӘгҒ©гҒ®жі•еҫӢиЎҢзӮәгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒйҒәиЁҖдҪңжҲҗгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҝқдҪҗгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©•дҫЎпјҲе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜеҢ»её«гҒ®ж„ҸиҰӢпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒ§гҒҠи©ұгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒ”жң¬дәәгӮ„иҰӘж—ҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫҢиҰӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдҝқдҪҗгӮ’йҒёжҠһиӮўгҒ«еҠ гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢдҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»ҠгӮ„ж—Ҙжң¬гҒҜи¶…й«ҳйҪўеҢ–зӨҫдјҡгӮ’иҝҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒиІЎз”Јдҝқе…ЁгӮ„гҒ„гҒҡгӮҢжқҘгӮӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶзӣёз¶ҡгҒёгҒ®еӮҷгҒҲгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҰізӮ№гҒӢгӮүгҖҒеҫҢиҰӢгҒ®еүҚж®өйҡҺгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҖҢдҝқдҪҗгҖҚгҒ®еҲ©з”ЁгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢж„Ҹе‘ігҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒңгҒІгҒ”жӨңиЁҺгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒЁгҖҢеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҖҚ
зөҰдёҺжүҖеҫ—иҖ…гӮ„еҖӢдәәдәӢжҘӯиҖ…гҒ®ж–№гҒҢеӨҡйЎҚгҒ®иІ еӮөгӮ’жҠұгҒҲгҖҒеӮөеӢҷж•ҙзҗҶгҒ®зӣёи«ҮгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰжі•зҡ„гҒӘж•ҙзҗҶгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жүӢз¶ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜз ҙз”ЈгҒӢеҖӢдәәеҶҚз”ҹгҒ®дёЎж–№гҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеүҚгҒ«гӮӮгҒ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢйҷҗгӮҠеҖӢдәәеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ§гҒ®жі•зҡ„ж•ҙзҗҶгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҖӢдәәеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүдёҖе®ҡгҒ®иҰҒ件гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҰҒ件гҒ«гҒӮгҒҰгҒҜгҒҫгӮүгҒҡгҖҒз”із«ӢиҮӘдҪ“гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҸгғјгғүгғ«гҒҢй«ҳгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒдҫқй јиҖ…гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҒқгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҖҒеҶҚз”ҹиЁҲз”»иӘҚеҸҜгҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиҮӘе®…гӮ’еҮҰеҲҶгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§жёҲгӮҖгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ©гҒҠгӮҠдәӢжҘӯгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒзҜүгҒҚдёҠгҒ’гҒҹз”ҹжҙ»еҹәзӣӨгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®жәҖи¶іеәҰгҒҜйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„гӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ®е®ҹдҪ“зөҢжёҲгҖҒеӣҪж°‘з”ҹжҙ»гҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҜйқһеёёгҒ«йҮҚеӨ§гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҖӢдәәеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠеҚұж©ҹгҒ®еҪұйҹҝгҒҜж§ҳгҖ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫзҠ¶гҒ§гҒ®жҖҘгҒӘеҸҺе…Ҙжёӣе°‘гҒҜгҖҒдҪҸе®…гғӯгғјгғігҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгҒ®гғӯгғјгғігҖҒдәӢжҘӯгҒ®йҒӢи»ўиіҮйҮ‘гҖҒеӯҗдҫӣгҒ®еӯҰиІ»гҒӘгҒ©гҒ®йҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж”ҜеҮәгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲиҝ”жёҲгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҢгҒ°гҖҒеӮөеӢҷж•ҙзҗҶгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒзөҢйЁ“зҡ„гҒ«з”ігҒ—дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒгӮӮгҒҶе°‘гҒ—ж—©гҒ„ж®өйҡҺгҒ§зӣёи«ҮгҒ«жқҘгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°еҲҘгҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еүҚиҝ°гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒжҠұгҒҲгҒҹеӮөеӢҷгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжі•зҡ„ж•ҙзҗҶгҒ®ж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰз ҙз”ЈгҒЁеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз ҙз”ЈгҒЁз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеүҚиҝ°гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгӮ’ж®ӢгҒ—гҖҒе•ҶеЈІгӮӮз¶ҡгҒ‘гҒҰиЎҢгҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ«гӮӮиҰҒ件гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢеҫ®еҰҷгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҖҒеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡеүҚжҸҗгҒ§ејҒиӯ·еЈ«гҒҢд»Ӣе…ҘгҒ—гҖҒз”ҹжҙ»гӮ’з«ӢгҒҰзӣҙгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҶҚз”ҹгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«жә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгӮұгғјгӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜеҚҒеҲҶеҸҜиғҪгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒејҒиӯ·еЈ«д»Ӣе…ҘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӮөжЁ©иҖ…гҒёгҒ®иҝ”жёҲгӮ’гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“жӯўгӮҒгҖҒеҪ“йқўгҒ®зөҢжёҲзҡ„гҒӘдҪҷеҠӣгӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒгҒ”иҮӘиә«гҒ®еҸҺе…Ҙеў—гҒ«жіЁеҠӣгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ—гҒ°гӮүгҒҸз¶ҡгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ®жңҖйҮҚиҰҒиҰҒ件гҒ§гҒӮгӮӢе°ҶжқҘгҒ®е®үе®ҡгҒ—гҒҹеҸҺе…ҘгҒ®иҰӢиҫјгҒҝгӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶе®ҹзёҫгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰиЎҢгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиҰҒ件гӮҜгғӘгӮўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиҮӘе®…гҒ®дёҚеӢ•з”ЈгӮ’дҝқжңүгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰдҪҸе®…гғӯгғјгғігҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҜз¶ҡгҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒж»һзҙҚгҒҢз¶ҡгҒҸгҒЁд»ЈдҪҚејҒжёҲгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҪҸе®…гғӯгғјгғізү№еҲҘжқЎй …гҒ®йҒ©з”ЁгҒҢеҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйқһеёёгҒ«йӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгӮ’жүӢж”ҫгҒ•гҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒд»ЈдҪҚејҒжёҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеүҚгҒ«гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒҢд»Ӣе…ҘгҒ—гҒҰд»–гҒ®иІ еӮөгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’жӯўгӮҒгҖҒдҪҸе®…гғӯгғјгғігҒ гҒ‘гҒҜе„Әе…Ҳзҡ„гҒ«ж”Ҝжү•гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҖҒгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰж—©жңҹгҒ«дҪҸе®…гғӯгғјгғігҒ®еӮөжЁ©иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢйҮ‘иһҚж©ҹй–ўгҒЁгҒ®и©ұгҒ—еҗҲгҒ„гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжё…з®—дҫЎеҖӨгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ·гғјгғҲгҒ§иіҮз”Ји©•дҫЎгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹзөҗжһңгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдҪҸе®…гғӯгғјгғід»ҘеӨ–гҒ®дёҖиҲ¬еӮөеӢҷгҒҜпј•еҲҶгҒ®пј‘зЁӢеәҰгҒ«ең§зё®гҒ•гӮҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’пј“е№ҙгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜпј•е№ҙгҒ®еҲҶеүІжү•гҒ„гҒ§иҝ”жёҲгҒҷгӮҢгҒ°и¶ігӮҠгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®жүӢз¶ҡгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҠиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҰҒ件гҒ®еҲ¶зҙ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’йҖёгҒ—гҒҰзөҢжёҲзҠ¶жіҒгҒҢеҺігҒ—гҒҸгҒӘгӮҢгҒ°гҖҒжҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®еҶҚз”ҹгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»зўәдҝқгҒҢдёҚеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒжң¬еҪ“гҒ«еҲҮзҫҪи©°гҒҫгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮеүҚгҒ«гҖҒж—©гӮҒж—©гӮҒгҒ«еҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢиҰӢиҫјгҒҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жӨңиЁҺгӮ’й–Ӣе§ӢгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжүӢз¶ҡиІ»з”ЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒҢз”із«Ӣд»ЈзҗҶдәәгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒЁгҒ§гҒҜиЈҒеҲӨжүҖгҒ«зҙҚгӮҒгӮӢдәҲзҙҚйҮ‘гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҢе°‘гҒ—йҒ•гҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒз”із«Ӣд»ЈзҗҶдәәгҒ§гҒӮгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҖӢдәәеҶҚз”ҹ委員гҒ®д»•дәӢгҒ®дёҖйғЁгӮ’иІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҲҶдәҲзҙҚйҮ‘гӮ’дҪҺгҒҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁејҒиӯ·еЈ«иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲҶеүІгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢејҒиӯ·еЈ«гӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеҶҚз”ҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒҜеүҚиҝ°гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«гғ«гҒӘиҰҒзҙ гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒжүӢеүҚе‘іеҷҢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҒӮгӮӢеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӢҫз•ҷи«ӢжұӮеҚҙдёӢжұәе®ҡ
гҒқгӮҢгҒҫгҒ§е№із©ҸгҒӘж—ҘгҖ…гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«гҖҒгҒӮгӮӢж—ҘзӘҒ然еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®иў«з–‘иҖ…гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҖҒиӘ°гҒ«гҒ§гӮӮиө·гҒҚеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒӘгӮ“гҒҰеӣ жһңгҒӘе•ҶеЈІгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒӨгҒҸгҒҘгҒҸгҒқгҒҶжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒжңҖиҝ‘еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҹгҒӮгӮӢеҲ‘дәӢдәӢ件гҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢ件гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӯЈзӣҙгҒӘгҒңгҒ“гӮҢгҒҢеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒиә«жҹ„жӢҳжқҹгҒ«гҒҫгҒ§иҮігҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮз–‘е•ҸгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒжҚңжҹ»гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҚңжҹ»ж©ҹй–ўгҒ®жүӢжі•гҒ«гӮӮйқһеёёгҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒеҠӘеҠӣгҒ®з”Іж–җгҒӮгҒЈгҒҰеӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒҢеҚҙдёӢгҒ•гӮҢгҖҒиў«з–‘иҖ…гҒҜж—©жңҹгҒ«иҮӘз”ұгҒ®иә«гҒЁгҒӘгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҷӮй–“зҡ„еҲ¶зҙ„гӮӮгҒӮгӮӢдёӯгҒ§гҒ®ејҒиӯ·жҙ»еӢ•гҒҜйқһеёёгҒ«йӣЈе„ҖгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжҚңжҹ»гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«иӯҰйҗҳгӮ’йіҙгӮүгҒҷж„Ҹе‘ігӮӮеҗ«гӮҒгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒҜгҖҒз”·еҘій–“гҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§иө·гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘иҰӘгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҘіжҖ§гҒӢгӮүгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠиҮӘе®…гҒ«е‘јгҒігҒӨгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮҠгҖҒиў«з–‘иҖ…гҒЁгҒӘгӮӢз”·жҖ§гҒҢеҘіжҖ§гҒ®иҮӘе®…гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜеҸҢж–№гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒҢйЈҹгҒ„йҒ•гҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“з«ҜжҠҳгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз”·еҘігҒҜеҸЈи«–гҒӢгӮүгӮӮгҒҝеҗҲгҒ„гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒз”·жҖ§гҒҢеҘіжҖ§гҒ®йҰ–гӮ’зөһгӮҒгҒҰгҒ‘гҒҢгӮ’гҒ•гҒӣгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з”·жҖ§гҒҜеҫҢж—ҘиҮӘе®…гӮ’иЁӘгӮҢгҒҹиӯҰеҜҹе®ҳгҒ«гӮҲгӮҠеӮ·е®ізҪӘгҒ§гҒ„гҒҚгҒӘгӮҠйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®ж—ҘгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«йҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮҠгҖҒжҺҘиҰӢгҒ«иЎҢгҒҚгҖҒз”·жҖ§гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”·жҖ§гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеҘіжҖ§е®…гҒ«е‘јгҒігҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰиҮӘе®…гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒй…”гҒЈгҒұгӮүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҘіжҖ§гҒ«зөЎгҒҫгӮҢгҖҒиҲҲеҘ®гҒ—гҒҹеҘіжҖ§гҒҢе№іжүӢгҒ§жҡҙеҠӣгӮ’жҢҜгӮӢгҒЈгҒҰжқҘгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүеҘіжҖ§гҒҢд»ҠеәҰгҒҜжүӢжӢігҒ§ж®ҙгӮҠжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰжқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«гҒқгӮҢгӮ’еҲ¶жӯўгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰдҪ“гӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҘіжҖ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«иҲҲеҘ®гҒ—гҖҒи¶ігҒ§и№ҙгӮҠгҒӨгҒ‘гӮӢгҒӘгҒ©гҒ—гҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүгӮӮгҒҝгҒӮгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒеҖ’гӮҢгҒ“гӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҘіжҖ§гҒҢгҒ•гӮүгҒ«жҡҙиЎҢгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ„гӮҒгҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰйҰ–гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгӮ’жҠ‘гҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҘіжҖ§гҒҢгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷжҝҖжҳӮгҒ—гҖҒжҖ–гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒқгҒ®гҒҫгҒҫйҖғгҒ’её°гҒЈгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢиў«з–‘иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢз”·жҖ§еҒҙгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒеҘіжҖ§гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸйҖҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒдәӢ件гҒҜе®ӨеҶ…гҒ§иө·гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӣҙжҺҘгҒқгҒ®е ҙйқўгӮ’зӣ®ж’ғгҒ—гҒҹ第дёүиҖ…гҒҜгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒеҘіжҖ§гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒ„гҒҚгҒӘгӮҠиӯҰеҜҹгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒҢиҝ«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҷгҒҗгҒ«жӨңеҜҹе®ҳгҒ«йҖЈзөЎгӮ’еҸ–гӮҠгҖҒйқўи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҢеҸҢж–№гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ—гҒӢгҒӘгҒҸгҖҒжӯЈеҪ“йҳІиЎӣгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢдәӢ件гҒ гҒ—гҖҒз”·жҖ§гҒҜжЁӘжөңеёӮеҶ…гҒ§зңҹйқўзӣ®гҒ«е•ҶеЈІгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәзү©гҒӘгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮеӢҫз•ҷгҒ®зҗҶз”ұгҖҒеҝ…иҰҒжҖ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҖҒеӢҫз•ҷи«ӢжұӮгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶжұӮгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜгҖҒжқұдә¬гҒ§д»•дәӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж„ҸиҰӢжӣёдҪңжҲҗгҒ®жә–еӮҷгҒ®жҷӮй–“зҡ„дҪҷиЈ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒеҝөгҒ®гҒҹгӮҒгҒЁжҖқгҒ„гҖҒгҖҢгӮӮгҒ—еӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮӢгҒӘгӮүгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«еӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒ®еҚҙдёӢгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒҷгӮӢгҒЁжұәгӮҒгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§йҖЈзөЎгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЁй јгӮ“гҒ гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒҜгҖҢйҖЈзөЎгҒ—гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁзӯ”гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҚҲеҫҢпј”жҷӮгӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгӮӮжӨңеҜҹе®ҳгҒӢгӮүйҖЈзөЎгҒҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүйҖЈзөЎгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжӢ…еҪ“дәӢеӢҷе®ҳгҒӢгӮүгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еӢҫз•ҷи«ӢжұӮгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ гҒ‘дјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жӨңеҜҹе®ҳгҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒгҖҢзҙ„жқҹйҒ•еҸҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁжҠ—иӯ°гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒӢгӮүгҒҜгҖҢгҒқгӮ“гҒӘзҙ„жқҹгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁй–ӢгҒҚзӣҙгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—ҘгҖ…гҒ®жҘӯеӢҷгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«и¶іе…ғгӮ’жҺ¬гӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжҷӮжҠҳгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӢҫз•ҷгҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮпј‘пјҗж—Ҙй–“иҝ‘гҒҸгҒҜиә«жҹ„жӢҳжқҹгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиў«з–‘иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜд»•дәӢдёҠгӮӮйқһеёёгҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒ®гӮўгғігғ•гӮ§гӮўгҒӘеҜҫеҝңгҒ«жң¬еҪ“гҒ«жҖ’гӮҠеҝғй ӯгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ“гҒҶгҒӘгҒЈгҒҹд»ҘдёҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒЁгҒ®дәӨжёүгҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒҷгҒҗиЈҒеҲӨжүҖгҒ«йӣ»и©ұгҒ—гҖҒйқўжҺҘгӮ’з”ігҒ—е…ҘгӮҢгҖҒдёҰиЎҢгҒ—гҒҰж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йқўжҺҘгҒ§гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ«дәӢжЎҲгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиў«з–‘иҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ„иў«з–‘иҖ…гҒ®жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢдәӢжғ…гӮ’дјқгҒҲгҖҒеӢҫз•ҷи«ӢжұӮгӮ’еҚҙдёӢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгӮҲгҒҶеҸЈй ӯгҒ§гӮӮж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘжҖҘгҒ„гҒ§жә–еӮҷгҒ—гҒҹиҰӘж—ҸгҒ®иә«е…ғеј•еҸ—жӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®ж—ҘгҒ®еӨңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүеӢҫз•ҷи«ӢжұӮеҚҙдёӢгҒ®йҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮҠгҖҒеҚҲеҫҢпјҳжҷӮй ғгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиў«з–‘иҖ…гҒҜйҮҲж”ҫгҒ•гӮҢгҖҒиә«е…ғеј•еҸ—дәәгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з„ЎдәӢиҮӘе®…гҒ«её°гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
ж—©жңҹгҒ«иә«жҹ„жӢҳжқҹгӮ’и§ЈгҒҚгҖҒиҮӘз”ұгҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҲ‘дәӢдәӢ件гӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҖҒиә«жҹ„жӢҳжқҹгҒ«гӮҲгӮӢиў«з–‘иҖ…гҒ®зӨҫдјҡзҡ„дёҚеҲ©зӣҠгҒҜйқһеёёгҒ«йҮҚеӨ§гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иў«з–‘иҖ…ж®өйҡҺгҒ®еӢҫз•ҷгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰпј‘пјҗж—Ҙй–“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«йҖҡеёёдәӢ件гҒ§гҒҜгӮӮгҒҶпј‘пјҗж—Ҙ間延長гҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒйҖ®жҚ•гҒӢгӮүгҒ„гҒҶгҒЁпј“йҖұй–“д»ҘдёҠгҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеӨ§дҪ“гҒҢдәҲжғігҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәӢж…ӢгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®иә«жҹ„жӢҳжқҹгҒҢзӨҫдјҡзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§иҮҙе‘ҪеӮ·гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҖ®жҚ•гҒӢгӮүеӢҫз•ҷи«ӢжұӮгҒҫгҒ§гҒ«гҒҜгӮҸгҒҡгҒӢгҒӘжҷӮй–“гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«еӢҫз•ҷгӮ’гҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ејҒиӯ·жҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒқгҒҶе®№жҳ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮзӣёеҪ“гҒӘзһ¬зҷәеҠӣгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷпјҲеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒиӨҮж•°ејҒиӯ·еЈ«гҒ§еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
йҖҶгҒ«гҖҒжҚңжҹ»гҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒйҖ®жҚ•гҒ«гҒӣгӮҲгҖҒеӢҫз•ҷгҒ«гҒӣгӮҲгҖҒгҒҠеҪ№жүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғ«гғјгғҶгӮЈгғјгғігҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒжөҒгӮҢдҪңжҘӯгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жүӢз¶ҡгҒҢйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰгҖҒжҚңжҹ»ж©ҹй–ўгҒ®е•ҸйЎҢгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒ—гҒӢгӮҠгҒ§гҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«иҰӢгҒҰеӢҫз•ҷгҒ®зҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒеӢҫз•ҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиә«жҹ„жӢҳжқҹгӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’гҖҒдәӢжЎҲгҒ”гҒЁгҒ«иЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәӢ件гҒ§ејҒиӯ·еЈ«гҒҢйҒ©еҲҮгҒӢгҒӨж©ҹгӮ’йҖёгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚдәӢжғ…гӮ’иЈҒеҲӨжүҖгҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§ејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҪ№еүІгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒҢжҚңжҹ»ж©ҹй–ўгҒ®е•ҸйЎҢжҖ§гӮ’иЈҒеҲӨжүҖгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӢҫз•ҷеҲ¶еәҰгҒҢйҒ©еҲҮгҒ«йҒӢз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гӮӮйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒгӮӮгҒ—дҪ•гӮүгҒӢгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒ„гҒҲгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶жіҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘ж—©гӮҒгҒ«ејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҠ©иЁҖгӮ’д»°гҒҗгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸгҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“еј·еҲ¶жҚңжҹ»гҒ®гғ¬гғјгғ«гҒ«д№—гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүйҷҚгӮҠгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮе®№жҳ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ