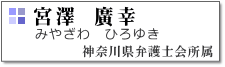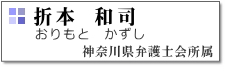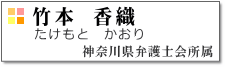дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әиў«е®ігӮ’йҳІгҒҺгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁ
й«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әдәӢ件гҒҜгҖҒгҒ„гҒӨгҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гӮӮеӨүгӮҸгӮүгҒҡиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒ•гӮүгҒ«ж—ҘеёёеҢ–гҒ—гҖҒгӮҲгӮҠжӮӘиіӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰе®ҹйҡӣгҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҹдәӢ件гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҖҢгӮ„гҒЈгҒҹгӮӮгӮ“еӢқгҒЎгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйўЁжҪ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®з©әж°—гҒҢгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеӮҫеҗ‘гӮ’еҠ©й•·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеӢӨеҠҙдё–д»ЈгҒ®е–„жӮӘгҒ®еҲӨж–ӯеҹәжә–гҒҢзӢӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒ®иЎ°гҒҲгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹеҚ‘еҠЈгҒӘи©җж¬әиў«е®ігӮ’гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҹгӮүйҳІгҒ’гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒжңҖиҝ‘еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұгҒӢгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ«гҒҜпј’гҒӨгҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢ件иҮӘдҪ“гҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ«иҮӘе®…гӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҒҰеҝғгӮ’иЁұгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒҠгӮҲгҒқдәҢжқҹдёүж–ҮгҒ®дёҚеӢ•з”ЈгӮ’иЁҖи‘үе·§гҒҝгҒ«еЈІгӮҠгҒӨгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜд»ҘеүҚгҒӢгӮүгҒӮгӮӢжүӢеҸЈгҒ§гҖҒеұӢж №гҒ®йӣЁжјҸгӮҠгҒЁгҒӢгҖҒгӮ·гғӯгӮўгғӘй§ҶйҷӨгҒӘгҒ©гҒ®еҗҚзӣ®гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁеҗҢж§ҳгҖҒзӢ¬еұ…гҒ®иҖҒдәәгӮ’зӢҷгҒҶе…ёеһӢзҡ„гҒӘжүӢеҸЈгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷпјҲгӮҸгӮҠгҒЁиүҜгҒ„иә«гҒӘгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰиҰӘеҲҮгҒӘжҢҜгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰе…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҒӮгҒҹгӮҠгҒҜд»ҠгӮӮжҳ”гӮӮеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒиӯҰжҲ’гӮ·гӮ°гғҠгғ«гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒеҸ—д»»гҒ—гҒҹдәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиӨҮж•°гҒ®дёҚеӢ•з”ЈжҘӯиҖ…гҒҢз«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«иЁӘгӮҢгҒҰеҗҢзЁ®гҒ®и©җж¬әгӮ’еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒҢгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж°—гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјҲгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжӣҙж–°з•ӘеҸ·гҒҢв‘ҙгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгӮӮиӯҰжҲ’гӮ·гӮ°гғҠгғ«гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒзҷ»иЁҳз°ҝ謄жң¬гӮ’еҸ–гҒЈгҒҹгӮҠгғӢгғҘгғјгӮ№е ұйҒ“гҒӘгҒ©гӮӮиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒз«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«иЁӘгӮҢгҒҹпј’зӨҫгҒ®жҘӯиҖ…гҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҳҺзҷҪгҒӘиЁјжӢ гҒ«гҒҜиҫҝгӮҠзқҖгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®дёҖзӨҫгҒ§гҒӮгӮӢпјўзӨҫгҒ®й–ўйҖЈдәӢ件гҒ®жғ…е ұгҒҢе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒқгҒ®жҘӯиҖ…гҒҜгҖҒеҲҘгҒ®дёҚеӢ•з”ЈжҘӯиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢпјЈзӨҫгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮүгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ“гҒ®пјЈзӨҫгҒ®дәәй–“гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«й«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әгҒ§йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе ұйҒ“гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒпјҷдёҮдәәгӮӮгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гҒ®еҗҚз°ҝгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзӢ¬еұ…гҒ®пјҳпјҗжӯід»ЈгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒ«гҒ—гҒҹи©җж¬әдәӢ件гҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®пјҷдёҮдәәгҒ®еҗҚз°ҝгҒҢгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁзӢ¬еұ…иҖҒдәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгғҮгғјгӮҝгҒ§гҒқгӮҢгӮ’е…ұжңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиӨҮж•°гҒ®и©җж¬әзӣ®зҡ„гҒ®йҖЈдёӯгҒҢзӢ¬еұ…иҖҒдәәгҒ«зҡ„гӮ’зөһгҒЈгҒҰдҪҸе®…ең°гӮ’еҫҳеҫҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ«еҫ—гҒҹжғ…е ұгҒ§гҒҜгҖҒйЁҷгҒ•гӮҢгҒҹиў«е®іиҖ…гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮй«ҳйҪўгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢж–°й•·и°·е·қејҸгҒӘгҒ©гҒ®жӨңжҹ»гҒ§гҒҜпј“пјҗзӮ№жәҖзӮ№дёӯпј’пјҗж•°зӮ№зЁӢеәҰеҸ–гӮҢгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ§ж—Ҙеёёзҡ„гҒӘеҸ—гҒ‘зӯ”гҒҲгҒҜдёҖеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§иҰӢгӮӢгҒЁгҒҹгҒ гҒЎгҒ«и©җж¬әгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒЁгҒҫгҒ§гҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе…ұйҖҡзӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒгҒӘгҒңдәҢжқҹдёүж–ҮгҒ®дёҚеӢ•з”ЈгҒ®иіје…ҘеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢе°ӢгҒӯгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮе…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжң¬дәәгҒ«гҒҜгҒқгӮӮгҒқгӮӮдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘгҒ®иӘҚиӯҳгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒйҠҖиЎҢгҒ®зӘ“еҸЈгҒ§гҒ®йҖҒйҮ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеЈІиІ·д»ЈйҮ‘гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиІёгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гҒҹгҒҸгӮүгҒ„гҒ®иӘҚиӯҳгҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷпјҲгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜйЁҷгҒ—гҒ®гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ®е·§еҰҷгҒ•гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒгғһгғӢгғҘгӮўгғ«еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒзўәиӘҚгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒ®еҜҫиұЎзү©д»¶гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҒҫгҒЁгӮӮгҒӘеҲӨж–ӯиғҪеҠӣгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°зө¶еҜҫгҒ«иІ·гӮҸгҒӘгҒ„гғ¬гғҷгғ«гҒ®гҒҠгӮҲгҒқдҫЎеҖӨгҒ®гҒӘгҒ„дёҚеӢ•з”ЈгҒ§гҒӮгӮҠпјҲиӘҝжҹ»гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁжҷӮдҫЎгҒ®еҚҒеҖҚгҒӢгӮүж•°еҚҒеҖҚгҒ§еЈІгӮҠгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖҒе®ҹдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸи©җж¬әгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®и©җж¬әдәӢ件гҒ®ж‘ҳзҷәгҒ«еҝ…гҒҡгҒ—гӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„жңҖиҝ‘гҒ®иӯҰеҜҹгҒ®еҜҫеҝңгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҲ‘дәӢдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰз«Ӣ件гҒҷгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§гҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҜдҪҺгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҰи©җж¬әзӣ®зҡ„гҒ§еҫҳеҫҠгҒҷгӮӢйҖЈдёӯгҒӢгӮүгҖҒзӢ¬еұ…гҒ®й«ҳйҪўиҖ…гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪ•гӮ’гҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
зҺҮзӣҙгҒ«з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҰгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зҠҜзҪӘгӮ’е®Ңе…ЁгҒ«йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮй«ҳйҪўиҖ…гҒ®ж–№гҒҢиҖҒеҫҢгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӯҗгӮ„еӯ«гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒЁиІҜгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹиҷҺгҒ®еӯҗгҒ®иІЎз”ЈгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңҖгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒӘжүӢж®өгӮ’еҸ–гӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгҒ—еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰзҸҫзҠ¶гҒ®жңҖе–„гҒ®ж–№жі•гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ§еҫҢиҰӢдәәгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜдҝқдҪҗдәәгӮ’йҒёд»»гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҖҒй җиІҜйҮ‘гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«з®ЎзҗҶгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и©җж¬әжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гӮ’гҒ•гҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜзӣ®зҡ„гӮ’йҒ”гҒӣгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®и©җж¬әгҒ®е ҙеҗҲгҖҒйҠҖиЎҢгҒӢгӮүйҖҒйҮ‘гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§гӮ„гӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒ®ж°ҙйҡӣгҒ§жӯўгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜгҒҷгӮҠжҠңгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеӨҡйЎҚгҒ®й җиІҜйҮ‘гҒ®з®ЎзҗҶгӮ’жң¬дәәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҫҢиҰӢдәәгҒӢдҝқдҪҗдәәгҒҢиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй җиІҜйҮ‘гҒӢгӮүгҒ®йҖҒйҮ‘иҮӘдҪ“гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҫҢиҰӢдәәгҒҢе°ұгҒ„гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҒқгӮӮгҒқгӮӮи©җж¬әжҘӯиҖ…гҒЁжң¬дәәгҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„иҮӘдҪ“гҒҢз„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒдҝқдҪҗдәәгӮӮеҘ‘зҙ„гҒ®еҸ–ж¶ҲжЁ©гӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеҫҢзҡ„гҒӘеҜҫеҝңгӮӮеҗ«гӮҒгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®жүӢз¶ҡгӮ’е®ҹи·өгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ®гҒҢгғҷгӮ№гғҲгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒд»ҠеӣһгҒ®дәӢ件гҒ§гӮӮжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҶгӮ№гғҲгҒ§иӘҚзҹҘз—ҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘж–№гҒ®е ҙеҗҲгҖҒжһңгҒҹгҒ—гҒҰеҫҢиҰӢдәәгҖҒдҝқдҪҗдәәгӮ’йҒёд»»гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҚеӢ•з”ЈеЈІиІ·гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиІЎз”ЈгӮ’ж №гҒ“гҒқгҒҺеҘӘгӮҸгӮҢгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҸ–еј•гҒ®еҲӨж–ӯгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дәәгҒ«гҒ“гҒқжі•зҡ„гҒӘеәҮиӯ·гҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҰҒеҫҢиҰӢгҖҒиҰҒдҝқдҪҗзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒёд»»иҰҒ件гҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚгҒқгҒҶгҒ—гҒҹиҰізӮ№гҒӢгӮүгҒӘгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒиў«е®ігӮ’дәҲйҳІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒӢгҒӨжҹ”и»ҹгҒ«йҒёд»»гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
зҸҫеңЁгҒ®гҖҒй«ҳйҪўиҖ…гӮ’зӢҷгҒЈгҒҹи©җж¬әгҒҢжЁӘиЎҢгҖҒ蔓延гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдё–гҒ®дёӯгҒ®е®ҹж…ӢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢйҒёд»»иҰҒ件гӮ’жҹ”и»ҹгҒ«и§ЈйҮҲгҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒд»®гҒ«иЈҒеҲӨжүҖгҒ®жүӢз¶ҡгҒ«е§”гҒӯгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж—©жҖҘгҒ«дҝқиӯ·зҡ„гҒӘеҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒд»»ж„ҸеҫҢиҰӢеҘ‘зҙ„гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰиІЎз”Јз®ЎзҗҶеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иІЎз”Јз®ЎзҗҶеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡйЎҚгҒ®й җиІҜйҮ‘гҒ®е…ҘгҒЈгҒҹйҖҡеёігӮ’дҝЎй јгҒ®гҒҠгҒ‘гӮӢдәәзү©гҒ«й җгҒӢгҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒ°гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮй җиІҜйҮ‘гӮ’гҒ гҒҫгҒ—еҸ–гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжңӘ然гҒ«йҳІгҒ’гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҪ“йқўгҒ®еҜҫеҝңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгҒӢгӮүгҒ•гҒҫгҒ§жӮӘиіӘгҒӘи©җж¬әгҒҢжЁӘиЎҢгҒҷгӮӢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«е«ҢгҒӘжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҲ‘гҒҢиә«гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӨ§еҲҮгҒӘиҰӘж—ҸгҒ®иҖҒеҫҢгҒ®иіҮйҮ‘гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зҹҘжҒөгӮ’зөһгӮҠгҖҒе…ҲжүӢгӮ’жү“гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®гҖҢзҙ…йә№гҖҚгҒ®е•ҸйЎҢ
е°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒҢз”ҹз”ЈгҒ—гҒҹгҖҢзҙ…йә№гҖҚгҒ«гӮҲгӮӢи…Һж©ҹиғҪйҡңе®ігҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҖҒжӯ»иҖ…гҖҒж„ҹжҹ“иҖ…ж•°гӮӮж—ҘгӮ’иҝҪгҒЈгҒҰеў—гҒҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«иЁҲпј‘пј—пјҗзӨҫгӮӮгҒ®дјҒжҘӯгҒ«д»–гҒ®дјҒжҘӯгҒ«гӮӮе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒҢз”ҹз”ЈгҒ—гҒҹзҙ…йә№гҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®еҪұйҹҝгҒҢгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒӢдәҲж–ӯгӮ’иЁұгҒ•гҒҡгҖҒеә•гҒӘгҒ—гҒ®ж§ҳзӣёгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дәӢ件гҒ®гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒи…ҺиҮ“гҒҜдҪ“еҶ…гҒ§з”Јз”ҹгҖҒеҗёеҸҺгҒ•гӮҢгҒҹд»Ји¬қз”Јзү©пјҢеҢ–еӯҰзү©иіӘпјҢи–¬еүӨзӯүгӮ’жҝғзё®гҒ—пјҢжҺ’жі„гҒҷгӮӢгҖҒе°ҸгҒ•гҒ„гҒӘгҒҢгӮүйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘиҮ“еҷЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«и–¬еүӨзӯүгҒ®еҪұйҹҝгҒ§и…Һйҡңе®ігӮ’гҒҚгҒҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件гҒ®й–ўдҝӮгҒ§иӘҝгҒ№гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи–¬еүӨзӯүгҒ®еҪұйҹҝгҒ§и…Һйҡңе®ігӮ’гҒҚгҒҹгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„зҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒи…ҺиҮ“гҒёгҒ®иЎҖжөҒйҮҸгҒҢиұҠеҜҢгҒӘгҒҹгӮҒ(еҝғжӢҚеҮәйҮҸгҒ®пј’пј•пј…зЁӢеәҰгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷ)гҖҒи–¬зү©гӮӮеҪ“然еӨҡгҒҸжөҒе…ҘгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ зҡ„гҒ«и–¬зү©гҒҢдёҠзҡ®зҙ°иғһгҒ«еҸ–гӮҠиҫјгҒҫгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„д»•зө„гҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гӮӮи–¬зү©гҒ®жҝғеәҰгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰжҜ’жҖ§еҹҹгҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„зӯүгҖҒи–¬зү©гҒ®еҪұйҹҝгҒ§и…Һйҡңе®ігҒҢиӘҳзҷәгҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж©ҹеәҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒжҖҘжҖ§е°ҝзҙ°з®Ўй–“иіӘжҖ§и…ҺзӮҺгҒ«зҪ№жӮЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ®е ұйҒ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи–¬еүӨжҖ§гҒ®и…Һж©ҹиғҪйҡңе®ігҒ®зҙ„еҚҠж•°гҒҜжҖҘжҖ§е°ҝзҙ°з®Ўй–“иіӘжҖ§и…ҺзӮҺгҒЁгҒ„гҒҶз—…ж…ӢгӮ’зӨәгҒҷгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ§гҒ“гӮҢгҒӢгӮүжҸҗиЁҙдәҲе®ҡгҒ®з—ҮдҫӢгҒ®дёӯгҒ«гҖҒжҠ—иҸҢи–¬гҒ®йҒёжҠһгӮ’иӘӨгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«жҖҘжҖ§гҒ®и…ҺдёҚе…ЁгӮ’гҒҚгҒҹгҒ—гҒҰдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢз—ҮдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгғҗгғігӮігғһгӮӨгӮ·гғігҒЁгӮІгғігӮҝгғһгӮӨгӮ·гғігҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒи…Һйҡңе®ігҒ®еў—жӮӘгӮ’жӢӣгҒҸеүҜдҪңз”ЁгҒҢеҠ©й•·гҒ•гӮҢгҖҒзҙ„пј’пјҗж—ҘгҒ®йҖЈз¶ҡжҠ•дёҺгҒ§жң«жңҹзҡ„гҒӘжҖҘжҖ§и…ҺдёҚе…ЁгӮ’гҒҚгҒҹгҒҷгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдәӢзЁӢе·Ұж§ҳгҒ«гҖҒи–¬еүӨжҖ§и…Һйҡңе®ігҒҜгҒҫгҒ•гҒ«е‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢйҮҚеӨ§гҒӘз—…ж…ӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҖҒдәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒҢеҫҗгҖ…гҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйҖ”дёӯгҒ§гҖҒгҒҫгҒ гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„зӮ№гҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе•ҸйЎҢгҒ®зҙ…йә№гҒҢз”ҹз”ЈгҒ•гӮҢгҒҹеӨ§йҳӘгҒ®е·Ҙе ҙгҒҢжҳЁе№ҙпј‘пј’жңҲгҒ«й–үйҺ–гҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҪ“и©ІгҒ®зҙ…йә№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«гҒҚгҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒӢгӮүгҖҢгғ—гғҷгғ«гғ«й…ёгҖҚгҒҢжӨңеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶе ұйҒ“гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҒһгҒҚж…ЈгӮҢгҒӘгҒ„еҗҚеүҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гӮүйқ’гҒӢгҒігҒӢгӮүз”Јз”ҹгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒҜгҒҡгҒЈгҒЁжңӘзҹҘгҒ®зү©иіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҒ”гҒЁгҒҚзҷәиЎЁгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢгғ—гғҷгғ«гғ«й…ёгҖҚгҒЁгҒ®зү№е®ҡгҒҜеҺҡеҠҙзңҒгҒ®зҷәиЎЁгҒ§еҮәгҒҰгҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒе°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®жғ…е ұй–ӢзӨәгҒ®е§ҝеӢўгҒ«гҒҜгӮ„гҒҜгӮҠз–‘еҝөгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲд»Ҡе№ҙпј’жңҲй ғгҒ«гҒҜж ӘдҫЎгҒҢжҡҙиҗҪгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶе ұйҒ“гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгӮӨгғігӮөгӮӨгғҖгғјгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®еЈ°гӮӮдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз–‘е•ҸгҒҜе°ҪгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮ
гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁи©ұгӮ’жҲ»гҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒд»ҠеӣһгҒ®е ұйҒ“гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҲҘгҒ®еҢ»зҷӮдәӢ件гҒЁгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁзҠ¶жіҒгҒҢдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„иҮігӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒзҷҪеҶ…йҡңгҒ®жүӢиЎ“еҫҢгҒ«ж„ҹжҹ“жҖ§зңјеҶ…зӮҺгӮ’зҷәз—ҮгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®дҫқй јиҖ…д»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒеҗҢгҒҳж—ҘгҒ«зҷҪеҶ…йҡңжүӢиЎ“гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдәәгҒ«ж„ҹжҹ“жҖ§зңјеҶ…зӮҺгӮ’зҷәз—ҮгҒ—гҒҹдәәгҒҢиӨҮж•°гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжүӢиЎ“гҒЁгҒ®й–ўйҖЈгҒҢз–‘гӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®ж„ҹжҹ“гҒ®иө·еӣ иҸҢгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҒҜзңҹиҸҢгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгӮ«гғ“иҸҢгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҪ“и©Ізңјз§‘гҒ®жүӢиЎ“е®ӨгҒ®еЈҒгҒ®е·ҫжңЁгҒӢгӮүзңҹиҸҢгҒҢжӨңеҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҒҜгҖҒжүӢиЎ“е®ӨгҒҢдёҚиЎӣз”ҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгӮ«гғ“иҸҢгҒҢз№Ғж®–гҒ—гҒҰдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҪўгҒ§жӮЈиҖ…гҒ«ж„ҹжҹ“гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶж©ҹеәҸгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
е°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®дәӢ件гҒ®иө·еӣ зү©иіӘгҒҢгӮ«гғ“гҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдёҠиЁҳгҒ®дәӢ件гҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгҖҒз”ҹз”ЈзҸҫе ҙгҒҢдёҚиЎӣз”ҹгҒӘгҒҹгӮҒгҒ«зҙ…йә№гҒ®з”ҹз”ЈйҒҺзЁӢгҒ§йқ’гҒӢгҒігҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒ§гҒҚгҒҹгҖҢгғ—гғҷгғ«гғ«й…ёгҖҚгҒҢе…ҘгӮҠиҫјгҒҝгҖҒеў—ж®–гҒ—гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йқ’гҒӢгҒігҒҜж№ҝж°—гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒз©әж°—гҒҢжҫұгӮҖгӮҲгҒҶгҒӘе ҙжүҖгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒ©гҒ“гҒ§гӮӮзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§йҳӘе·Ҙе ҙгҒ®й–үйҺ–гҒҢе•ҸйЎҢгҒ®зҷәиҰҡгҒ«иҝ‘жҺҘгҒ—гҒҹжҷӮжңҹгҒ§гҒӮгӮӢеҺ»е№ҙпј‘пј’жңҲгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁиЁјжӢ йҡ ж»…гҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁз–‘гӮҸгӮҢгҒҰгӮӮд»•ж–№гҒ®гҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹз”ЈзҸҫе ҙгҒҢдёҚиЎӣз”ҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢеҗҰгҒӢгҖҒйқ’гҒӢгҒігҒҢз№Ғж®–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜгҖҒзҸҫе ҙгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮҢгҒ°жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒиӮқеҝғгҒ®е·Ҙе ҙгҒҢй–үйҺ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жӨңиЁјгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гӮүгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢгғ—гғҷгғ«гғ«й…ёгҖҚгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠжҜ’жҖ§гҒ®еј·гҒ„зү©иіӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒи…Һж©ҹиғҪгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒҫгҒ гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒйқ’гҒӢгҒігҒӢгӮүгҖҢгғ—гғҷгғ«гғ«й…ёгҖҚгҒҢз”ҹжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢж©ҹеәҸгҒ®и§ЈжҳҺгӮӮгҒҫгҒ гҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«ж‘ӮеҸ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еӨҡгҒ„гӮөгғ—гғӘгҒ®дәәдҪ“гҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҜжұәгҒ—гҒҰи»ҪиҰ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
д»Ҡж—Ҙж—ҘгҖҒзҢ«гӮӮжқ“еӯҗгӮӮгҖҒеҒҘеә·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮөгғ—гғӘгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®е®үе…ЁжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гҒҜйҮҺж”ҫгҒ—гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зү№гҒ«гҖҒд»ҠеӣһгҒ®е°Ҹжһ—иЈҪи–¬гҒ®е•Ҷе“ҒгҒҜгҖҒж©ҹиғҪжҖ§иЎЁзӨәйЈҹе“ҒгҒЁгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгӮүгҒ—гҒҸгӮ«гғҶгӮҙгғ©гӮӨгӮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж—©гҒ„и©ұгҖҒеҪ“и©ІдјҒжҘӯгҒ®иҮӘдё»з”іе‘ҠпјҲеұҠеҮәгҒ®гҒҝпјүгҒ§гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«и¬ігҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒе…¬зҡ„гҒӘж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгӮӢеҜ©жҹ»гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҒӘгҒҠгҒ•гӮүгҒ§гҒҷпјҲгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®ж©ҹиғҪжҖ§иЎЁзӨәйЈҹе“ҒгӮӮе®үеҖҚж”ҝжЁ©гҒ®жҷӮгҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢжөҒйҖҡгҒҷгӮӢжғ…е ұгӮ’йөңе‘‘гҒҝгҒ«гҒӣгҒҡиіўгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒқгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҒҘеә·гӮ„е‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢйЈҹе“ҒгӮ„гӮөгғ—гғӘгҖҒйЈІж–ҷзӯүгҒ®е®үе…ЁжҖ§гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҢе…¬зҡ„гҒӘеҪўгҒ§жӢ…дҝқгҒ•гӮҢгӮӢд»•зө„гҒҝгҒҜеҝ…й ҲгҒӘгҒ®гҒ гҒЁгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰз—ӣж„ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…пј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’
еүҚеӣһгҒӢгӮүз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
з ”дҝ®еҢ»гҒҢеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжҢҮе°ҺгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮ“гҒӘеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§йҮҚеӨ§гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒңгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
иүІгҖ…иӘҝгҒ№гҒҹгӮҠгҖҒи©ұгӮ’дјәгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеў—гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиғҢжҷҜзҡ„гҒӘдәӢжғ…гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«жҖқгҒ„иҮігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒӮгӮӢиҮЁеәҠеҢ»гҒӢгӮүдјәгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮй–ўдҝӮиҖ…гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹж–ҮзҢ®гҒ§гӮӮзӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘиғҢжҷҜдәӢжғ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢз ”дҝ®гҒ®гҒҹгӮҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒзҸҫе ҙгҒ®жҲҰеҠӣгҒЁгҒ—гҒҰз ”дҝ®еҢ»гӮ’йӣҮгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйқўгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠгҒ®еҢ»зҷӮгҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒеӣҪгҒ®ж”ҝзӯ–гҒ§еҢ»зҷӮиІ»гҒҢеүҠжёӣгҒ•гӮҢгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢиөӨеӯ—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫе®ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒеҢ»её«гҒ®з ”дҝ®еҲ¶еәҰгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҖҒдёҖе®ҡгҒ®зөҢйЁ“гӮ’жңүгҒҷгӮӢеҢ»её«гӮ’еёӮдёӯгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢзўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢжғ…гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжң¬жқҘгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдёҖе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўгӮ’жңүгҒҷгӮӢеҢ»её«гҒҢй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚе ҙжүҖгҒ«гҖҒзөҢйЁ“гҒ®е°‘гҒӘгҒ„з ”дҝ®еҢ»гӮ’гҒӮгҒҰгҒҢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠжҢҮе°ҺгҖҒеҠ©иЁҖгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®еҒҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒӘгӮ“гҒҰзҹҘгӮӢиЎ“гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒз©әжҒҗгӮҚгҒ—гҒ„йҷҗгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
и…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ®гғҹгӮ№гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒеҪ“и©Із ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§дёҖеәҰгӮӮи…°жӨҺз©ҝеҲәгӮ’гӮ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒқгҒҶгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§й«„ж¶ІжҺЎеҸ–гҒҫгҒ§пј—еӣһгӮӮз©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғўгғ«гғўгғғгғҲгҒӢгҒЁгҒ„гҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„и©ұгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеүҚгҒ«зңҢеҶ…гҒ®гғҷгғҶгғ©гғігҒ®еҢ»её«гҒ®ж–№гҒ«иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеҶ…гҒ®гҒӮгӮӢең°еҹҹгҒ®еҹәе№№з—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒеӨңй–“гҒ®ж•‘жҖҘеҜҫеҝңгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒ«еҜҫеҝңгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“и©ІеҢ»её«гҒ„гӮҸгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒ§ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзө¶еҜҫгҒ«еҲҘгҒ®з—…йҷўгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гӮ·гғЈгғ¬гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҪ•еәҰгӮӮдҪ•еәҰгӮӮз©ҝеҲәгҒ«еӨұж•—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй–“гҖҒгӮӮгҒ—жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ°гҒ«гҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҖҢгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒҜеҚұйҷәгҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰйҖ”дёӯгҒ§жүӢжҠҖгӮ’дәӨд»ЈгҒҷгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒеӨҡж•°еӣһгҒ®з©ҝеҲәгҒ®еҚұйҷәжҖ§гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒиЎ“еҫҢз®ЎзҗҶгҒҜеҪ“然еҺійҮҚгҒ«гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒиЎ“еҫҢгҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒӘз•°еёёгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢй–ўдёҺгҒ—гҒҹеҪўи·ЎгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒҜиӘ°гҒ®гғҹгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒ„гҒҲгҒ°гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«еҚұйҷәжҖ§гҒ®дјҙгҒҶеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгӮ’гӮ№гғ«гғјгҒ§гӮ„гӮүгҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒЁи©•дҫЎгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚгҒ«гҖҒгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҢ»её«гҒӢгӮүгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹз—…йҷўгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§зӣёи«ҮгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒқгҒ®з—…йҷўгҒ§з ”дҝ®еҢ»гҒҢгҒІгҒ©гҒ„зӣ®гҒ«йҒӯгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе®ҹжғ…гӮ’жүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҖҒгҒӮгҒ®з—…йҷўгҒ§гҒҜгҒҫгҒЁгӮӮгҒӘжҢҮе°ҺгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒз ”дҝ®еҢ»гӮ’жҙҫйҒЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁжҶӨгҒЈгҒҰгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з ”дҝ®еҢ»гӮ’иӮІгҒҰгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®үжҳ“гҒ«жҲҰеҠӣгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгҒ гҒ‘гҒ®з—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒқгҒ®йҖҡгӮҠгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰжҖқгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҢ»зҷӮеҒҙгҒ«гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜеҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮзү©з”ігҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒ•гҒ«з ”дҝ®еҢ»еҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡгҖҒдәҢгҒӨжҸҗжЎҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖгҒӨгҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гҒҜеҗҚжңӯгҒ«дҪ•е№ҙзӣ®гҒ®з ”дҝ®еҢ»гҒӢгӮ’жҳҺиЁҳгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖӮжӮЈиҖ…гҒҢдёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгӮүгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®еҜҫеҝңгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
з—…йҷўеҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜз…©гӮҸгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢз–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®йҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҖҒгғ©гғ”гғғгғүгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гғҒгғјгғ гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеүҚгҒ«еҠ©иЁҖгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹеҢ»её«гҒӢгӮүж•ҷгӮҸгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁеҠ©иЁҖгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®жҢҮзӨәгҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁиӢҘгҒ„еҢ»её«гҒҢз–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒ科гҒ®жһ гӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҖҒжЁӘж–ӯзҡ„гҒ«зӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғҒгғјгғ гҒҢйҷўеҶ…гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҢгҒқгҒ“гҒ«й§ҶгҒ‘иҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®йҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁгҖҒжңҖеҫҢгҒ«еҢ»зҷӮеҒҙгҒ«еј·гҒҸиЁҙгҒҲгҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹжҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҡгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒзңҹйқўзӣ®гҒӘеҢ»зҷӮиҖ…гҒ»гҒ©гғҲгғ©гӮҰгғһгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҢ»её«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дәәз”ҹгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸзӢӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҖҒдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ®ж–№гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪ“йЁ“и«ҮгӮ’дјәгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҢ»её«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢдәӢж•…гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢзӣ®гӮ’й…ҚгҒЈгҒҰжҷ®йҖҡгҒ«ж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгӮ«гғҗгғјгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®дәӢж•…гӮ’гҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰз„ЎгҒҸгҒҷгҒӢгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзҹҘжҒөгӮ’зөһгҒЈгҒҰиүҜгҒ„еҢ»зҷӮгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒЁеј·гҒҸжҖқгҒҶ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…пј°пҪҒпҪ’пҪ”пј‘
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гӮӮгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®дёӯгҒ§дҪ•еәҰгҒӢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰжӯЈйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӯЈйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒӢгҒЁз”ігҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиӨҮж•°гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжҜ”ијғзҡ„жңҖиҝ‘и§ЈжұәгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®еүІеҗҲгҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒзҸҫеңЁгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ§гҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒҜгҖҒ6件гҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“пј‘е№ҙдҪҷгӮҠгҒ®й–“гҒ«и§ЈжұәгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢ4件пјҲжӯҜ科еҢ»гӮ„дёҖиҲ¬й–ӢжҘӯеҢ»гҒ®дәӢ件гӮ’йҷӨгҒҚгҒҫгҒҷпјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜжҸҗиЁҙжә–еӮҷдёӯгҒ®жЎҲ件гҒҢ2件гҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁеҚҠж•°гҒҢз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒҢзөЎгӮ“гҒ еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮзҸҫеңЁиӘҝжҹ»дёӯгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜзӨәи«ҮдәӨжёүдёӯгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҺіеҜҶгҒ«гҒҜеҚҠж•°гӮҲгӮҠгҒҜдёӢеӣһгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖж–№гҖҒдёҠгҒ®пј‘2件гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒд»Ӣиӯ·гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜе…ҘжөҙгҒҢгӮүгҒҝгҒ®дәӢж•…гҒҢ2件еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒе®ҹж„ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢдәӢж•…гҒ®жҜ”зҺҮгҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„еҚ°иұЎгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгҒҸгҒҫгҒ§еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»–гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒӢгӮүгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘи©ұгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒд»ҘеүҚгҒЁжҜ”гҒ№гҒҰгӮӮеў—еҠ гҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҹеӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒ“гҒ“гҒ®жүҖжүұгҒЈгҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’гҒ•гӮүгҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®еӮҫеҗ‘гҖҒзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«еҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒдҪҝгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„и–¬гӮ’иӘӨгҒЈгҒҰжҠ•дёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫеңЁиЁҙиЁҹдёӯгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒж•—иЎҖз—ҮгҒ®жӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЎҖж¶Іеҹ№йӨҠжӨңжҹ»гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰиө·еӣ иҸҢгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгҒ®иө·еӣ иҸҢгҒ«гҒҜз„ЎеҠ№гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢи–¬гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰжҠ•дёҺгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®ж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§жңҖеҲқгҒ®и–¬гҒҢеҠ№гҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒгҒҫгҒҹгӮӮгӮ„иӘӨгҒЈгҒҹи–¬гӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒҰгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢжӯ»дәЎгҒҷгӮӢгҒ«иҮігӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжңҖгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжүӢжҠҖгӮ’й–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒ4件гҒҢз©ҝеҲәгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠйҮқгӮ’еҲәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶжүӢжҠҖгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒҢ2件гҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒҢ1件гҖҒиӮқз”ҹжӨңгҒҢ1件гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ®пј’件гҒЁиӮқз”ҹжӨңгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеӢ•и„ҲиӘӨз©ҝеҲәгҒ§еҮәиЎҖеӨҡйҮҸгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжӮЈиҖ…гҒҜдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒжӮЈиҖ…гҒ«йҮҚзҜӨгҒӘеҫҢйҒәз—ҮгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®пј”件гҒ®гҒҶгҒЎпј“件гҒҜгҖҒеҗҲиЁҲгҒ®з©ҝеҲәеӣһж•°гҒҢгҖҒпј–еӣһгҒӘгҒ„гҒ—пј‘пјҗеӣһгҒ«еҸҠгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷпјҲиӮқз”ҹжӨңгҒҜйҖ”дёӯгҒ§гғҷгғҶгғ©гғігҒ®еҢ»её«гҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ»гҒӢгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒ§гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе°‘гҒ—еүҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҮҚзҜӨгҒӘжҖҘжҖ§и…№з—ҮгҒ®дәӢжЎҲгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒеҜҫеҝңгҒ—гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒҢгғ¬гғігғҲгӮІгғігӮӮж’®гӮүгҒҡгҖҒпј“жӯігҒ®еӯҗдҫӣгӮ’жҖҘжҖ§иғғи…ёзӮҺгҒЁиЁәж–ӯгҒ—гҒҰеё°е®…гҒ•гҒӣгҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ®еӨңгҖҒгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ§жҖҘеӨүгҒ—гҒҰжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢжҳҺгӮүгҒӢгҒӘиӘӨиЁәгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®дәӢж•…гӮ’еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзңӢйҒҺгҒ—йӣЈгҒ„зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹж§ҳеӯҗгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒгҒ»гҒјгғҺгғјгӮҝгғғгғҒгҒ§д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒзөҢйЁ“гҒҢжө…гҒҸгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжүӢжҠҖгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒи–¬гӮ„жІ»зҷӮж–№йҮқгҒ®йҒёжҠһгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгғҮгғӘгӮұгғјгғҲгҒӘз—ҮдҫӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁәж–ӯгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮзҡ„зўәгҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒе ҙйқўе ҙйқўгҒ§гҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҒ©е®ңеҠ©иЁҖгҖҒжҢҮе°ҺгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…й ҲгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҠиЁҳгҒ®з—ҮдҫӢгҒ§гҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒ§й–ўдёҺгҒ—гҒҹз—ҮдҫӢгҒҜ1件гҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹпјҲгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒқгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒзөҢйҒҺиҰіеҜҹгҒ§гҒҜе®Ңе…ЁгҒ«з ”дҝ®еҢ»д»»гҒӣгҒ§гҖҒзөҗеұҖжӮЈиҖ…гҒҜеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§дәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖӮ
жҷ®йҖҡгҒ«иҖғгҒҲгҒҰгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒпј—еӣһгҒЁгҒӢпј‘пјҗеӣһгӮӮгҒ®еӣһж•°з©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒӣгҒ°гҖҒеӢ•и„ҲгҒӘгҒ©гҒ«иҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘжҗҚеӮ·гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷеҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҖ”дёӯгҒ§дәӨд»ЈгҒӣгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжңҖеҫҢгҒҫгҒ§з ”дҝ®еҢ»гҒ«з©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҒқгҒ®е ҙгҒ«жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҒжңӘеҝ…гҒ®ж•…ж„ҸгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ•гҒҲжҖқгҒҲгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒЁгҒҠи©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ§гӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢеҝ…гҒҡгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘд»•зө„гҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеёёгҒ«жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ°гҒ§гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒӘгҒҢгӮүиЎҢгӮҸгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒиӘӨиЁәгҒ§пј“жӯіе…җгӮ’жӯ»гҒӘгҒӣгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒиӨҮж•°еӣһгҒ®иӘӨз©ҝеҲәгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒжҠ—иҸҢи–¬гҒ®йҒёжҠһгӮ’иӘӨгҒЈгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹеҪўи·ЎгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еүҚиҝ°гҒ—гҒҹжҠ—иҸҢи–¬гҒ®иӘӨжҠ•дёҺгҒ®з—ҮдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜй»„иүІгғ–гғүгӮҰзҗғиҸҢж„ҹжҹ“гҒ§гҒ®ж•—иЎҖз—ҮгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЎҖж¶Іеҹ№йӨҠжӨңжҹ»гҒЁдҪөгҒӣгҒҰе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§гҒ©гҒ®жҠ—иҸҢи–¬гҒҢеҠ№гҒҸгҒӢгӮ’иӘҝгҒ№гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гғҶгӮ№гғҲгҒ®зөҗжһңгҒҢеҮәгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ®еҲӨе®ҡгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жҠ—иҸҢи–¬гҒ§гҒӮгӮӢпј°пј©пј°пјЈгҒЁгҒ„гҒҶи–¬гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰжҠ•дёҺгҒҷгӮӢпјҲгҒқгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҒЁгҒ„гҒҶгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гӮүж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§ж„ҹеҸ—жҖ§гҒӮгӮҠгҒЁеҲӨе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹпјӯпј°пј©пј°пјЈгҒЁеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒ гҒЁеӢҳйҒ•гҒ„гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢе ҙйқўгҒ§гҖҒ笑гҒ„и©ұгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҒёжҠһгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒҜеҲ°еә•иҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®еҢ»зҷӮиЎҢзӮәгӮ’жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҫгҒЁгӮӮгҒ«зӣЈзқЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒӢжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘз—ҮдҫӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
й•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒпј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһиғҪзҷ»еҚҠеі¶ең°йңҮгҒЁгҖҢжөҒдҪ“гҖҚгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁPartпј’
Partпј‘гҒӢгӮүгҒ®з¶ҡгҒҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиғҪзҷ»еҚҠеі¶гҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®ең°йңҮгҒҢжқҘгӮӢеүҚгҒ«гҒҜгҖҒеӣҪгҒҢдҪңжҲҗгҒҷгӮӢең°йңҮгғһгғғгғ—дёҠгҒ§гҒҜгҖҒеҚұйҷәгҒӘжҙ»ж–ӯеұӨгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдёҖжҳЁе№ҙгҒ®зҫӨзҷәең°йңҮгҒ®йҡӣгӮӮгҖҒең°йңҮиӘҝжҹ»е§”е“ЎдјҡгҒ®е№із”°гҒЁгҒ„гҒҶ委員長гҒҜгҖҒгҖҢд»ҠеҫҢгӮӮгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜеҗҢзЁӢеәҰгҒ®иҰҸжЁЎгҒ®ең°йңҮгҒҢиө·гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒЁйҖҡгӮҠдёҖйҒҚгҒ®иҰӢи§ЈгӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгӮӮеҗҢгҒҳдәәзү©гҒҢеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘзҷәиЁҖгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒPartпј‘гҒ§гӮӮжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҷгҒ§гҒ«гҖҒйҮ‘жІўеӨ§гҖҒдә¬еӨ§гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®з ”究иҖ…гҒҜгҖҒгҖҢжөҒдҪ“гҖҚгҒ®еӯҳеңЁгҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢе·ЁеӨ§ең°йңҮгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜжҙҘжіўгҒ®еҚұйҷәгҒ«гҒҫгҒ§иЁҖеҸҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒең°йңҮиӘҝжҹ»е§”е“ЎдјҡгҒ®иӘҚиӯҳгҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ гҒ—гҖҒ委員дјҡгҒ®еӯҳеңЁж„Ҹзҫ©гҒҢз–‘гӮҸгӮҢгҒҰгӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„еӨұж…ӢгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҲеӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒӣгӮҒгҒҰгҖҒ委員дјҡгҒ®иӘҚиӯҳгҒҢз”ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒЈгҒҰй ӯгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒ•гӮүгҒ«иҖғгҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒең°йңҮдәҲзҹҘгҒ§гҒ—гҒҚгӮҠгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ®жӣ–жҳ§гҒ•гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒЈгҒҰгҖҒжң¬еҪ“гҒ«иҮӘ然科еӯҰзҡ„гҒ«гҒҝгҒҰгҖҒжӯЈгҒ—гҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиЁҖи‘үгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§иө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢе·ЁеӨ§ең°йңҮгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒ®гҒҡгӮҢгҒ§иө·гҒҚгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒй•·йҮҺзңҢеҢ—йғЁең°йңҮгҒЁзҶҠжң¬ең°йңҮгҒ®гҒҝгҒ гҒқгҒҶгҒ§пјҲжқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪгҒҜзҷәз”ҹгҒ®ж©ҹеәҸгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иғҪзҷ»еҚҠеі¶ең°йңҮгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒжҙ»ж–ӯеұӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁдәӢеүҚгҒ«жҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙжүҖгҒ§иө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒж–ӯеұӨгӮ’жҙ»ж–ӯеұӨгҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«еҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«дҪ•гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘е•ҸгҒҢ湧гҒ„гҒҰжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒжҙ»ж–ӯеұӨгҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ§гҒҜең°йңҮгҒёгҒ®еӮҷгҒҲгҒ«еҝғгҒҢгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе•“зҷәзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүж–ӯеұӨгҒҢгҒҡгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒд»ҠгҒ®з§‘еӯҰгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒҜеҺіеҜҶгҒ«еҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжң¬еҪ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иғҪзҷ»еҚҠеі¶ең°йңҮгҒҢиө·гҒҚгҒҹгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒҢгҖҢжөҒдҪ“гҖҚгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҖҢжҙ»гҖҚж–ӯеұӨгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜгҖҒдҪ•гҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е№іжқҫж•ҷжҺҲгӮүгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒең°дёӢгҒ®жөҒдҪ“гҒҜгҖҒжқұдә¬гғүгғјгғ пј’пј“жқҜеҲҶгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§пјҲгҒқгӮҢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒҷгҒ”гҒ„гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжө·еә•гҒ®ж–ӯеұӨгҒ«е…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ§ж–ӯеұӨгӮ’жҠјгҒ—еәғгҒ’гҖҒгҒҡгӮҢгӮ’жӢӣгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒжөҒдҪ“гҒ®иЎҢ方次第гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжөҒдҪ“гҒҢе…ҘгӮҠиҫјгӮҖдҪҷең°гҒ®гҒӮгӮӢж–ӯеұӨгҒ•гҒҲгҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҖҒдҪ•еҮҰгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘең°йңҮгҒҜиө·гҒҚеҫ—гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е°ҶжқҘгӮ’е·ҰеҸігҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘе ҙйқўгҒ§гҖҒж„Ҹе‘ігӮ’дёҺгҒҲз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜеҺҹзҷәгҒ®еҶҚзЁјеғҚгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе ҙйқўгҒ§гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ж”ҝеәңгҒ®еҺҹеӯҗеҠӣиҰҸеҲ¶е§”е“ЎдјҡгҒҜгҖҒеҺҹзҷәгҒ®з«Ӣең°гҒҢжҙ»ж–ӯеұӨгҒ®дёҠгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҶҚзЁјеғҚгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйӣ»еҠӣдјҡзӨҫеҒҙгҒҜгҖҒгҖҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹж–ӯеұӨгҒҜжҙ»ж–ӯеұӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжӨңиЁјгҒ®е ұе‘ҠжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҰгҖҒеҶҚзЁјеғҚгҒ«жҢҒгҒЈгҒҰиЎҢгҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҸҫзҠ¶гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®е·ЁеӨ§ең°йңҮгҒҢгҖҒжҙ»ж–ӯеұӨгҒЁдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒӘгҒ„е ҙжүҖгҒ§иө·гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮ“гҒӘеҹәжә–гӮ„иӯ°и«–гҒ«гҒҜдҪ•гҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒиғҪзҷ»еҚҠеі¶гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®иў«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢеҝ—иіҖеҺҹзҷәгҒ®еҶҚзЁјеғҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҜ©жҹ»гҒ§гҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢиҢ¶з•ӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢж…ӢгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
敬ж„ҸгӮ’гҒҹгҒ©гӮӢгҒЁгҖҒпј’пјҗпј‘пј’е№ҙгҒ“гӮҚгҖҒеҝ—иіҖеҺҹзҷәгҒ®ж•·ең°еҶ…гҒ«жҙ»ж–ӯеұӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁгҒ„гҒҶжҢҮж‘ҳгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӣҪгӮӮжҙ»ж–ӯеұӨгҒЁгҒ®иӘҚиӯҳгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҢ—йҷёйӣ»еҠӣеҒҙгҒҢгҖҒиӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҰгҖҒеҺ»е№ҙгҒ®еҺҹеӯҗеҠӣиҰҸеҲ¶е§”е“ЎдјҡгҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гҒҜеӣҪгҒҢиӘҚгӮҒгҒҹгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒЁгҒ®иӘҚиӯҳгӮ’гҒІгҒЈгҒҸгӮҠиҝ”гҒ—гҖҒгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҶҚзЁјеғҚгҒ®ж–№еҗ‘гҒ«иҲөгӮ’еҲҮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒд»ҠгҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒӘеӨұж…ӢгӮ’зҠҜгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ең°дёӢгҒ®жөҒдҪ“гҒҢж–ӯеұӨгӮ’жҠјгҒ—еәғгҒ’гҒҰгҖҒж–ӯеұӨгҒ®гҒҡгӮҢгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮ’еүҚжҸҗгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒе®ҡзҫ©гҒ®жӣ–жҳ§гҒӘгҖҢжҙ»гҖҚж–ӯеұӨгҒӢеҗҰгҒӢгҒ§гҖҒеҶҚзЁјеғҚгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгӮӮгҒҜгӮ„иҢ¶з•ӘгҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҺҹзҷәиҰҸеҲ¶е§”е“ЎдјҡгҒ®еҜ©жҹ»гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ®ж №жң¬гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еүҚгҒ«гӮӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҺҹзҷәгҒҜгҖҒгҖҢеӢ•гҒӢгҒӘгҒ„пјҲеӢ•гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„пјүж ёе…өеҷЁгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰе®®еҙҺй§ҝзӣЈзқЈгҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮӮеӨҡгҒҸгҒ®еҺҹзҷәгҒҢгҒӮгӮӢж—Ҙжң¬гҒҢжҲҰдәүгҒӘгӮ“гҒӢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеҢ—жңқй®®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁжҲҰдәүгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒеҺҹзҷәгҒ«гғҹгӮөгӮӨгғ«гӮ’ж’ғгҒЎиҫјгӮҖгҒЁжҢ‘зҷәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҲҰдәүгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒгӮӮгҒ—гҖҒдёҮгҒҢдёҖгҒ«гӮӮгҖҒзҰҸеі¶еҺҹзҷәгҒ§иө·гҒҚгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘдәӢж…ӢгҒҢеҶҚгҒіиө·гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®е‘ЁиҫәгҒҢж №гҒ“гҒқгҒҺе»ғеўҹгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒҡгҖҒжң¬еҪ“гҒ«еҸ–гӮҠиҝ”гҒ—гҒ®гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјҲе®ҹйҡӣгҖҒзҰҸеі¶гҒ®зҸҫе®ҹгҒҜеҸ–гӮҠиҝ”гҒ—гҒ®гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
д»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫжө·еә•гҒ®ж–ӯеұӨгҒҢгҒҡгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҝ—иіҖеҺҹзҷәгҒ®зӣҙдёӢгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиҝ‘иҫәгҒ®ж–ӯеұӨгҒҢгҒҡгӮҢгҒҰгҖҒжө·еә•гҒҢж•°гғЎгғјгғҲгғ«гӮӮйҡҶиө·гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒйӣ»жәҗе–ӘеӨұгҒ©гҒ“гӮҚгҒӢгҖҒе»әеұӢгҒҢз ҙеЈҠгҒ•гӮҢгҖҒгғЎгғ«гғҲгғҖгӮҰгғігҒҜеҝ…иҮігҒ гҒЈгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷпјҲеҶҚзЁјеғҚгҒ«еҸҚеҜҫгҒҷгӮӢдәәгҒ®зІҳгӮҠеј·гҒ„йҒӢеӢ•гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеҶҚзЁјеғҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒд»ҠеӣһгҒ®ең°йңҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гӮҲгӮҠйҮҚеӨ§гҒӘиў«е®ігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒ гҒЈгҒҰеҗҰе®ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮ
еҺҹзҷәгҒ®еҶҚзЁјеғҚгҒ§иӯ°и«–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйӣ»жәҗе–ӘеӨұгӮ’йҳІгҒҗдҪ“еҲ¶гҒ®гҒӮгӮӢгҒӘгҒ—гҒ®ж¬Ўе…ғгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиғҪзҷ»еҚҠеі¶гҒ®гҒ»гӮ“гҒ®е°‘гҒ—еҚ—иҘҝеҒҙгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеҺҹзҷәйҠҖеә§гҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ЁеӨ§ең°йңҮгҒҢзӣҙж’ғгҒҷгӮҢгҒ°гҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
й–ўиҘҝеңҸгҖҒеҢ—йҷёеңҸгҒҜеЈҠж»…гҒ®еҚұж©ҹгҒ«зҖ•гҒҷгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгӮүгҖҒжғіеғҸгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§з©әжҒҗгӮҚгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жүҖи©®гҖҒеҺҹеӯҗеҠӣиҰҸеҲ¶е§”е“ЎдјҡгӮӮгҖҒең°йңҮиӘҝжҹ»е§”е“ЎдјҡгӮӮгҖҒеҺҹзҷәгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢд»ҠгҒ®иҮӘж°‘е…ҡж”ҝеәңгҒ®й–ўдҝӮж©ҹй–ўгҒ«гҒҷгҒҺгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е·ЁеӨ§гҒӘйңҮгҒҲгӮӢиҲҢгҒ®дёҠгҒ«д№—гҒЈгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬еҲ—еі¶гҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒгҒ„гҒӨгҒ©гҒ“гҒ§е·ЁеӨ§ең°йңҮгҒ«иҰӢиҲһгӮҸгӮҢгӮӢгҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҖҢжҙ»ж–ӯеұӨгҖҚгҒӘгӮ“гҒҰзҙӣгӮүгӮҸгҒ—гҒ„иЁҖи‘үгҒ§гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒеӣҪж°‘гӮ’ж¬әгҒҸгҒ®гҒҜгӮӮгҒҶгӮ„гӮҒгҒҰгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҺҹзҷәгҒ®зЁјеғҚгӮ’еҒңжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸж–№еҗ‘гҒёгҒЁж”ҝзӯ–и»ўжҸӣгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®иғҪзҷ»еҚҠеі¶ең°йңҮгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮӮгҒҶдёҖгҒӨеј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒең°йңҮгҒҢиө·гҒҚгҒҹеҫҢгҒ®жҸҙеҠ©гҖҒгӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒҢеҰӮдҪ•гҒ«и„ҶејұгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ең°йңҮгҒҢиө·гҒҚгҒҹзӣҙеҫҢгҒ®ж•‘жҸҙжҙ»еӢ•гҒ®еҲқеӢ•гҒ®йҒ…гҒ•гҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӨгғігғ•гғ©гҒҢеЈҠж»…зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒзҸҫең°гҒ§иӢҰгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢйҖЈж—ҘгӮ«гғЎгғ©гҒҢе…ҘгҒЈгҒҰе ұйҒ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒӘгҒңгҒқгӮҢгҒҢжңӘгҒ гҒ«и§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶеӮҷгҒҲгҒ®и„ҶејұгҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ§гҒҷгҖӮ
иғҪзҷ»еҚҠеі¶гҒӢгӮүгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеӨ–гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒ§гҒҜгҖҒдҪ•дәӢгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«дәәгҖ…гҒҜжҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ©гҒ“гҒ«гҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢж—ҘгҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гҖҒд»•дәӢгҒ«иҝҪгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҜиҮҙгҒ—ж–№гҒ®гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒең°йңҮгӮ„жҙӘж°ҙгҒӘгҒ©гҒ®йҮҚеӨ§гҒӘиў«е®ігҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰд»–дәәдәӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒиө·гҒҚгҒҰгҒӢгӮүгҒ®еҜҫеҝңгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒж°ҙгӮ„йЈҹж–ҷгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜдҪҸгӮҖе ҙжүҖгҒ®зўәдҝқгҒ®е•ҸйЎҢгҒӮгҒҹгӮҠгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҒҪе®ігҒҢиө·гҒҚгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҒЈгҒЁеүҚгҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠеәғеҹҹгҒ§еҜҫеҝңгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дәәеҸЈгҒҜгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«жёӣе°‘гҒ—гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒ§йҒҺз–ҺеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ„гҒ–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒз·ҠжҖҘгҒ§йҒҝйӣЈгҒҷгӮӢдәәгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«еҸҜиғҪгҒ гҒ—гҖҒзү№гҒ«гҖҒең°йңҮгӮ„жҙӘж°ҙгҒӘгҒ©гҒ®з”ҡеӨ§гҒӘиў«е®ігҒҜжҜҺе№ҙгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҖҒгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒҚгҒ«дҪ•гҒ®еҪ№гҒ«з«ӢгҒҹгҒҡгҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒӘжҖқжғ‘гҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®гҖҢдҪ•гҒЁгҒӢ委員дјҡгҖҚгҒӘгӮ“гҒӢгӮҲгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгӮ’е„Әе…Ҳзҡ„гҒ«дҪңгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒӮгҖҒиЈҸйҮ‘е·ҘдҪңгҒ§гҖҒеҰӮдҪ•гҒ«гҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ®жҮҗгӮ’жё©гӮҒгӮҲгҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ—гҒӢиҖғгҒҲгҒӘгҒ„гҖҒд»ҠгҒ®дҝқе®Ҳж”ҝе…ҡгҒ®йҖЈдёӯгҒ«гҒҜгҖҒжңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘無駄гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖӮ
ж №жң¬зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгӮ’гҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зӣ®е…ҲгҒ®зөҢжёҲзҡ„еҲ©зӣҠгӮ’е„Әе…ҲгҒ—гҖҒејұиӮүеј·йЈҹгҒ§гҖҒжҗҫеҸ–гҒ•гӮҢгӮӢдәәгҒҢиӢҰгҒ—гӮҖгҒ®гӮ’ж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзӨҫдјҡгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзөҢжёҲзҡ„гҒ«гӮӮжүҖеҫ—гҒ®еҶҚеҲҶй…ҚгҒ§еҒҘе…ЁгҒӘ競дәүзӨҫдјҡгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒ„гҒ–гҒЁгҒӘгӮҢгҒ°еҠ©гҒ‘еҗҲгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе…ұеҠ©гҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’жүӢеҺҡгҒҸгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзӨҫдјҡгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҫҢиҖ…гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶдәәгҒҢеў—гҒҲгҖҒйҒёжҢҷгҒ«иЎҢгҒҚгҖҒеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзӨҫдјҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁеҝғгҒӢгӮүйЎҳгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ