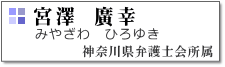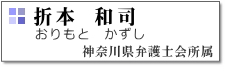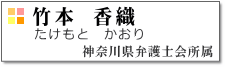дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһйӣўе©ҡдәӢ件гҒЁиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ®гҒҠи©ұ
еүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҜеҘіжҖ§ејҒиӯ·еЈ«гҒҢиӨҮж•°гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйӣўе©ҡдәӢ件гҒ®жҜ”зҺҮгҒҢгӮ„гӮ„й«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒдёҖиЁҖгҒ§йӣўе©ҡдәӢ件гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘдәүзӮ№гҒҜеӨҡзЁ®еӨҡж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
еӯҗдҫӣгҒ®иҰӘжЁ©гӮ„йӨҠиӮІиІ»гҒӮгҒҹгӮҠгҒҢдё»иҰҒгҒӘдәүзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдёҚиІһгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮӢж…°и¬қж–ҷгҒ®еӯҳеҗҰгҒҢдәүзӮ№гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒй–ўйҖЈдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе©ҡ姻費用пјҲз”ҹжҙ»иІ»пјүгӮ„йқўдјҡдәӨжөҒгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’гҖҒиӘҝеҒңгӮ„еҜ©еҲӨгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®йӣўе©ҡдәӢ件гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘдәүзӮ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгҒ®гҒҢиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒҜгҖҒеӨ«е©ҰгҒ§еҪўжҲҗгҒ—гҒҹе…ұжңүиІЎз”ЈгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲҶгҒ‘гӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ«е©ҰгҒ®е…ұжңүиІЎз”ЈгҒ®еӯҳеҗҰгҖҒеҶ…е®№гӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҷӮгҒ«йқһеёёгҒ«еҺ„д»ӢгҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеӨ«е©ҰгҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгҖҒзүҮж–№гҒҢиІЎз”ЈгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзөҗж§ӢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгӮӮгҒҶзүҮж–№гҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиІЎз”ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҫҖгҖ…гҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®еҚ”иӯ°гӮ„иӘҝеҒңгҒ®е ҙгҒ§гҖҒеҲҶдёҺгҒ«еҝңгҒҳгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„еҒҙгҒҢгҖҒеӯҳеңЁгҒҷгӮӢе…ұжңүиІЎз”ЈгӮ’жӯЈзӣҙгҒ«й–ӢзӨәгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹе ҙйқўгҒ§гҖҒиІЎз”ЈеҲҶдёҺгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеҒҙгҒҢгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁе…ұжңүиІЎз”ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒзӣёжүӢж–№гҒҢгҖҒгӮӮгҒҶгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒ„ејөгӮӢгҒЁгҖҒж°ҙжҺӣгҒ‘и«–гҒ«гҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүӢз¶ҡгҒ§гҒҜгҖҒеҲҶдёҺгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеҒҙгҒ«дё»ејөз«ӢиЁјиІ¬д»»гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒйҡ гҒ•гӮҢгҒҹе…ұжңүиІЎз”ЈгҒ®еӯҳеңЁгҖҒеҶ…е®№гӮ’иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒеҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®е…ұжңүиІЎз”ЈгӮ’гҖҒйҡ гҒ—гҒҹеҒҙгҒҢзӢ¬гӮҠеҚ гӮҒгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶдёҚе…¬жӯЈгҒӘзөҗжһңгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒиЈҒеҲӨжүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒ®з”із«ӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–№жі•гҒ§гҖҒзӣёжүӢж–№еҗҚзҫ©гҒ®йҠҖиЎҢй җйҮ‘гӮ„иЁјеҲёеҸ–еј•гҖҒз”ҹе‘ҪдҝқйҷәзӯүгҒ®й–ӢзӨәгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гӮ’еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘеүҚжүұгҒЈгҒҹдәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒиЁҙиЁҹжҸҗиө·жҷӮзӮ№гҒ§гҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиІЎз”ЈгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдёҖж–№й…ҚеҒ¶иҖ…гҒ«йҡ гҒ—иІЎз”ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒЁгҒ®иҰӢиҫјгҒҝгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒиӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒ®з”із«ӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒпј“пјҗпјҗпјҗдёҮеҶҶиҝ‘гҒ„йҡ гҒ—й җйҮ‘гҒ®еӯҳеңЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰиҰӢиҫјгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒӮгҒҰгҒҡгҒЈгҒҪгҒҶгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиӘҚгӮҒгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮӮйҷҗз•ҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲи©ұгҒ—еҗҲгҒ„гғҷгғјгӮ№гҒ®иӘҝеҒңгҒ§гҒҷгҒЁгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиӘҝеҒңгӮ„иЈҒеҲӨгҒ®жүӢз¶ҡгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҖҒдҪ•гҒӢгҒЁйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«гҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еүҚгҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҖҒгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§дёӢиӘҝгҒ№гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒӮгҖҒдҪ•дәӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдёӢжә–еӮҷгҒҢеӨ§еҲҮгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҜйӣўе©ҡдәӢ件гҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гҖҒзӣёи«ҮиҖ…гҒҢгҖҒеӨ«е©ҰгҒ®е…ұжңүиІЎз”ЈгҒҢгҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒӮгӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲпјҲеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҒҜеҘіжҖ§гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҒ«гҒҜгҖҒйӣўе©ҡеҚ”иӯ°гӮ’гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ•гҒӣгӮӢеүҚгҒ«гҖҒзӣёжүӢж–№гҒҢдҝқжңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй җиІҜйҮ‘гҖҒж ӘгҖҒз”ҹе‘ҪдҝқйҷәгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиіҮз”ЈгҒ®еӯҳеңЁгҒ®иЈҸд»ҳгҒ‘гҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйҖҡеёігҖҒиЁјеҲёгҖҒйҮ‘иһҚж©ҹй–ўгҒӢгӮүгҒ®жүӢзҙҷгҖҒгҒҜгҒҢгҒҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҖҒиҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹгӮүеҝ…гҒҡгӮігғ”гғјгҒӢеҶҷзңҹгӮ’ж’®гҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгӮҲгҒҶжҢҮзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘жүұгҒЈгҒҹдәӢ件гҒ§гӮӮгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ«гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҢҮзӨәгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиіҮж–ҷгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®иӘҝеҒңжүӢз¶ҡгҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ«зӣёжүӢж–№гҒҢй–ӢзӨәгҒ—гҒҹйҮ‘иһҚиіҮз”ЈгҒЁгҖҒдәӢеүҚгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҹиіҮж–ҷгӮ’з…§еҗҲгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®жјҸгӮҢгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒзӣёжүӢж–№гӮӮжёӢгҖ…гҒӘгҒҢгӮүй–ӢзӨәгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜпј’пјҗпјҗпјҗдёҮеҶҶгҒ»гҒ©е…ұжңүиІЎз”ЈгҒҢеў—гҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒиӘҝеҒңгҒ§зӣёжүӢж–№гӮӮиҝҪеҠ гҒ®й–ӢзӨәгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»®гҒ«зӣёжүӢж–№гҒҢиҝҪеҠ гҒ®й–ӢзӨәгҒ«еҝңгҒҳгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨгҒ®дёӯгҒ§гҖҒе…ҲгҒ»гҒ©з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹиӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒ®жүӢз¶ҡгӮ’еҸ–гӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖе®ҡгҒ®иЈҸд»ҳгҒ‘иіҮж–ҷгҒ•гҒҲгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгӮӮиӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣўе©ҡгҒҜдәәз”ҹгҒ®еҶҚеҮәзҷәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜзөҢжёҲзҡ„гҒӘе®үеҝғгӮӮеҝ…иҰҒгҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
еӨ«е©ҰгҒ§еҪўжҲҗгҒ—гҒҹиІЎз”ЈгҒ®еҲҶдёҺгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжӯЈеҪ“гҒӘжЁ©еҲ©гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒеӨҡе°‘гҒӘгӮҠеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһгҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹгҖҢйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҖҚгҒ®ж”№гҒ–гӮ“ж–№жі•
гғҶгғ¬гғ“жңқж—ҘгҒ§гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ®гғӘгғЎгӮӨгӮҜзүҲгҒҢж”ҫжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒігҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒиЁҖгӮҸгҒҡгҒЁзҹҘгӮҢгҒҹеұұеҙҺиұҠеӯҗеҺҹдҪңгҒ®еҗҚдҪңеҢ»зҷӮгғүгғ©гғһгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҺҹдҪңгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒҜгӮӢгҒӢжҳ”гҒ®жҳӯе’ҢгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҺҹдҪңгӮ’еҝ е®ҹгҒ«жҸҸгҒ‘гҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁзӯүгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гғӘгғЎгӮӨгӮҜзүҲгҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҹгӮўгғ¬гғігӮёгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ§еӯҰз—…йҷўгҒҢиҲһеҸ°гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢеҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгғүгғ©гғһгҒ®дёӯгҒ§гҒӢгҒӘгӮҠйҮҚиҰҒгҒӘдҪҝгӮҸгӮҢж–№гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӢгҒ„гҒӨгҒҫгӮ“гҒ§жӣёгҒҸгҒЁгҖҒдё»дәәе…¬гҒ®иІЎеүҚеҢ»её«гҒҢеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҖҒйғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒ«еҸЈиЈҸеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’жҢҮзӨәгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹжүӢиЎ“иЁҳйҢІгҒҢж”№гҒ–гӮ“гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒ®ж–№жі•гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸдёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҒ гҒЁдҪ•гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’жӮӘз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ®дёӯгҒ§жӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹж”№гҒ–гӮ“жүӢжі•гҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢдёҖгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒігҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ«гғ«гғҶгҒ®ж”№гҒ–гӮ“ж–№жі•гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶдёҠгҒ«йғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒҢжӣёгҒ„гҒҹжүӢиЎ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳијүгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«дёҚеҲ©гҒӘеҶ…е®№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиЁҳијүгҒ—гҒҹеҢ»её«гӮ’иІЎеүҚеҢ»её«гҒҢе‘јгҒігҒӨгҒ‘гҖҒгҒқгҒ®иЁҳијүгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®гҖҢд»®зҷ»йҢІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж®өйҡҺгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҖҢд»®зҷ»йҢІгҒӘгӮүгҖҒжӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҢеҸҜиғҪгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ®иЁҳиҝ°гҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲпјҲж”№гҒ–гӮ“пјүгӮ’иҝ«гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
йғЁдёӢгҒ®еҢ»её«гҒҜгҖҒиӢҰжӮ©гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®жҢҮзӨәгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒдёҚеҲ©гҒӘиЁҳијүгӮ’жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒзңҹзӣёгҒ®и§ЈжҳҺгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§дёҚйғҪеҗҲгҒӘиЁҳдәӢгӮ’жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢзӮәгҒҢгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢдёҖгҒ®жүӢеҸЈгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЁҳдәӢгӮ’йҖ”дёӯгҒҫгҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ«жӣёгҒҚи¶ігҒ—гҒҹгӮҠгҖҒиЁӮжӯЈгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒжҖҘгҒ«еҲҘгҒ®жӮЈиҖ…еҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ—гҒҰгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮе…ЁеҗҰе®ҡгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢд»®зҷ»йҢІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжүӢжі•гӮ’жӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жӣҙж–°еұҘжӯҙгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒд»®зҷ»йҢІдёӯгҒ«жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒеүҠйҷӨгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹиЁҳијүгҒҢгҖҒжӣҙж–°еұҘжӯҙдёӯгҒ«гҒҜеҮәгҒҰжқҘгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒе…ғгҖ…дҪ•гҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдәӢж•…гҒ§дҪ•гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гҖҢжң¬зҷ»йҢІгҖҚгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжӣҙж–°еұҘжӯҙгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӨңиЁјгҒҢеҸҜиғҪгҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒд»®зҷ»йҢІдёӯгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёи§ЈжҳҺгӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚеӨ§гҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҷгғігғҖгғјгҒ«гӮҲгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮӮгҒ—гҒҡгҒЈгҒЁд»®зҷ»йҢІгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒдәӢж•…еҫҢгҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮж”№гҒ–гӮ“гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜгҒқгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒд»®зҷ»йҢІгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёгӮ’йҡ гҒәгҒ„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҡ гӮҢи“‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®з–‘еҝөгӮ’жҠұгҒӢгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гғүгғ©гғһгҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®гӮ«гғ«гғҶж”№гҒ–гӮ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨгӮ·гғјгғігҒ§еҢ»зҷӮеҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ—гҒҹиЁјжӢ гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁеҸҚи«–гҒ—гҖҒж”№гҒ–гӮ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹжҳҺзҷҪгҒӘиЁјжӢ гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гӮҶгҒ гҒӯгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гғјгғігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁз•°и«–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒҜжӣҙж–°еұҘжӯҙдёҠгҒ«гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиЎЁгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№дёҠгҒ§гҒҜгҖҒд»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“еүҚеҫҢгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®жҷӮеҲ»гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰиЁҳйҢІгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ—гҒӨгҒ“гҒҸжұӮгӮҒгҒҹзөҗжһңгҖҒгҒӮгҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®з—•и·ЎгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®д»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж”№гҒ–гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢз«Ӣе ҙгҒ«з«ӢгҒҰгҒ°гҖҒйқһеёёгҒ«з”ұгҖ…гҒ—гҒҚе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҢзҷҪгҒ„е·ЁеЎ”гҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жӮӘиіӘгҒӘжүӢеҸЈгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ«иӘҚзҹҘгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶеҸҚйқўгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҒ«гҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§гҒ“гҒ®жүӢжі•гҒҢжЁӘиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒйқһеёёгҒ«гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹиЁҳдәӢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гӮӮжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢзңҹжӯЈжҖ§гҖҚгҖҢиҰӢиӘӯжҖ§гҖҚгҖҢдҝқеӯҳжҖ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёүеҺҹеүҮгҒҢзӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и©ізҙ°гҒҜгҒқгҒЎгӮүгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҰҒгҒҜгҖҒеҫҢгҒ§гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжӨңиЁјгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘд»•зө„гҒҝгҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®д»®зҷ»йҢІж®өйҡҺгҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒҜгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ“гҒ®дёүеҺҹеүҮгӮ’йҖёи„ұгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—©гҒ„и©ұгҖҒд»®зҷ»йҢІгҒЁгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгҒҜгҒ•гҒЈгҒ•гҒЁз„ЎгҒҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
еҢ»зҷӮиҖ…гҒҜгҖҒиЁҳијүйҖ”дёӯгҒ§гӮӮгҖҒз·ҠжҖҘеҜҫеҝңгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒиЁҳијүйҖ”дёӯгҒ§гӮӮгҖҒжң¬зҷ»йҢІгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҠ зӯҶиЁӮжӯЈгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгӮүгҖҒжӣҙж–°гҒҷгӮҢгҒ°и¶ігӮҠгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫе ҙгҒ§гҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒдәӢж•…гҒ®жӨңиЁјгҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгҒ—гӮҚгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰгғүгғ©гғһгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҖҒ公然гҒЁгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж”№гҒ–гӮ“гҒ®ж–№жі•гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеӣҪж°‘гҒ®еҒҘеә·гҖҒз”ҹе‘ҪгҒ«гҒӨгҒҚиІ¬д»»гӮ’иІ гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҺҡеҠҙзңҒгҒҢзҺҮе…ҲгҒ—гҒҰйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®ж¬ йҷҘгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжҠңжң¬зҡ„гҒӘж”№е–„гӮ’зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжүӢгӮ’жү“гҒӨгҒ№гҒҚгҒ гҒЁеј·гҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғүгғ©гғһгҒ«й–ўгҒҷгӮӢж„ҹжғігҒҜгҒқгҒЈгҒЎгҒ®гҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«иҲҲе‘іж·ұгҒҸй‘‘иіһгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҖҢгӮ«гғ«гғҶиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®дҪ“йЁ“и«ҮгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҖҚгҒқгҒ®пј‘
д»Ҡе№ҙгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«гӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’пј“еӣһе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҶ…1件гҒҜгҖҒеҖӢдәәеҢ»гҒ§гҖҒгӮ«гғ«гғҶгӮӮйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҙҷгӮ«гғ«гғҶгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»–гҒ®пј’件гҒҜйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮгҖҒе№ҫеәҰгҒӢйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒдҝқе…ЁгҒ®жүӢз¶ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиЁҳдәӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ«зҸҫе ҙгӮ’иёҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«и©ігҒ—гҒ„ејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮӮиЈңеҠ©иҖ…пјҲгӮ«гғЎгғ©гғһгғіпјүгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзҸҫе ҙгҒ§гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘжүӢз¶ҡгҒ®йҖІгӮҒж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜжҰӮгҒӯжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҒ„гҒ–иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®зҸҫе ҙгҒ«иЎҢгҒҸгҒЁжғіе®ҡеӨ–гҒ®еҮәжқҘдәӢгҒҢиө·гҒҚгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ®дёӯгҒ§иө·гҒҚгҒҹгҖҢгҒҲгҒЈпјҹгҖҚгҒЁжҖқгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеҮәжқҘдәӢгҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹдәҲжңҹгҒӣгҒ¬дәӢж…ӢгҒ«йҒӯйҒҮгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒ©гҒҶеҜҫеҮҰгҒ—гҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒд»ҠеҫҢгҖҒжҠҳгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҸҫе ҙгҒ§гҒ®дҪ“йЁ“и«ҮгҒҜгҖҒгҖҢеӨӘйҷҪгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«ж–°гҒ—гҒҚгӮӮгҒ®гҒӘгҒ—гҖҚгҒ§гҖҒгҒҠеҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠиӘӯгҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒҜдҪ•гҒӢгҒ®еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҒҜгҒқгҒ®з¬¬пј‘еӣһзӣ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӨгҒ„жңҖиҝ‘е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹгҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеҶ…гҒ®гҒӮгӮӢз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ§гҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ§й©ҡгҒ„гҒҹгҖҒгҒЁгҒӮгӮӢдҪ“йЁ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢжЎҲгҒҜгҖҒиӮәзӮҺз–‘гҒ„гҒ§е…ҘйҷўгҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҠңжӯҜеҫҢгҒ®е®№ж…ӢжҖҘеӨүгҒӢгӮүгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒдәӢжЎҲгҒ®и©ізҙ°гӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе·®гҒ—жҺ§гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҪ“然гҖҒе‘јеҗёеҷЁзі»гҒ®еҶ…科гҒЁжӯҜ科гҒ®гӮ«гғ«гғҶгҒӘгҒ©гҒҢдҝқе…ЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁеҪ“ж—ҘгҖҒз—…йҷўгҒ«иөҙгҒҸгҒЁгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠз—…йҷўгҒ®дәӢеӢҷеұҖжӢ…еҪ“иҖ…гҒӢгӮүгҖҢжӯҜ科гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҗҢгҒҳз—…йҷўеҶ…гҒ«гҒҜгҒӮгӮӢгҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒгҒҶгҒЎгҒ®еҢ»зҷӮжі•дәәгҒ®зөҢе–¶гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе ҙжүҖгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§еҖӢдәәгҒ®жӯҜ科еҢ»гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘ¬жҳҺгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зҷәиЁҖгӮ’иҒһгҒ„гҒҰдёҖзһ¬иҖігӮ’з–‘гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁжүӢз¶ҡзҡ„гҒ«гҒҜеҺ„д»ӢгҒӘе•ҸйЎҢгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®зӣёжүӢж–№гҒЁжғіе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜз—…йҷўгӮ’зөҢе–¶гҒҷгӮӢеҢ»зҷӮжі•дәәгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдҝқе…ЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгӮ«гғ«гғҶгӮӮгҖҒеҺҹеүҮзҡ„гҒ«гҒҜзӣёжүӢж–№гҒ§гҒӮгӮӢеҢ»зҷӮжі•дәәгҒҢдҝқз®ЎгҒҷгӮӢгӮ«гғ«гғҶгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјҲдҫӢеӨ–гӮӮгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзөҗж§ӢйқўеҖ’гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
жЎҲгҒ®е®ҡгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢгҖҒгҖҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒжӯҜ科гҒ®гӮ«гғ«гғҶгҒҜдҝқе…ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖҚгҒЁе‘ҹгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§гҖҒзӣёжүӢж–№гҒҢд»»ж„ҸгҒ§жҸҗеҮәгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒҸгӮҢгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҢд»»ж„ҸгҒ®й–ӢзӨәгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӣёжүӢж–№гҒҢй–ӢзӨәгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜдҝқе…ЁгҒ®еҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
й©ҡгҒ„гҒҹз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§гҒҷгҒҗз—…йҷўгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гҒ©гҒ“гӮ’иҰӢгҒҰгӮӮгҖҒжӯҜ科гҒ®зөҢе–¶дё»дҪ“гҒҢеҲҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ®иЁҳијүгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйҖҶгҒ«гҖҒз—…йҷўеҶ…гҒ®дёҖ科зӣ®гҒЁгҒ—гҒҰд»–гҒ®иЁәзҷӮ科зӣ®гҒЁеҗҢгҒҳеҖӢжүҖгҒ«зҫ…еҲ—гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжӯҜ科гҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•гӮӮд»–гҒ®иЁәзҷӮ科зӣ®гҒЁеҗҢж§ҳгҒ®дҪ“иЈҒгҒ§иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ«гҒқгҒ®гғҡгғјгӮёгӮ’зӨәгҒ—гҖҒгҖҢгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеӨ–иҰігҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжі•зҡ„гҒ«еҲҘдәәж јгҒЁдё»ејөгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиЁұгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁиҖіжү“гҒЎгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨе®ҳгӮӮгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®дҪ“иЈҒгҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰзҙҚеҫ—гҒҜгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒ®еҮәж–№гҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзү№гҒ«зөҗи«–гӮҒгҒ„гҒҹзҷәиЁҖгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгӮӮгҖҒгҖҢгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸжӯҜ科гҒ®гӮ«гғ«гғҶгӮӮеҮәгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҚгҒЁзҷәиЁҖгҒ—гҖҒз—…йҷўеҒҙгҒ«й–ӢзӨәгӮ’дҝғгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒз—…йҷўеҒҙгӮӮгҖҒз•°и«–гӮ’гҒҜгҒ•гӮҖгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸжӯҜ科гҒ®гӮ«гғ«гғҶгӮ’й–ӢзӨәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜдәӢгҒӘгҒҚгӮ’еҫ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҠгӮҲгҒқдәҲжңҹгҒӣгҒ¬еұ•й–ӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”із«ӢгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒӨгӮӮж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰгҖҒдҝқе…ЁгҒ®зӣёжүӢж–№гҒ®зү№е®ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҫ№еә•гҒ—гҒҰжӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁз—ӣж„ҹгҒ—гҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
зӣёжүӢж–№гҒ®зү№е®ҡгҒ§жӮ©гӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒҜд»ҘеүҚгҒ«гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒй–“йҒ•гҒҲгӮӢгҒЁиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҢз©әжҢҜгӮҠгҒЁгҒӘгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҸгӮҢгҒҗгӮҢгӮӮгҖҢиҰҒжіЁж„ҸгҖҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж—ҘгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҖҢгҒҲгҒЈпјҹгҖҚгҒЁй©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒҫгҒҹеҲҘгҒ®ж©ҹдјҡгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еІЎжң¬з§Җйӣ„ејҒиӯ·еЈ«еҠ е…ҘгҒ®гҒ”е ұе‘Ҡ
еҪ“и‘өжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§з”·жҖ§ејҒиӯ·еЈ«2еҗҚгҖҒеҘіжҖ§ејҒиӯ·еЈ«2еҗҚгҒ§жҙ»еӢ•гҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еәҰгҖҒеҪ“ејҒиӯ·еЈ«дјҡгҒ®дјҡй•·гҒӘгҒ©гҒ®иҰҒиҒ·гӮ’жӯҙд»»гҒ•гӮҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«жӯҙ47е№ҙзӣ®гӮ’иҝҺгҒҲгӮӢеІЎжң¬з§Җйӣ„ејҒиӯ·еЈ«гӮ’ж–°гғЎгғігғҗгғјгҒЁгҒ—гҒҰиҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ”е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еІЎжң¬з§Җйӣ„ејҒиӯ·еЈ«гҒҜгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®жҠҳжң¬гҒҢејҒиӯ·еЈ«зҷ»йҢІгӮ’гҒ—гҒҹжҷӮгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҖҒеҲқжӯ©гҒӢгӮүгҒ”жҢҮе°ҺгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҒ©дәәгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒе®®жҫӨгҒЁгӮӮгҒ©гӮӮй•·гҒҸгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰиұҠгҒӢгҒӘзөҢйЁ“гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒдәәж јиӯҳиҰӢгҒЁгӮӮйқһеёёгҒ«е„ӘгӮҢгҒҹеІЎжң¬з§Җйӣ„ејҒиӯ·еЈ«гӮ’еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«иҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»ҠеҫҢгҖҒгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷеӨҡж§ҳеҢ–гҒҷгӮӢдҫқй јиҖ…гҖҒгҒ”зӣёи«ҮиҖ…гҒ®ж–№гҖ…гҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠдёҖеұӨеҝңгҒҲгҒҰиЎҢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеӢҷжүҖгҒ®ж—ўеӯҳгғЎгғігғҗгғјгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝғеј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢжүҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеҫҢгҒЁгӮӮгҖҒеј•гҒҚз¶ҡгҒҚгҖҒгҒ”жҢҮе°ҺгҒ”йһӯж’»гҒ®гҒ»гҒ©гҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖи‘өжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖејҒиӯ·еЈ«гҖҖе®®жҫӨе»Је№ё
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖејҒиӯ·еЈ«гҖҖжҠҳжң¬е’ҢеҸё
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖејҒиӯ·еЈ«гҖҖзҷҪдә•зҹҘзҫҺ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖејҒиӯ·еЈ«гҖҖз«№жң¬йҰҷз№”
гҒ”жҢЁжӢ¶
ејҒиӯ·еЈ«гҒ®еІЎжң¬з§Җйӣ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҹгҒігҖҒзёҒгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒи‘өжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ«зұҚгӮ’зҪ®гҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®®жҫӨе»Је№ёејҒиӯ·еЈ«гҒҜдҝ®зҝ’з”ҹгҒ®й ғгҒӢгӮүгҖҒжҠҳжң¬е’ҢеҸёејҒиӯ·еЈ«гҒҜејҒиӯ·еЈ«зҷ»йҢІгҒ®жҷӮгҒӢгӮүгҒ®гҒҠд»ҳгҒҚеҗҲгҒ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҗҢгҒҳдәӢеӢҷжүҖгҒ§еҹ·еӢҷгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§дёҚжҖқиӯ°гҒӘзёҒгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒй•·гҒҚгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒеІЎжң¬жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҹ·еӢҷгҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ47е№ҙй–“гҒ«еҹ№гҒЈгҒҹејҒиӯ·еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®зөҢйЁ“гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒгҒҫгҒҹеҝғж©ҹдёҖи»ўгҖҒж–°гҒ—гҒ„жҘӯеӢҷгҒ«гӮӮеҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҫгҒ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁжұәж„ҸгӮ’ж–°гҒҹгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒз§ҒгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«жҘӯеӢҷгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҸгӮҢгҒҰжқҘгҒҹеҸӨиҘҝйҒ”еӨ«ејҒиӯ·еЈ«гҒЁжңүйҰ¬еӨ§зҘҗејҒиӯ·еЈ«гҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒ«гҖҒгҖҢеҸӨиҘҝжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҖҚгӮ’гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҖҢеҸӨиҘҝжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҖҚгҒ«гҒӨгҒҚгҒҫгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеј•гҒҚз¶ҡгҒҚгҒ”ж„ӣйЎ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгӮҲгҒҶгҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖејҒиӯ·еЈ«гҖҖеІЎжң¬з§Җйӣ„
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұпҪһеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ®дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒӨгҒ„е…Ҳж—ҘгҖҒпј’жӯігҒ®еӯҗдҫӣгҒ®иҷ«жӯҜжІ»зҷӮгҒ§гҖҒжӯҜ科еҢ»её«гҒҢжӯҜиҢҺгҒ«гғӘгғүгӮ«гӮӨгғігҒЁгҒ„гҒҶеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе°„гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒз—ҷж”ЈгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҖҒдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ӣгҒҫгҒ—гҒ„дәӢж•…гҒ®е ұйҒ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒ»гҒјеҗҢдёҖеҶ…е®№гҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҸҫеңЁиЁҙиЁҹдҝӮеұһдёӯгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гӮ„дёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҒёгҒ®жіЁж„Ҹе–ҡиө·гҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮиҫјгӮҒгҒҰгҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж•…гҒ®дәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒҜгҖҒжҰӮз•Ҙд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
иӢҘгҒ„з”·жҖ§жӮЈиҖ…гҒҢиӮ©еҮқгӮҠгҒ®жІ»зҷӮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иЎҢгҒҚгҒӨгҒ‘гҒ®ж•ҙеҪўеӨ–科гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ«иЎҢгҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҖҒйҰ–гҒӢгӮүиғҢдёӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰеұҖжүҖйә»й…”и–¬гғӘгғүгӮ«гӮӨгғігӮ’жіЁе°„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зӣҙеҫҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҜеҢ»её«гҒ®зӣ®гҒ®еүҚгҒ§ж„ҸиӯҳгӮ’ж¶ҲеӨұгҒ—гҖҒеҝғеҒңжӯўгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҜгҖҒеҗҢгҒҳиЎҢж”ҝеҢәеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢеӨ§еӯҰз—…йҷўгҒ«ж•‘жҖҘжҗ¬йҖҒгҒ•гӮҢгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“иҳҮз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«йҮҚзҜӨгҒӘдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзөҗеұҖдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғӢгғҘгғјгӮ№е ұйҒ“гҒ•гӮҢгҒҹдәӢж•…гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒжӯҜ科еҢ»гҒЁж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®йҒ•гҒ„гҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®зӮ№гҒҜйқһеёёгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒ§ж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®еҢ»её«гҒҢиЎҢгҒЈгҒҹжіЁе°„гҒҜгҖҒең§з—ӣзӮ№гҒ«еұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе…ҘгҒҷгӮӢгғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгӮ„ж•ҙеҪўеӨ–科гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжіЁе°„гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’и„ігҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеӢ•и„ҲгҒ«иӘӨжіЁе…ҘгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒжҖҘжҝҖгҒӘж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҖҒеҝғеҒңжӯўгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҜҫеҮҰгӮ’иӘӨгӮӢгҒЁе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдәӢж•…гҒ®зҷәз”ҹгӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҢгҒҫгҒҡйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒз©ҝеҲәеҫҢгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе…ҘгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҖҒгғҗгғғгӮҜгғ•гғӯгғјгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжіЁе°„йҮқгӮ’гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“еј•гҒҚжҲ»гҒ—гҖҒиЎҖгҒҢж··гҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢжүӢжҠҖгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢпјҲиЎҖгҒҢж··гҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°жіЁе°„йҮқгҒҜиЎҖз®ЎеҶ…гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’е°‘йҮҸгҒҡгҒӨе…ҘгӮҢгҒӘгҒҢгӮүж§ҳеӯҗгҒ®еӨүеҢ–гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢпјҲз—ҮзҠ¶гҒҜжҖҘжҝҖгҒ«еҮәгҒҰжқҘгҒҫгҒҷпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж…ҺйҮҚгҒӘжүӢй ҶгӮ’иёҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҮдёҖдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҰгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®е®№ж…ӢгҒҢжҖҘеӨүгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»ҠеәҰгҒҜж…ҢгҒҰгҒҡгҒ«йҖҹгӮ„гҒӢгҒӘж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гӮ’еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮиӮқиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҖҘеӨүгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®е…·дҪ“зҡ„еҜҫеҮҰгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеј•гҒҚйҮ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒ®иЎҖдёӯжҝғеәҰгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҮҰзҪ®гӮӮеҝ…иҰҒгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢеҝғеҒңжӯўгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮе„Әе…ҲгҒ—гҒҰе®ҹж–ҪгҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒиғёйӘЁең§иҝ«гҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғіжҠ•дёҺгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж•‘жҖҘиҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дәәй–“гҒ®дҪ“гҒ§гҒҜи„ігҒҢй…ёзҙ гҒ®пј”еүІгӮ’ж¶ҲиІ»гҒ—гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒи„ігҒёгҒ®й…ёзҙ дҫӣзөҰгҒҢдёҖе®ҡжҷӮй–“д»ҘдёҠйҖ”зө¶гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒи„ігҒ«йҡңе®ігҒҢж®ӢгӮҠгҖҒдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҹгҒ гҒЎгҒ«и„ігҒёгҒ®й…ёзҙ дҫӣзөҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жүӢжҠҖгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзӣёи«ҮгҒ—гҒҹгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒҢзөҢйЁ“и«ҮгҒЁгҒ—гҒҰиӘһгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҖҒеұҖжүҖйә»й…”дёӯжҜ’гҒ«гӮҲгӮӢеҝғеҒңжӯўгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«иғёйӘЁең§иҝ«гҖҒдәәе·Ҙе‘јеҗёгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғіжҠ•дёҺзӯүгҒ®иҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒЁжҖҘйҖҹгҒӘијёж¶ІзӯүгӮ’иЎҢгҒҲгҒ°гҖҒжӮЈиҖ…гҒҜгҖҒгҒ»гҒ©гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒЈгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҒҷгӮ“гҒӘгӮҠгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§дҪ•дәӢгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«зӣ®иҰҡгӮҒгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгӮӮгҖҒд»ҠеӣһгҒ®е ұйҒ“гҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ж—ҘеёёгҒ®иЁәзҷӮгҒ®й ҳеҹҹгҒҢгҖҒе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гӮ„еёӮдёӯгҒ®гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ§гҒ®дәӢж•…гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§е…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ«жӮЈиҖ…гҒҢзӣ®гҒ®еүҚгҒ§еҝғеҒңжӯўгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјҲе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҒқгҒҶгҒ§гҒҷпјүгҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒҜгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢеҢ»её«гҒ«дҪҝз”Ёжі•гӮ’иӘӨгӮӢгҒЁе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢи–¬еүӨгӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҚұж©ҹж„ҹгҒҢд№ҸгҒ—гҒ„еҢ»её«гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’йқһеёёгҒ«еҚұжғ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁи©ұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж•…гӮ„д»ҠеӣһгҒ®е ұйҒ“гҒ®дәӢж•…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒ®жҠ•дёҺгҒ«гҒҜе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢдәӢж…ӢгӮ’жӢӣгҒҸгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеҶ…еңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’йә»й…”еҮҰзҪ®гӮ„зҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжІ»зҷӮгҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж—Ҙеёёзҡ„гҒ«дҪҝгҒҶеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮж…ҺйҮҚгҒӘжүӢжҠҖгҒ®гғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҒ®еҫ№еә•гҒЁгҖҒж•‘е‘ҪиҳҮз”ҹгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢдәӢж…ӢгҒёгҒ®еӮҷгҒҲгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гҒ®е‘ҪгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӮҷгҒҲгӮ„еҚұж©ҹж„ҸиӯҳгҒҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒе®үжҳ“гҒ«еұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе®ҹж…ӢгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ§гӮӮгҖҒж•ҙеҪўеӨ–科еҢ»гҒҜгҖҒж•‘е‘ҪиҳҮз”ҹгҒ®з¬¬дёҖйҒёжҠһи–¬гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігӮ’еёёеӮҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҝғеҒңжӯўеҫҢгҖҒгҒӘгҒңгҒӢгҒқгӮҢгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігҒ«гҒҜеҝғжӢҚгӮ’еў—еј·гҒ—гҖҒжң«жўўгҒ®иЎҖз®ЎгӮ’з· гӮҒгӮӢдҪңз”Ёж©ҹеәҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒи„ігҒӘгҒ©гҒ®дё»иҰҒиҮ“еҷЁгҒёгҒ®иЎҖж¶ІеҫӘз’°пјҲгҒӨгҒҫгӮҠй…ёзҙ дҫӣзөҰпјүгҒҢе„Әе…Ҳзҡ„гҒ«зўәдҝқгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒҜгҖҒж•‘жҖҘйҡҠе“ЎгҒ§гӮӮжҠ•дёҺеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨгҒ®еүҚгҒ«дәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹж•ҙеҪўеӨ–科еҢ»гҒ«дјҡгҒЈгҒҹжҷӮгҖҒгӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғігӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе°ӢгҒӯгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢиЎҖжөҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиғёйӘЁең§иҝ«гӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢж„Ҹе‘ігҒҷгӮүгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иғёйӘЁең§иҝ«гӮ„дәәе·Ҙе‘јеҗёзӯүгҒҜгҖҒгҖҢж•‘жҖҘиҳҮз”ҹгҒ®пјЎпјўпјЈгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒеӨ§еӯҰгӮ„иҮЁеәҠгҒ®е®ҹзҝ’гҒ§еӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒ®гҒ”гҒҸеҲқжӯ©зҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҷгӮүзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҢ»её«гҒҢеҝғеҒңжӯўгҒ®еҚұйҷәгӮ’еӯ•гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’гҒ”гҒҸж—Ҙеёёзҡ„гҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫзҠ¶гҒ«гҒҜз©әжҒҗгӮҚгҒ—гҒ•гҒҷгӮүж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠгӮҲгҒқе‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ®гҖҒгҖҢиӮ©еҮқгӮҠгҖҚгӮ„гҖҢиҷ«жӯҜгҖҚгҒ®жІ»зҷӮгҒ§гҒӘгҒңеӨ§еҲҮгҒӘе‘ҪгҒҢеҘӘгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹжӮЈиҖ…гӮ„гҒқгҒ®гҒ”йҒәж—ҸгҒ®з„ЎеҝөгҒ•гӮ’жҖқгҒҶгҒЁгҖҒж•‘жҖҘиҳҮз”ҹеҮҰзҪ®гҒҷгӮүгҒҫгҒЁгӮӮгҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»её«гҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жүұгҒҶиіҮж јгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒҷгӮүжҖқгӮҸгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒ®йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒҜеӨ§дёҲеӨ«гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
еҢ»зҷӮиҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰдёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжіЁж„Ҹе–ҡиө·гӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иЁҳдәӢгӮ’жӣёгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ