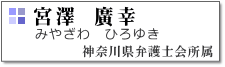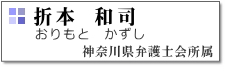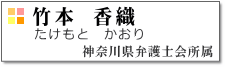ж–°е№ҙгҒ®гҒ”жҢЁжӢ¶
ж–°е№ҙгҒӮгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҰгҒҠгӮҒгҒ§гҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰпј’еәҰзӣ®гҒ®ж–°е№ҙгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮӮгҖҒгҒІгҒЁгҒҲгҒ«еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢзҡҶж§ҳгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҝғгӮҲгӮҠж„ҹи¬қз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
жҢҜгӮҠиҝ”гӮҢгҒ°гҖҒж—§е№ҙдёӯгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘж–№гҒЁй–ўгӮҸгӮҠгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘдәӢ件гӮ„жҙ»еӢ•гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹдёӯгҒ§ж”№гӮҒгҒҰеј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж—ҘгҖ…з ”й‘ҪгӮ’з©ҚгӮҖгҒ“гҒЁгҒ®еӨ§еҲҮгҒ•гҒ§гҒҷгҖӮ
жі•зҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгӮ„иЈҒеҲӨзӯүгҒ®е®ҹеӢҷгҒҜж—ҘгҖ…еӨүеҢ–гҒ—гҒҰиЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒдё–гҒ®дёӯгҒ®дҫЎеҖӨиҰігҖҒеёёиӯҳгӮ„дәәгҒ®жғігҒ„гӮӮиүҜгҒ—жӮӘгҒ—гҒҜеҲҘгҒ«гҒ—гҒҰгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒҢзӣ®жҢҮгҒҷгҒ№гҒҚи§ЈжұәгӮӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжүӢжі•гӮӮгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹеӨүеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгӮ’й–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸеҸ—гҒ‘гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгӮўгғігғҶгғҠгӮ’еәғгҒ’гҒӨгҒӨгҖҒи¬ҷиҷҡгҒ«еӯҰгҒ¶е§ҝеӢўгҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒ гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°гҒ—гҒ„е№ҙгӮӮгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹе§ҝеӢўгӮ’еҝҳгӮҢгҒҡгҖҒзңҹж‘ҜгҒ«жҘӯеӢҷгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҫгҒ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮгҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһиӮқз”ҹжӨңеҫҢгҒ®д№іе…җгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®гҒҠи©ұPart2
е…Ҳж—ҘгҖҒгҒ“гҒ®ж¬„гҒ«жӣёгҒ„гҒҹгҖҢиӮқз”ҹжӨңеҫҢгҒ®д№іе…җгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®иЈҒеҲӨгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒпј‘пј’жңҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰ第1еӣһеҸЈй ӯејҒи«–жңҹж—ҘгҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒҜдёҚеҮәй ӯгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ第1еӣһгҒ®жңҹж—ҘгҒҜеҺҹе‘ҠеҒҙгҒ®йғҪеҗҲгҒ гҒ‘гҒ§жұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®жңҹж—ҘгҒ®еүҚгҒ«гҖҒиў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒӢгӮүгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®жӣёиЁјгҒҢеұҠгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иҰӢгҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁй©ҡгҒҚгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁе«ҢгҒӘж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”е ұе‘ҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®жӣёиЁјгҒЁгҒҜгҖҒпј“йҖҡгҒ®й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҢжҖҘеӨүзӣҙеҫҢгҒ«ж’®гӮүгӮҢгҒҹXз·ҡз”»еғҸгҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®зөҗи«–гҒҜгҖҒгҖҢеҗҢXз·ҡз”»еғҸдёҠгҒ«еҮәиЎҖгӮ’гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӣгӮӢжүҖиҰӢгҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬д»¶гҒҜгҖҒжӯ»дҪ“жӨңжЎҲжӣёгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢз”ҹеҫҢ11гҒӢжңҲгҒ®д№іе…җгҒ®иӮқиҮ“гҒ«6еҖӢгҒ®з©ҝеҲәз—•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒи…№и…”еҶ…гҒ«дҪ“еҶ…з·ҸиЎҖж¶ІйҮҸгҒ®2еҲҶгҒ®1гӮ’и¶…гҒҲгӮӢ360mlгҒ®иЎҖж¶ІгҒҢиІҜз•ҷгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢиӮқз”ҹжӨңгҒ«иө·еӣ гҒҷгӮӢеҮәиЎҖжӯ»гҖҚгҒЁгҒҫгҒ§ж–ӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәӢжЎҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиЈҒеҲӨгҒ§гҒ“гҒЎгӮүеҒҙгҒҢжҸҗеҮәгҒ—гҒҹй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒд»–гҒ®иӨҮж•°гҒ®еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒӢгӮүгӮӮгҖҒгҖҢжҖҘеӨүзӣҙеҫҢгҒ«ж’®гӮүгӮҢгҒҹеҗҢгҒҳXз·ҡз”»еғҸдёҠгҒ«еҮәиЎҖгӮ’гҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӣгӮӢжүҖиҰӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜжҳҺзўәгҒӘж„ҸиҰӢгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиў«е‘ҠеҒҙгҒӢгӮүеұҠгҒ„гҒҹй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮзңҹйҖҶгҒ®ж„ҸиҰӢгҒҢиҝ°гҒ№гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒиў«е‘ҠгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиӮқз”ҹжӨңгҒ«гӮҲгӮӢеҮәиЎҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гӮ’дәүзӮ№гҒ«гҒҷгӮӢж„Ҹеҗ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ§гҒқгҒ®зӮ№гӮ’жң¬ж°—гҒ§дәүгҒҶгҒӨгӮӮгӮҠгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁгҖҒжӯЈзӣҙгҖҒдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«ж„•з„¶гҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҒ®дҫқй јгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ®ж„ҸиҰӢжӣёгӮ’пј“дәәгӮӮгҒ®еҢ»её«гҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ§еҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’жүұгҒҶгҒ“гҒЁгҒ®жңҖеӨ§гҒ®йӣЈй–ўгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүеҒҙгҒӢгӮүгҒ®зӣёи«ҮгҒ«д№—гҒЈгҒҰж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгҒӨгҒҰгӮ’й јгҒЈгҒҰгҖҒеҠ©иЁҖгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢеҢ»её«гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§иЎҢгҒ‘гӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒ„гғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйқһеёёгҒ«дёҚеҲ©гҒӘй ҳеҹҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҖҒиӘӨи§ЈгӮ’жҒҗгӮҢгҒҡгҒ«гҒ„гҒҶгҒӘгӮүгҒ°гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ®еҚ”еҠӣеҢ»гҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҢдёӯз«Ӣе…¬жӯЈгҒӘгҖҚж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰдёӢгҒ•гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҒҜгҖҒеёёиӯҳзҡ„гҒӘеҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«жңүеҲ©гҒӘеҶ…е®№гҒ®й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒҢжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚеҗҲзҗҶгҒӘй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҝЎз”ЁжҖ§гӮ’ејҫеҠҫгҒ—гҖҒзңҹе®ҹгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзңҹзӣёз©¶жҳҺгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫзҠ¶гҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒҢдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰжқҘгӮӢгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҮәгҒҰжқҘгҒӘгҒ„гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®иүҜеҝғгҒ«е§”гҒӯгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжң¬д»¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ§зңҹзӣёгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒІгҒ„гҒҰгҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жёӣгӮүгҒ—гҖҒжӮЈиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҢ»зҷӮгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҢ»зҷӮиҖ…ж–№гҖ…гҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°гҒЁеј·гҒҸжҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјҲй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҖҒйқһеёёгҒ«й©ҡгҒҸгҒ№гҒҚдҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҲҘгҒ®ж©ҹдјҡгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ“гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®ж¬Ўеӣһжңҹж—ҘгҒҜпј‘жңҲеҫҢеҚҠгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҺҹе‘ҠгҒ§гҒӮгӮӢиҰӘеҫЎгҒ•гӮ“гҒ®ж„ҸиҰӢйҷіиҝ°гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жқңж’°гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ§еӨ§еҲҮгҒӘе№јеӯҗгӮ’дәЎгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹиҰӘеҫЎгҒ•гӮ“гҒ®жғігҒ„гӮ„йЎҳгҒ„гҒҢиЈҒеҲӨжүҖгӮ„иў«е‘Ҡд»ЈзҗҶдәәгҒ«еұҠгҒ‘гҒ°гҒЁйЎҳгҒҶгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһиІҙгғҺеІ©гҒ®иЁәж–ӯжӣёгҒЁгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®е ұйҒ“гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
ж—ҘйҰ¬еҜҢеЈ«гҒ«гӮҲгӮӢиІҙгғҺеІ©гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҡҙиЎҢдәӢ件гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҖҒзӣёж’Із•ҢгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸжҸәгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҪ•гҒЁгҒӘгҒҸгҒҶгӮ„гӮҖгӮ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹе…«зҷҫй•·е•ҸйЎҢгӮ„гҖҒйҒҺеҺ»гҒ«дҪ•еәҰгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹжҡҙиЎҢдәӢ件гҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҖҒзӣёж’Із•ҢгҒ®дҪ“иіӘгҒҢж—§ж…Ӣдҫқ然гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжү№еҲӨгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜй ·гҒ‘гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒзӣёж’ІеҚ”дјҡгҒҢе…¬зӣҠжі•дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁзӯүгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚзӮ№гҒҢеӨҡгҖ…гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҒӢгӮүгҖҒе ұйҒ“гҒ®гҒ•гӮҢж–№гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒйқһеёёгҒӘйҒ•е’Ңж„ҹгӮ’иҰҡгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒ гҒҫгҒ жғ…е ұгҒҢйҢҜз¶ңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжҡҙиЎҢгҒ®дёӯиә«гҒҢгҒ©гҒҶгҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҒЁгҒӢгҖҒжҡҙиЎҢгҒ®иғҢжҷҜгҖҒеӢ•ж©ҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜж—ҘйҰ¬еҜҢеЈ«гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҮҰеҲҶгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜдҪ•гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒжң¬дәәгҒҢеј•йҖҖгҒ®ж„ҸжҖқгӮ’еӣәгӮҒгҒҹгҒЁгҒ®е ұйҒ“гҒҢжөҒгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјүгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒиҒ·жҘӯжҹ„гҖҒгҒӮгӮҢгҒЈгҒЁж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйғЁеҲҶгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«зөһгҒЈгҒҰгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгӮҢгҒЈгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢдҪ•гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҢ»её«гҒҢжӣёгҒ„гҒҹиЁәж–ӯжӣёгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҷгҒ§гҒ«гҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҢй ӯи“Ӣеә•йӘЁжҠҳз–‘гҒ„гҖҚгҖҢй«„ж¶ІжјҸгӮҢз–‘гҒ„гҖҚгҒ®жүҖиҰӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжӣёгҒ„гҒҹеҢ»её«гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮзўәе®ҡиЁәж–ӯгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гӮүгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹз–ҫз—…гҒҜгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒеҪ“еҲқгҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®еҸ–гӮҠдёҠгҒ’ж–№гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгғ“гғјгғ«з“¶дә‘гҖ…гӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮиЁәж–ӯжӣёгҒ®гҖҢй ӯи“Ӣеә•йӘЁжҠҳгҖҚгҖҢй«„ж¶ІжјҸгӮҢгҖҚгҒ®иЁҳијүгҒҢйқһеёёгҒ«гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж—ҘйҰ¬еҜҢеЈ«гҒ®иЎҢзӮәгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«жӮӘиіӘгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢй ӯи“Ӣеә•йӘЁжҠҳгҖҚгҖҢй«„ж¶ІжјҸгӮҢгҖҚгҒҜгҒ©гҒҶгӮӮжҖӘгҒ—гҒ„гҒЁгҒ®еҚ°иұЎгҒҢеј·гҒҸгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒдәӢ件еҫҢгҖҒиІҙгғҺеІ©гҒҢе·ЎжҘӯгӮ„зЁҪеҸӨгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҒ®гӮ®гғЈгғғгғ—гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®з–ҫз—…гҒ®еҫҢгӮҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢз–‘гҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳијүгҒҢеј•гҒЈгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®з–ҫз—…еҗҚгҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ®иЁәж–ӯжӣёгҒ«гҒӘгҒҸгҖҒдәӢ件гҒӢгӮүпј’йҖұй–“гӮӮзөҢгҒЈгҒҰжӣёгҒӢгӮҢгҒҹиЁәж–ӯжӣёгҒ§зӘҒ然еҮәгҒҰжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзІҫжҹ»гҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз–ҫз—…гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҜгҒӘгҒҸгӮӮгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒ„гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒӘгҒңгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҖҢз–‘гҒ„гҖҚгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘е•ҸгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢй ӯи“Ӣеә•йӘЁжҠҳгҖҚгҒ§гҒӮгӮҢгҖҢй«„ж¶ІжјҸгӮҢгҖҚгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒгӮӮгҒ—гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз–ҫз—…гҒҢз–‘гӮҸгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒйҖҶгҒ«гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁзІҫжҹ»гҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒпј’йҖұй–“гӮӮзөҢгҒЈгҒҰз–‘гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиЁҳијүгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮ„дёҚиҮӘ然гҒӘеҚ°иұЎгӮ’жӢӯгҒҲгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷпјҲгҒҫгҒҹгҖҒз–‘гҒ„гҒЁгҒ„гҒ„гҒӨгҒӨгҖҒгҖҢе…ЁжІ»пј’йҖұй–“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮеҢ»еӯҰзҡ„гҒ«гҒҜзҹӣзӣҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒдҪңжҲҗгҒ—гҒҹеҢ»её«гҒҢгҖҒйҮҲжҳҺгҒ®гӮігғЎгғігғҲгӮ’еҮәгҒ—гҖҒгҖҢз–‘гҒ„гҖҚгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒзўәе®ҡиЁәж–ӯгҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎејҒиӯ·еЈ«гҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚеҸҜи§ЈгҒӘиЁәж–ӯжӣёгҒҜгҖҒжҷӮжҠҳгӮҠгҖҒзӣ®гҒ«гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ§гӮӮгҖҒгҒӮгӮӢдәӢ件гҒ§гҖҒгҒЁгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„иЁәж–ӯжӣёгӮ’зӣ®гҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒЁгҒҜгҖҒеӮ·е®ігҒ«й–ўгҒҷгӮӢж°‘дәӢдәӢ件гҒ§гҖҒиў«е®іиҖ…гҒЁз§°гҒҷгӮӢдәәзү©гҒҢгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгҒ®иЁәж–ӯжӣёгӮ’иЈҒеҲӨжүҖгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҰжқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁҳијүгҒЁе…ЁгҒҸзҹӣзӣҫгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒЁзҹӣзӣҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒ„гҒҹеҢ»её«гҒҜгҖҒеҫҢд»»гҒ®еҢ»её«гҒ§зӣҙжҺҘиЁәзҷӮгҒ«гҒҜй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢжғ…гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒӘгҒңгӮ«гғ«гғҶгҒЁзҹӣзӣҫгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒҢжӣёгҒ‘гӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠи…№з«ӢгҒҹгҒ—гҒҸж„ҹгҒҳгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒдәӢ件гҒ®зӣёжүӢж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒиЁәж–ӯжӣёгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҰжқҘгҒҹжң¬дәәгҒҜйқһеёёгҒ«зІҳзқҖиіӘгҒ§гҖҒдёҖиЁҖгҒ§гҒ„гҒҲгҒ°гҖҒзӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜжүӢж®өгӮ’йҒёгҒ°гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ®гҒӮгӮӢдәәзү©гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜжҺЁжё¬гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒжң¬дәәгҒҢгҖҒеҹ·жӢ—гҒ«иЁәж–ӯжӣёгҒёгҒ®иЁҳијүгӮ’еј·гҒҸжұӮгӮҒгҖҒгӮҒгӮ“гҒ©гҒҸгҒ•гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҢ»её«гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зөҗеұҖгҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®иӘҝжҹ»еҳұиЁ—гҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁҳијүгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЁәж–ӯжӣёгҒ®иЁҳијүгҒҜдҝЎз”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®зөҗи«–гҒ«иҮігҒЈгҒҰдәӢгҒӘгҒҚгӮ’еҫ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜиЁәж–ӯжӣёгҒ®дҝЎз”ЁжҖ§гҒҜй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’иҰҶгҒҷгҒ®гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеӨ§еӨүгҒӘгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒиЁәж–ӯжӣёгҒ®еҶ…е®№гҒҢдәӢе®ҹгҒЁз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҖҒжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®е®ҹж„ҹгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүиҰӢгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ®еҲқжңҹгҒ®е ұйҒ“гҒ®гҒ•гӮҢж–№гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҰйқһеёёгҒ«е«ҢгҒ гҒӘгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮзңҹе®ҹгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢиЁәж–ӯжӣёгҒ®иЁҳијүгӮ’еүҚжҸҗгҒ«гҖҒж—ҘйҰ¬еҜҢеЈ«гҒҢжҘөжӮӘйқһйҒ“гҒ®дәәй–“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е ұгҒҳгӮүгӮҢгҖҒеј•йҖҖгӮӮдёҚеҸҜйҒҝгҒӘгӮҲгҒҶгҒ«е ұгҒҳгӮүгӮҢз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷпјҲзөҗеұҖгҖҒеј•йҖҖгҒ«иҝҪгҒ„иҫјгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖӮ
дёҖж–№зҡ„гҒӘжҡҙеҠӣгҒҢжҢҜгӮӢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдәӢе®ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®иІ¬д»»гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒ„гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜжұәгҒ—гҒҰгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҚжӯЈзўәгҒ§дёҖж–№зҡ„гҒӘжғ…е ұгҒ§гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒе…Ҳиө°гҒЈгҒҹе ұйҒ“гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒгғҜгӮӨгғүгӮ·гғ§гғјгҒӘгҒ©гҒ§гӮӮз„ЎиІ¬д»»гҒӘгӮігғЎгғігғҲгҒҢжәўгӮҢгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§дёӯдё–гҒ®йӯ”еҘізӢ©гӮҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒ©гҒҶиҖғгҒҲгҒҰгӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҚгҒқгӮҚгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдәӢ件е ұйҒ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰжғ…е ұгҒҢжҸғгҒЈгҒҹж®өйҡҺгҒҫгҒ§еҫ…гҒЈгҒҰжӨңиЁјгӮ’гҒ—гҒӨгҒӨе ұйҒ“гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе§ҝеӢўгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжғ…е ұгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢеҒҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮиҮӘеҲ¶гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҖгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ«жңҖгӮӮе«ҢгӮҸгӮҢгҒҹз”·гҖҚиҰіиіһиЁҳPartпј’пҪһгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒӘгҒ©
еүҚеӣһгҖҒгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҖгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ«жңҖгӮӮе«ҢгӮҸгӮҢгҒҹз”·гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒ„гҒҹйҡӣгҒ«гҖҒгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢжӣёгҒҚгҒҚгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒҜгҖҒгҒ”еӯҳгҒҳгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒзӣЈзқЈгҒҜгӮҰгӮӨгғӘгӮўгғ гғ»гғҜгӮӨгғ©гғјгҖҒдё»жј”гҒҜгӮ°гғ¬гӮҙгғӘгғјгғ»гғҡгғғгӮҜгҒЁгӮӘгғјгғүгғӘгғјгғ»гғҳгғғгғ—гғҗгғјгғігҒ§еҲ¶дҪңгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲ¶дҪңж®өйҡҺгҒ§гӮӮгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁзҙҶдҪҷжӣІжҠҳгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӯгғЈгӮ№гғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҒҜгҖҒгӮІгӮӨгғӘгғјгғ»гӮҜгғјгғ‘гғјгҒЁгӮЁгғӘгӮ¶гғҷгӮ№гғ»гғҶгӮӨгғ©гғјгҒҢдәҲе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜдәҲз®—гҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ«еј·гҒҸеҸҚзҷәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҰгӮӨгғӘгӮўгғ гғ»гғҜгӮӨгғ©гғјзӣЈзқЈгҒҜгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒеҗҢгҒҳгҒҸгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ«еҸҚеҜҫгҒ®ж„ҸжҖқгӮ’иЎЁжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ°гғ¬гӮҙгғӘгғјгғ»гғҡгғғгӮҜгӮ’дё»жј”з”·е„ӘгҒ«иө·з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮ·гғ§гғігҒ§йҒёгҒ°гӮҢгҒҹгӮӘгғјгғүгғӘгғјгғ»гғҳгғғгғ—гғҗгғјгғігҒҢгӮўгғізҺӢеҘігӮ’жј”гҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гҖҒгӮӘгғјгғүгғӘгғјгғ»гғҳгғғгғ—гғҗгғјгғіиҮӘиә«гҒ«гӮӮгҖҒжҲҰдәүгҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢиҫӣгҒ„дҪ“йЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгӮ’иҰігҒҹдёҠгҒ§гҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгӮ’иҰігҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒжңҖеҫҢгҒ®гӮ·гғјгғігҒ§гӮ°гғ¬гӮҙгғӘгғјгғ»гғҡгғғгӮҜгҒЁгӮӘгғјгғүгғӘгғјгғ»гғҳгғғгғ—гғҗгғјгғігҒҢдәӨгӮҸгҒҷгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ«гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮйҮҚгҒ„ж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғҚгӮҝгғҗгғ¬гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжңүеҗҚгҒӘгӮ·гғјгғігҒӘгҒ®гҒ§гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ®еҗҲеҗҢиЁҳиҖ…дјҡиҰӢе ҙгҒ§гҖҒгӮ°гғ¬гӮҙгғӘгғјгғ»гғҡгғғгӮҜжү®гҒҷгӮӢгӮёгғ§гғјгҒҢж–°иҒһиЁҳиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮҠгҖҒгӮўгғізҺӢеҘігҒҜй©ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгӮёгғ§гғјгҒ®еҗҢеғҡгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁйҡ гҒ—ж’®гӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҶҷзңҹгӮ’жүӢжёЎгҒҷгҒЁгӮўгғізҺӢеҘігҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӢ•жҸәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҲҘгҒ®иЁҳиҖ…гҒӢгӮүгҒ®гҖҒеӣҪ家間гҒ®иҰӘе–„й–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе°ӢгҒӯгӮӢиіӘе•ҸгҒ«гҖҒгӮўгғізҺӢеҘігҒҜгҖҒгҖҢж°ёз¶ҡгӮ’дҝЎгҒҳгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁзӯ”гҒҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҢдәәгҒЁдәәгҒ®й–“гҒ®еҸӢжғ…гӮ’дҝЎгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҒЁд»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮёгғ§гғјгҒҢгҖҢз§ҒгҒ®йҖҡдҝЎзӨҫгӮ’д»ЈиЎЁгҒ—гҒҰз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒгҖҢзҺӢеҘігҒ®дҝЎеҝөгҒҢиЈҸеҲҮгӮүгӮҢгҒ¬гҒ“гҒЁгӮ’дҝЎгҒҳгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҺӢеҘігҒҜгҖҒгҖҢгҒқгӮҢгҒ§е®үеҝғгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁиҝ”гҒ—гҖҒеҫ®з¬‘гӮҖгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰжҖқгҒ„иҝ”гҒҷгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гӮ·гғјгғігҒ®гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҺҹдҪңгӮ’жӣёгҒ„гҒҹеҪ“жҷӮгҒ®гҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒ®еҝғеўғгҒҢеј·гҒҸиЎЁгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“жҷӮгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒиҮӘиә«гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒе‘ЁгӮҠгҒ®еҗҢеҝ—гҒҢгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ«йҒӯгҒЈгҒҰгҖҒиӯ°дјҡгҒ«е‘јгҒіеҮәгҒ•гӮҢгҖҒд»Ій–“гҒ®еҗҚеүҚгӮ’иЁҖгҒҲгҒЁеј·иҰҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮ“гҒӘдёӯгҖҒгҖҢдәәгҒЁдәәгҒ®й–“гҒ®дҝЎй јгҒҢиЈҸеҲҮгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҚгҒҢеҰӮдҪ•гҒ«еӨ§еҲҮгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«жғігҒ„гӮ’йҰігҒӣгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®гӮ·гғјгғігҒ®гӮ»гғӘгғ•гӮ’жӣёгҒҚдёҠгҒ’гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жҳ з”»гҒ§гҒҜгҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒ®еҺҹдҪңгҒ«д»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгӮүгӮҢгҒҹйғЁеҲҶгӮӮгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒӢгӮүпјҲжңүеҗҚгҒӘзңҹе®ҹгҒ®еҸЈгҒ®гӮ·гғјгғігҒҜгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷпјүгҖҒгӮӮгҒ—йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҒҷгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒЁгҒ„гҒҶгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒгҒӮгҒ®жӯҙеҸІдёҠгҒ«ж®ӢгӮӢеӨ§еӮ‘дҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ«гҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„жҖқгҒ„е…ҘгӮҢгӮ’ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гӮӮгҖҒгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгҒҜеҝ…иҰӢгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖеәҰгҖҒгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«и©ұгӮ’жҲ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҳ з”»гҒ®гӮЁгғігғүгғӯгғјгғ«гҒ§гҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңжң¬дәәгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјжҳ еғҸгҒҢжөҒгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ§еҪјгҒҜгҖҒгҖҢеҗҚеүҚгӮ’еҸ–гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖгҒ„ж–№гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®иЁҖи‘үгӮ’иҒһгҒ„гҒҰйҖЈжғігҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иҠёиғҪз•ҢгҒ§гӮӮгҖҒжң¬еҗҚгҒҷгӮүеҗҚд№—гӮҢгҒӘгҒ„дҝіе„ӘгҒҢгҒ„гӮӢгҒӘгҒӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзҹҘгӮҠеҫ—гӮӢзҜ„еӣІеҶ…гҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҜжҖқжғіејҫең§гҒЁгҒ„гҒҶгғ¬гғҷгғ«гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒз«Ҝзҡ„гҒ«гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№дёҠгҒ®жҗҚеҫ—гҒҝгҒҹгҒ„гҒӘж„ҸеӣігҒ«жӢ гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒйҖҶгҒ«гҒқгҒ®зЁӢеәҰгҒ®зҗҶз”ұгҒ§гҒҷгӮүжң¬еҗҚгӮ’дҪҝгҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иҠёиғҪз•ҢгӮ„гғһгӮ№гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®дё–з•ҢгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒқгӮҢгҒ§гҒ©гҒҶгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®й–үйҺ–зҡ„гҒӘзҸҫзҠ¶гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜеј·зғҲгҒӘйҒ•е’Ңж„ҹгӮ’иҰҡгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁгӮӮгҒҶдёҖгҒӨжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҚ”еҠӣгҒ—гҒҹжҳ з”»дәәгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жҳ з”»гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгӮёгғ§гғігғ»гӮҰгӮЁгӮӨгғігӮ„гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӨ§зөұй ҳгҒЁгҒӘгӮӢгғӯгғҠгғ«гғүгғ»гғ¬гғјгӮ¬гғізӯүгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҝҳгӮҢгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгӮҰгӮ©гғ«гғҲгғ»гғҮгӮЈгӮәгғӢгғјгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҪјгҒҢгҖҒгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ§з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҪ“еұҖгҒ«еҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӨгҒЁгҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҹи©ұгҒ§гҒҷгҖӮ
дҪ•еҮҰгҒӢгҒ§иӘӯгӮ“гҒ жғ…е ұгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§еӢўгҒ®еҠҙеғҚиҖ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгӮўгғӢгғЎеҲ¶дҪңгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеҠҙеғҚйҒӢеӢ•гҒҢйӮӘйӯ”гҒ гҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒӘгӮ“гҒҰгҒ“гҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи‘—дҪңжЁ©гҒ®дҝқиӯ·жңҹй–“гҒ®е»¶й•·гҒ®и©ұгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒжӯЈзӣҙгҖҒгғҮгӮЈгӮәгғӢгғјгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮеҘҪгҒҚгҒ«гҒӘгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹй»’жӯҙеҸІгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢеӨўгҒ®еӣҪгҖҚгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жҳ з”»дәәгҒ®ејҫең§гҒ«гӮҰгӮ©гғ«гғҲгғ»гғҮгӮЈгӮәгғӢгғјгҒҢз©ҚжҘөзҡ„гҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҹй»’жӯҙеҸІгҒ®дёҠгҒ«жҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒЁеҝғгҒӢгӮүжҘҪгҒ—гӮҒгҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠгҒ®гғҮгӮЈгӮәгғӢгғјдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒ«зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒ®гӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒгғҮгӮЈгӮәгғӢгғјгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒжүӢеЎҡжІ»иҷ«гҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒҹгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒжӢҳгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгӮүгӮӯгғӘгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгӮӮжҖқгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒ‘гҒ©гҒӯгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҖҒгҒҠгҒҫгҒ‘гҒ®ж„ҹжғігҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҳ з”»гҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«иҮӘдҪ“гҒ®й»’жӯҙеҸІгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдҪңе“ҒгӮ’е•ҶжҘӯгғҷгғјгӮ№гҒ§гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжҳ з”»еҢ–гҒ§гҒҚгӮӢгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгӮ„гҒҜгӮҠгҒҷгҒ”гҒ„гҒӘгҒӮгҒЁгӮӮжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷпјҲе°ҒеҲҮжҷӮгҒ«гҒҜдҝқе®ҲжҙҫгӮүгҒ®жү№еҲӨгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖӮ
зҝ»гҒЈгҒҰд»ҠгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ§гҒ“гӮ“гҒӘжҳ з”»гҒҢдҪңгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒЁгҖҒеҪјеІёгҒ®е·®гҒ«ж„•з„¶гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иӘ°гӮӮгҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҒ®гҖҒиҮӘз”ұгҒ«гӮӮгҒ®гӮ’иҖғгҒҲгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гҖҒдјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢиҮӘз”ұгӮ’жҢҒгҒЎз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еӨ§еҲҮгҒ•гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒдёҖиҰӢгҒӮгҒЈгҒҰеҪ“然гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгӮӢгҒқгӮҢгӮүгҒ®иҮӘз”ұгӮ’жҢҒгҒЎз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еӣ°йӣЈгҒ•гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜйҒ…гӮҢгҒ°гҒӣгҒӘгҒҢгӮүгӮӮеӢҮж°—гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиҝ‘гҒ„йҒҺеҺ»гӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҰе‘ҠзҷәгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҳ з”»гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷжұәж–ӯеҠӣгҖҒе®ҹиЎҢеҠӣгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’е®ҹж„ҹгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеӢҮж°—гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢжҳ з”»гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жңӘиҰӢгҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІгҒ”й‘‘иіһгҒӮгӮҢпјҒ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҖгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ«жңҖгӮӮе«ҢгӮҸгӮҢгҒҹз”·гҖҚиҰіиіһиЁҳPart1
гҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҖгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ«жңҖгӮӮе«ҢгӮҸгӮҢгҒҹз”·гҖҚпјҲд»ҘдёӢгҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚпјүгҒЁгҒ„гҒҶжҳ з”»гӮ’пјӨпј¶пјӨгҒ§иҰігҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгӮӮгҒҶпј‘пј‘жңҲгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ«гҖҒд»Ҡе№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰдёҖеәҰгӮӮжҳ з”»йӨЁгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӨгҒҸгҒҘгҒҸгҖҒжҜҺж—ҘгӮ’гҒӣгӮҸгҒ—гҒӘгҒҸз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒӘгҒӮгҒЁе®ҹж„ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒжҳЁе№ҙе…¬й–ӢгҒ®гҒ“гҒ®гҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдҪңе“ҒгҖҒдёҖиҰӢең°е‘ігҒӘгҒҢгӮүгҖҒжңҖй«ҳгҒ«йқўзҷҪгҒҸгҖҒеҝғгҒ«ж®ӢгӮӢеӮ‘дҪңгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§иҰігҒҹжҳ з”»гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгғҲгғғгғ—гғҶгғігҒ«е…ҘгӮӢдҪңе“ҒгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒдҪңе“ҒгҒ®еҮәжқҘгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гӮӮгҒ•гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҹгҒҳгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒиҖғгҒҲгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜгҒ“гҒ®гҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдҪ•гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„дәәгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӮгҒ®гҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгӮ’жӣёгҒ„гҒҹдәәгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒиҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒҹгӮҢгӮӢж–№гӮӮгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒз§ҒгҒҢгҒқгҒҶгҒ гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ®еҲ¶дҪңз§ҳи©ұгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒҠи©ұгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дё»дәәе…¬гҒ®гғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒЁгҒ„гҒҶдәәзү©гҒҜгҖҒгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ§и„ҡжң¬е®¶гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»еӢ•гҒҷгӮӢеӮҚгӮүгҖҒе…ұз”Је…ҡгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒеҠҙеғҚйҒӢеӢ•гҒӘгҒ©гҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒЁгӮҪйҖЈгҒҢеҜҫз«ӢгҒ—гҖҒеҶ·жҲҰжҷӮд»ЈгҒ«зӘҒе…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«еӣҪеҶ…гҒ§е…ұз”Је…ҡжҙ»еӢ•е®¶гӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгӮүгҖҒгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ§жҙ»еӢ•гҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгӮӮжЁҷзҡ„гҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…ұз”Јдё»зҫ©гӮ’дҝЎеҘүгҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгғўгӮ№гӮҜгғҜгҒЁйҖЈзөЎгӮ’еҸ–гӮҠеҗҲгҒ„гҖҒеӣҪ家転иҰҶгӮ’еӣігӮӢеҚұйҷәеҲҶеӯҗгҒ гҒЁгҒ®еӣҪ家гҒҗгӮӢгҒҝгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҒҢз№°гӮҠеәғгҒ’гӮүгӮҢгҖҒзөҗжһңгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жҳ з”»й–ўдҝӮиҖ…гҒҢе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйқһзұіжҙ»еӢ•е§”е“ЎдјҡгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«е‘јгҒіеҮәгҒ•гӮҢгҖҒе°Ӣе•ҸгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ§иЎҶиҠёиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢжҳ з”»з”ЈжҘӯгҒҜгҖҒеӣҪж°‘гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ§еҪұйҹҝеҠӣгҒ®еј·гҒ„дәәгҒҹгҒЎгҒҢгӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶйқўгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒгғҸгғӘгӮҰгғғгғүгҒ§ж•°зҷҫдәәгҖҒеӣҪе…ЁдҪ“гҒ§ж•°еҚғдәәгҒҢгғ–гғ©гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгҒ«ијүгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢиҒ·гӮ’еӨұгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹжӮӘеӨўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҷӮд»ЈгӮ’жҮёе‘ҪгҒ«з”ҹгҒҚжҠңгҒ„гҒҹгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒЁгҖҒ家ж—ҸгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒеҪјгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸдәәгҒҹгҒЎгҒ®з”ҹгҒҚгҒ–гҒҫгҖҒи‘ӣи—ӨгҒЁгҒ„гҒҶйҮҚгҒ„йЎҢжқҗгӮ’гҖҒгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒгғҶгғігғқиүҜгҒҸгҖҒгӮҰгӮӨгғғгғҲгҒ«еҜҢгӮ“гҒ гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮ’дәӨгҒҲгҒҰжҸҸгҒ„гҒҹеӮ‘дҪңгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢгғҲгғ©гғігғңгҖҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒҜгҖҒиҮӘиә«гҒ®еҗҚеүҚгҒ§гҒҜд»•дәӢгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҒҪеҗҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒд»–гҒ®дәәгҒ®еҗҚеүҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰдҪңе“ҒгӮ’дё–гҒ«еҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгӮӮгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪңе“ҒгҒ§гҖҒе…¬й–ӢеҪ“жҷӮгҖҒгӮўгӮ«гғҮгғҹгғјиіһгӮ’еҸ—иіһгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҺҲиіһејҸгҒ§е‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜеҲҘгҒ®дәәгҒ®еҗҚеүҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ©гҒ“гӮҚгҒӢгҖҒиӯ°дјҡгҒ§гҖҒиҮӘиә«гҒ®иӘҮгӮҠгҒЁд»Ій–“гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ敢然гҒЁиЁјиЁҖгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӯ°дјҡдҫ®иҫұзҪӘгҒЁи¬ӮгӮҸгӮҢгҒӘгҒҚе‘ҠзҷәгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒжҠ•зҚ„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒеҪјгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®дҝЎеҝөгӮ’иІ«гҒҚгҖҒеҒҪеҗҚгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒи„ҡжң¬гӮ„еҺҹдҪңгӮ’жӣёгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒжҖқжғіиҮӘдҪ“гӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒ«гҒҷгӮӢгҖҢиөӨзӢ©гӮҠгҖҚгҒ«з«ӢгҒЎеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰиЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒеҶҚгҒіеҒҪеҗҚгҒ§гӮўгӮ«гғҮгғҹгғјиіһгӮ’еҸ–гҒЈгҒҹеҫҢгҖҒеҪјгҒҜгҖҒжҲҗй•·гҒ—гҒҹй•·еҘігҒ®еҠұгҒҫгҒ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеӢҮж°—гҒӮгӮӢе‘ҠзҷҪгҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жҳ з”»гӮ’иҰізөӮгҒҲгҒҹжҷӮгҖҒж¶ҷгҒҢжӯўгҒҫгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгҒқгҒ®жҷӮд»ЈгҖҒгҒқгҒ®е ҙжүҖгҒ«гҒ„гҒҹгӮүгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҢҜиҲһгҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁиҖғгҒҲиҫјгӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жҳ з”»гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒжҠ—гҒЈгҒҹдәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз”ҹгҒҚгҒҰиЎҢгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«еҝғгҒӘгӮүгҒҡгӮӮи»ўеҗ‘гҒ—гҒҹдәәгҖҒиЈҸеҲҮгӮҠгҖҒд»Ій–“гҒ гҒЈгҒҹдәәгӮ’е‘ҠзҷәгҒҷгӮӢдәәгҖҒдё»дәәе…¬гӮүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢдәәгҖҒдё»дәәе…¬гӮүгӮ’ж”ҜгҒҲгҖҒеҝңжҸҙгҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒ®еҝғиұЎйўЁжҷҜгҒҢе®ҹгҒ«дёҒеҜ§гҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒқгҒҶгҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒиҮӘеҲҶгҒҜгҒ©гҒ“гҒ«еұһгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®дҝЎгҒҳгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иІ«гҒҚйҖҡгҒӣгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиҝ«е®ігҒҜжұәгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒҢгғҲгғ©гғігғңгҒ®еҺҹдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжӯЈејҸгҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢпј‘пјҷпјҷпј“е№ҙгҖҒжҳ еғҸгҒ«гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜпј’пјҗпј‘пјҗе№ҙгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒд»ҠгҒ®ж—Ҙжң¬гӮ„гӮўгғЎгғӘгӮ«гҖҒгҒқгҒ—гҒҰдё–з•ҢгҒ®гҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгӮ’иҰӢжёЎгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжҺ’еӨ–зҡ„гҒӘжҖқжғігҒҢ蔓延гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӣҪеҶ…гҒ§гӮӮгҖҒжЁ©еҠӣгӮ„йҮ‘еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨдёҖйғЁгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жҘҜзӘҒгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдәәй–“гӮ’жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҖҒе ӮгҖ…гҒЁзҪ·гӮҠйҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ§гҒ•гҒҲгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжЁ©еҠӣиҖ…гҒ«йҳҝгӮӢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иӘ°гӮӮгҒҢиҮӘз”ұгҒ«иҖғгҒҲгҖҒж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҖҒиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ§гӮӮж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжҶІжі•дёҠдҝқйҡңгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжЁ©еҲ©гҒҜгҖҒжЁ©еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒжҷӮгҒ«йқһеёёгҒ«зӣ®йҡңгӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒжҖқжғіиүҜеҝғгҒ®иҮӘз”ұгҖҒиЎЁзҸҫгҒ®иҮӘз”ұгҒҜгҖҒеёёгҒ«жЁ©еҠӣиҖ…гҒ®иҰҸеҲ¶гҒ®жЁҷзҡ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжЁ©еҠӣгҒ«ж“ҰгӮҠеҜ„гӮӢдәәгҒҹгҒЎгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жЁ©еҲ©гҒ®иЎҢдҪҝиҖ…гҒёгҒ®иҝ«е®ігҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жүӢгӮ’иІёгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒжҷӮд»ЈгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡиө·гҒ“гӮҠеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒҜиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиӘ°гӮӮгҒҢжӮӘеӨўгҒ®жҷӮд»ЈгҒ®иў«е®іиҖ…гҒӘгҒ®гҒ гҖҚгҒЁгҖӮ
зҸҫе®ҹгҒ«иө·гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒйқһеёёгҒ«иҰігҒҰгҒ„гҒҰеҝғгҒҢз· гӮҒд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҳ з”»гӮ’иҰізөӮгӮҸгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«еҝғгҒҢгҒ»гҒЈгҒ“гӮҠжё©гҒҫгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҪјгҒ®з”ҹгҒҚж–№гҒҢгҖҒдҝЎеҝөгӮ’иІ«гҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒд»–иҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҜӣе®№гҒ®зІҫзҘһгҒ«жәҖгҒЎгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘеҲҶиҮӘиә«гӮӮгҒқгҒҶгҒӮгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁеӢҮж°—гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ«йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жҳ з”»гӮ’иҰігҒҰгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиӘҝгҒ№гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҹзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„дҪңе“ҒгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҢгӮёгғ§гғӢгғјгҒҜжҲҰе ҙгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҖҚгҖҢгғ‘гғ”гғЁгғігҖҚгҖҢгғҖгғ©гӮ№гҒ®зҶұгҒ„ж—ҘгҖҚгҖҢгӮ№гғ‘гғ«гӮҝгӮ«гӮ№гҖҚгҖҢж „е…үгҒёгҒ®и„ұеҮәгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдҪңе“ҒгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҳ з”»еҸІгҒ«ж®ӢгӮӢеҗҚдҪңгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘гҖҒиҝ«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢдёӯгҒ§д»–дәәгҒ®еҗҚеүҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҳ з”»гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҒ•гӮүгҒЈгҒЁгҒ—гҒӢи§ҰгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒ®жҷӮд»ЈиғҢжҷҜгҒҢдҪңе“ҒгҒ®еҲ¶дҪңгҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒе®ҹгҒҜгҖҒгғҖгғ«гғҲгғігғ»гғҲгғ©гғігғңгҒ®з”ҹгҒҚж–№гҒҢиүІжҝғгҒҸжҠ•еҪұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгғӯгғјгғһгҒ®дј‘ж—ҘгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ жӣёгҒҚгҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒPartпј’гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ